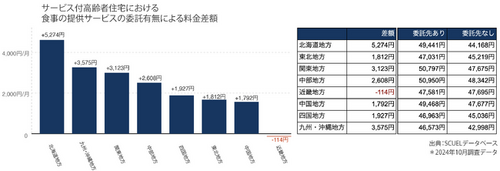物価高が直撃! 子育て家庭の食費と栄養バランスのリアルを調査
2025年4月14日(月)16時42分 マイナビニュース
森の環は2025年4月11日、「食費高騰と子どもの栄養」に関する調査の結果を発表した。同調査は2025年3月18日~2025年3月19日、小学生から高校生までの子どもがいる主婦・主夫1,021人を対象にインターネットで実施した。
はじめに、「物価高騰によって、家庭の食費はどのように変化しましたか?」と質問したところ、9割以上の人が、『大幅に増えた』(49.1%)または『やや増えた』(41.2%)と回答した。
非常に多くの人が、物価高騰による食費の負担を感じていることがわかった。特に『大幅に増えた』との回答が約半数にのぼっていることから、単なる物価上昇ではなく、日常的な食卓や買い物の仕方に明確な負担が生じている様子がうかがえる。
そこで、「物価高騰の影響で、食材の買い物にはどのような変化がありましたか?当てはまるものをすべて選んでください(複数回答可)」と質問したところ、『安い食材を選ぶようになった』(64.3%)と回答した人が最も多く、『まとめ買いや特売の活用が増えた』(42.8%)『価格比較をして安い店で買うようになった』(36.8%)と続いた。
特売や安価な食材へのシフト、まとめ買いの傾向から、家庭が日々の出費を抑えるために戦略的に買い物を工夫していることがわかる。
では、そうした節約行動の一方で、子どもの成長期において欠かせない栄養バランスの確保にはどのような難しさを感じているのだろうか。
「食費を抑えながら栄養価を維持することはどの程度難しいと感じますか?」と質問したところ、約9割の人が『とても難しい』(37.3%)または『やや難しい』(49.8%)と回答した。
非常に多く人が『難しい』と感じていることから、節約を意識した買い物を実践している一方で、食費を抑えながら栄養価を維持することの難しさを感じている様子が明らかになった。
そのような中でも、栄養価の高い食材を摂らせるには、子どもの嗜好にも配慮が必要。そこで、子どもが苦手な食材についてうかがった。
「お子さんはどの食材が苦手ですか?(複数回答可)」と質問したところ、『きのこ』(32.9%)と回答した人が最も多く、『野菜』(21.6%)『魚』(19.2%)と続いた。子どもが苦手とする食材として、栄養価の高い『きのこ』や『野菜』『魚』が上位に挙がっており、健康的な食事を実現する上でのハードルの高さがうかがえる。
続けて、「それらの食材のどのような部分に苦手意識がありますか?(複数回答可)」と質問したところ、『味』(53.7%)と回答した人が最も多く、『食感』(50.9%)『ニオイ』(34.2%)と続いた。
子どもが食材を苦手と感じる主な理由は、味や食感、ニオイなどの感覚的な要素であることがわかった。
また、子どもが苦手な食材を食べてもらうために工夫していることとして以下のような声が寄せられた。
・食べないと分かっていても食卓には出して、親が美味しく食べているのを見てもらう(30代/女性/北海道)
・好きなものと料理する(40代/女性/石川県)
・細かく切って他の食材に混ぜて食べさせている(40代/女性/滋賀県)
・子供の好きな調味料をつかって料理する(50代/女性/香川県)
・スープなどに入れてエキスとして栄養をとらせています(50代/女性/神奈川県)
子どもの嗜好に寄り添いながら、苦手な食材を少しでも食べてもらえるように工夫している家庭の様子がうかがえる。
次に、「お子さんの成長や健康のために、もっと補いたいと感じる栄養素はありますか?(複数回答可)」と質問したところ、『カルシウム』(60.8%)と回答した人が最も多く、『タンパク質』(56.6%)『鉄分』(50.2%)と続いた。
成長期の子どもにとって重要な『カルシウム』『タンパク質』『鉄分』が上位に挙がっており、保護者の多くが骨の成長や体力づくり、貧血予防などを意識していることがうかがえる。
特にカルシウムは必要性が高く認識されていることから、その吸収を助けるビタミンDについての理解もより広く認識される必要がありそうだ。
続けて、「栄養素を補うことでどのような不安を解消したいと考えていますか?(複数回答可)」と質問したところ、『免疫力が下がる』(57.3%)と回答した人が最も多く、『疲れやすくなる』(43.3%)『骨が弱くなる』(37.9%)と続いた。
最も多く挙げられたのは『免疫力が下がる』という不安であり、子どもを病気から守るために栄養補給を重要視している家庭が多いことがわかる。
加えて、『疲れやすくなる』『骨が弱くなる』といった成長や日常生活への影響も懸念されており、健康をサポートする食事の必要性が強く認識されている様子がうかがえる。
では、こうした栄養への意識が高まる中で、実際に家庭で栄養のある食事を作る際には、どのような悩みを抱えているのか。
「栄養のある食事を作るうえの悩みとして当てはまるものを選んでください(複数回答可)」と質問したところ、『栄養バランスを考えるのが大変』(58.1%)と回答した人が最も多く、『栄養のある食事のレパートリーが少ない』(33.4%)『手間がかかり続かない』(30.3%)と続いた。
多くの保護者が栄養バランスを考えることに負担を感じており、加えてレパートリーの少なさや手間の問題も課題となっているようだ。
最後に「栄養のある食事を作るうえで、重視することは何ですか?(複数回答可) 」と質問したところ、『価格が安定している』(44.9%)と回答した人が最も多く、『どんな料理にも合わせやすい』(40.6%)『スーパーで手に入りやすい』(35.4%)と続いた。
理想的な栄養摂取と現実的な調理負担とのギャップに悩む家庭にとって、使いやすさや経済性、入手のしやすさといった「日常的に続けられる条件」が重視されていることがうかがえる。
栄養価が高いだけでなく、調理のしやすさやコストパフォーマンスも、家庭での食材選びにおいて重要な判断基準となっていることが示された。
今回の調査結果から、物価高騰が子育て世帯の食生活に大きな影響を与えていることが明らかになった。
まず、9割以上の家庭が食費の増加を実感しており、節約のために安価な食材や特売の活用、価格比較などの工夫を日常的に行っている様子がうかがえる。
一方で、そうした節約行動が子どもの成長に欠かせない栄養価の維持と両立することの難しさを感じている家庭が非常に多く、栄養確保とのジレンマが浮き彫りとなった。
特に、子どもが苦手とする食材の上位に挙がったのは『きのこ』『野菜』『魚』といった、いずれも栄養価の高い食材であり、子どもの嗜好を尊重しながら必要な栄養素を摂取させるためには、メニューや調理方法に一層の工夫が求められている現状が明らかとなった。
また、保護者が補いたいと感じる栄養素としては『カルシウム』『タンパク質』『鉄分』が多く挙げられ、特に『免疫力の低下』『疲れやすさ』『骨の弱さ』といった健康への不安が背景にあることがわかった。
特にカルシウムは、吸収を助けるビタミンDとあわせて摂ることが重要であり、ビタミンDへの理解も今後さらに広まっていくことが望まれる。
しかしながら、栄養のある食事を作るうえでの現実的な悩みとしては、『栄養バランスを考えるのが大変』『レパートリーが少ない』『手間がかかる』といった負担感が上位に挙がり、限られた時間や予算の中での食事づくりに苦慮している様子がうかがえる。
そうした中で求められているのは、栄養価が高いことに加えて、『価格の安定』『調理のしやすさ』『入手のしやすさ』といった、日常的に無理なく取り入れられる条件を備えた食材であることが明らかになった。
家庭での食生活には、栄養と経済性、そして子どもの嗜好という三つのバランスを取る難しさがあり、そうした中で、手軽に使えて栄養価も高い食材を活用していくことが、毎日の食事づくりの助けになるかもしれない。