15歳で人を斬り、16歳で不良グループのトップに…戦後の東京に君臨した「伝説のアウトロー」尾津喜之助の“破天荒すぎる少年時代”――2024年読まれた記事
2025年5月3日(土)18時10分 文春オンライン
2024年、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。社会部門の第1位は、こちら!(初公開日 2024/12/28)。
* * *
戦後新宿の闇市でいち早く頭角を現し、焦土の東京に君臨した“伝説のテキヤ”尾津喜之助。アウトローな人生を歩んでいた彼は、どのようにして「街の商工大臣」と称されるようになったのか?
ここでは、ノンフィクション作家のフリート横田氏が、尾津喜之助の破天荒な生涯を綴った『 新宿をつくった男 戦後闇市の王・尾津喜之助と昭和裏面史 』(毎日新聞出版)より一部を抜粋・再構成して紹介する。(全4回の1回目/ 2回目 に続く)
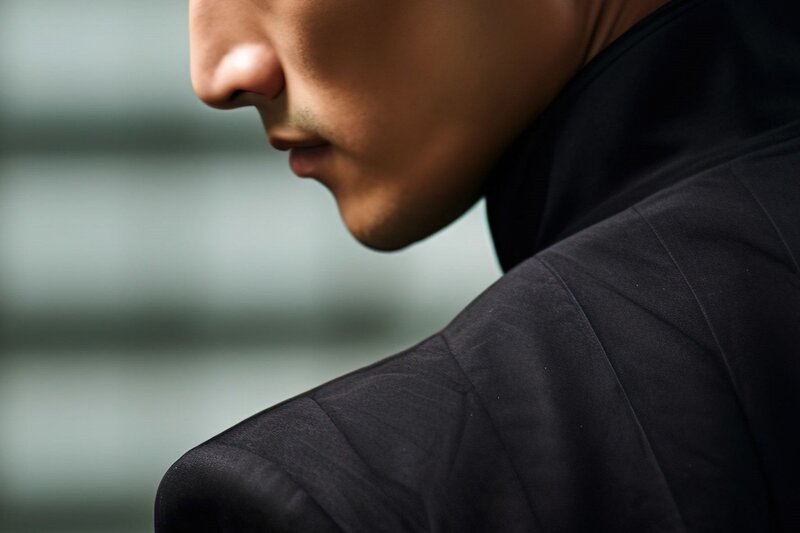
◆◆◆
継母と馬が合わなかった少年時代の喜之助
明治31年1月28日、東京本所相生町に生まれた喜之助。父は砲兵工廠(ほうへいこうしょう)の現場責任者を経て鋳物工場を営んでいた。遊び人でもあったようだが、幼少期は、中流以上の暮らしを送れていた。
母は、士族の娘だったからか、酒と女が好きだった夫に付き従うのをよしとせず、喜之助2歳のときに家を捨てた。台湾へ渡ったらしい。父は別の女性を後妻として迎える。
継母となった女性と喜之助、これがつくづく馬が合わない。幼いころから喜之助は利発で勉強ができ、14歳のころ、ナンバースクールである旧制府立第三中学校へ合格を果たしている。本人はのち、老境に至ってもこの入試で2番の成績であったことを誇った。
ところが、通うことが許されない。資金的な問題はなかった。ただ、継母がいい顔をしなかった。彼女ともしうまくやれていたなら、戦後の新宿駅前の様子は全く違っていたはずだ。結局、入学を辞退させられたとき、少年は、人生最初の大きな癇癪玉(かんしゃくだま)を炸裂させた。棒切れで継母を叩くや、そのまま、家を捨てた。
浮浪児とほとんど似た暮らし
本所の家を飛び出し、1か月ほどさまよい歩いていた喜之助。上野公園や浅草寺あたりで寝泊まりしながら、さびしさに耐えかねて泣いていた。のちの姿からは想像できないが、このころはただあどけない子どもでしかない。金もない。
物乞いをして、糊口(ここう)をしのぐしかなかった。浅草は当時、帝都随一の遊興地であり有象無象も集まっている。弱い者を狙う無法者もうろついていた。
喜之助もある日追い剝ぎにあい、身ぐるみをはがされてしまう。裸で泣いているところを、地元の不良少年グループのリーダーに拾われ、あっさり子分となってしまった。このころは、不良たちとスリやコソ泥をして歩いていた。終戦後、尾津マーケット付近に大勢いた浮浪児とほとんど似た暮らしをしていたのだ。
肉切り包丁を振り回しての喧嘩で人を斬り…
15歳、ついに、人を斬る。肉切り包丁を振り回しての喧嘩だったが、このとき少年は気付いた。自分が人より体格に優れていることと、修羅場の勇気と機転も備わっていることを。10代半ばにして喜之助は、「暴力の説得力」を身に付けてしまったのだった。
こうして大きく社会から脱線していく喜之助。刃傷沙汰によって地元にいられなくなってしまうと、進退窮まって、炭鉱へ身を隠すことにした。東京北部の炭鉱だったというから、おそらく青梅だろう。自分の身を自分で請負業者に80円で売り、逃げたのだった。この炭鉱夫暮らしの時期に、刃物に限らず、拳銃の使い方をも身に付けてしまった。
あるとき坑道内で働いていると、突如として落盤事故が発生、真っ暗闇のなかに閉じ込められてしまう。一切飲み食いはできず、闇の閉所で喜之助のほか3人の坑夫は苦しむことになった。闇は目からの情報を奪い、現実を奪い、時間の観念を奪い、無のなかで無限におのれと向き合うことを強いる。
「俺は死なない」救助されたとき、体はほとんど無傷だった
数日して救援隊が穴をあけたとき、2人は衰弱しきり、もう1人は、発狂していた。喜之助は無に引き寄せられない。ひたすら現実がやってくるのを待っていたのだった。救助されたとき、体はほとんど無傷だった。このときに確信めいた心境に至る。
「『俺は死なない』——これが俺の宗教だ。俺は人より体は大きいし、力だって5倍は強い」
確信は異様な方向へと向かっていく。乱暴さは助長され、人に金を借りて返さず踏み倒そうとも、誰からもなにも言われないから増長する一方。16歳のころには、日本刀をムシロにくるんであちこちをうろつきだし、飲み倒し食い倒しは日常茶飯事、とがめられると白刃をみせつける悪童ぶりを発揮した。
16歳で不良グループのトップに就任
誰が付けたか「鷹」という通り名で呼ばれ、当時の言い方なら与太者そのものになってしまっていた。「暴力の説得力」だけを身に付けた男。これだけの人物であったなら、もちろん筆者もとっくに筆を投げているけれど……もうすこしお付き合いいただきたい。
勉強はできたから、このころ築地の工手学校(現・工学院大学)へ入る。継母とは疎遠のままだったようで、叔父からわずかな小遣いをもらいつつ通学しはじめた。これで持ち直すか、と思われたが……むしろ、本格的なアウトローの道へ転がっていく。
大正3年、16歳となると、喜之助は「紫義団」なる一団を結成した。なんのことはない、不良グループである。小石川の円乗寺に工手学校の学生を中心に30人ほどを集めて、結団式を行い、一帯をナワバリとするグループの団長におさまったのだった。
浅草の不良グループ・赤帯組と抗争
団長就任早々、飲み屋の用心棒をやりながら、当時、辻々に新聞の立ち売りを子どもらがやっていることに目を付けた喜之助は、小川町、春日町、水道橋、本郷肴町の街角に立つ売り子を配下に組み入れ、組織化していった。
子どもらには威圧を加えて服従を強い、カスリ(上納金)をとっていったのだろう。示威力を背景とした組織を率いて利益を狙う点、路上の商売人たちを組織化する点に、のちの時代にこの男が手掛ける商法の萌芽がすでに見える。
ところが、団長におさまっていたのは束の間だった。歓楽地を抱える浅草の不良グループ・赤帯組との間でいざこざが起こり、抗争へと発展、喜之助はふたたび逃亡するはめに。今度の逃亡先は、西。大阪まで流れた。
労働者たちの蝟集(いしゅう)する飯場へもぐりこみ、すぐに左官や瓦屋の手伝いの口をみつけた。このころは、「政やん」の名乗りだったようだ。そのうち鳶の仕事も覚え、ひとりの鳶職人を子分にして、建前屋をはじめる。基礎工事を請け負う仕事といったところだろう。
喜之助にとって最初の「子分」をこのとき持つ。おそらく略式ながらも、互いに酒を酌み交わして親と子の契りを固める盃事もやったはずだ。一般市民から見れば、もはややくざと見做されてもなんら不思議はない。そう、ここでひとつの疑問が頭をもたげてくる。
尾津喜之助は「やくざ」なのだろうか?
彼は、「やくざ」なのだろうか。
戦後間もない時期に書かれたやくざ(=暴力団、とする)に触れた資料や研究をみると、やくざをまずは職種で把握しようとしているものが見受けられる。最初に登場するのは、博打打ちで、次いでテキヤや土木建設関連業(加えて港湾荷役業なども)が続き、いうなればこれらを十把一絡げでやくざと見做していることがある。
暴力をいとわないために他者との紛争を巻き起こし、一般社会からドロップアウトしてしまう人、しがちな人はいつの時代もいる。右に挙がっている業種は、出自や経歴を問わずにやる気さえあればどんな人も受け入れ、生活の立つ道を与えてきたから、社会から逸脱していく人々の受け皿となりやすかった。
若いうちに「暴力の説得力」を発見して、ほしいままに生きてきた喜之助のようなものも包含してくれたのだった。
しかし職種だけで切り出してやくざか否かを判定するのは、現在の我々のボンヤリとした認識からいっても、そぐわない。土木系など言うまでもなく、スキルを積みあげねば仕事にならない職人芸的正業なのを我々は知っている。
ならば、しきたりから見るとどうだろう。親分子分関係を結んでいるかどうかや、「兄弟分」など独特の業界用語(?)や符丁を使っているか。いや、これも筆者には単なる外装で、些末なことに思える。
では一般人かやくざかを分かつ決定的事由はなにか。
それは、本質的には「暴力を手段として商売をしているか否か」にかかっているのではないか。
テキヤは商品を露店に置き、それを売って利益を得るという実業
土木建設業は技能と筋力の組み合わせで構造物を造って利益を得、テキヤは商品を見極めて露店に置き、それを売って利益を得るという確固とした実業に違いなく、粗暴で喧嘩騒ぎを起こす者がいくらいたにせよ、暴力そのものを手段として利潤を追求してはいない。
それぞれの実務の道を究めることが美徳という世界観が用意されている。ドロップアウトした人々が業界に入っても、心を入れ替えれば、暴力から離れ、それぞれのプロとして生きる道がある。
博打打ち、博徒はその点異なる。汗をかいて働くのは野暮で、違法行為と知りながら、余人をよせつけない示威力をもって賭場を開き、維持し、そこで生きることを美徳としてきた。職人として時間をかけて技術習得したり、商人として取引先開拓をしたりして生きていく道とは異なる。
商売の構造自体がもとから示威力と結びついており、もっというなら暴力そのものを純化させ、商品化して利益を得ようとする道へと入りやすい。つまり博徒こそをまず、厳密なやくざの定義に入れていい。そして、暴力が商材というならば、このとき尾津もやくざと言っていいことになる。
なんだかややこしくなってしまったが、のちの時代、警察がやくざ分類法を完成させたことによって、一般社会のやくざ認識もまた、誠にややこしくなった。高度成長期以降、警察は暴力団の取り締まりと監視を一層強化したが、そのとき、暴力団を仕分けた方法が、さきほどの暴力で規定するやり方とは必ずしも一致しないのだ。
警察的定義に従えば、親分子分関係など外装的なことも多分に加味され、右の博徒もテキヤも同類として扱ってしまっている。
筆者が知っている現在のテキヤ団体のいくつかは、露店で物を売る商人でしかないが、暴対法、暴排条例によって、商売は相当に規制を受けている。警察から見れば、今もやくざなのである。
ややこしさを振り払いたいとき、もう一度言うが、これだけを判定材料にすればいい。
「暴力を手段として商売をしているか否か」
少々、脇道に入り込みすぎた。大正期の尾津喜之助へ戻ろう。
2024年 読まれた記事「社会部門」結果一覧
1位:15歳で人を斬り、16歳で不良グループのトップに…戦後の東京に君臨した「伝説のアウトロー」尾津喜之助の“破天荒すぎる少年時代”
https://bunshun.jp/articles/-/78660
2位:「タイプじゃない男性はお断り」「若いイケメンが話しかけると女性はホテルへ…」大阪・梅田の「立ちんぼスポット」を密着してわかった“売春ビジネス”の裏側【写真あり】
https://bunshun.jp/articles/-/78659
3位:300mの崖に宙吊りになった登山遭難者の遺体を回収する“前代未聞の作戦” 47人の自衛隊員がライフルと機関銃で撃ちロープを切断すると…
https://bunshun.jp/articles/-/78658
4位:「おれを舐めるにもほどがある!」“伝説のヤクザ”安藤昇が力道山に激怒→自宅を襲撃…安藤組と“プロレス界の英雄”が対立した経緯
https://bunshun.jp/articles/-/78657
5位:「章男くん程度の社員ならば、ごろごろいる」トヨタを世界一にしたサラリーマン社長が抱いていた“創業家への感情”
https://bunshun.jp/articles/-/78656
(フリート横田/Webオリジナル(外部転載))
関連記事(外部サイト)
- 【続きを読む】19歳で対立する組長の暗殺を計画、20歳で芸者と“駆け落ち”…「伝説のアウトロー」尾津喜之助が歩んだ波乱万丈すぎる道のり
- 【衝撃画像】イカツすぎる…戦後の東京に君臨した「伝説のアウトロー」尾津喜之助の“素顔写真”を見る
- 「ベッドの中で、2人は激しく愛し合った」“伝説のヤクザ”とセレブ女優が男女の関係に…俳優に転身した安藤昇の“凄すぎるモテ伝説”
- 「ヤクザが仕事現場にもついて来た」借金10億円超を背負い自己破産寸前…“最後の銀幕スター”小林旭が経験した“どん底生活”
- 「1日100人とヤッて、本当にキツい」風俗店に16時間勤務して“性行為漬け”…21歳の貧困女子大生が直面する“ヤバい現実”













