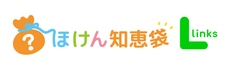みなが“自分のパイ”を奪い合うのに必死な社会でどう生きるか? 隠居制度という日本の知恵に学ぶ
2025年5月10日(土)11時0分 文春オンライン
〈 「給料はみんなで使うもの」“所有しない”ピグミー族の驚くべき知恵とは? 山極寿一と内田樹が“サル化”する現代社会を斬る 〉から続く
ゴリラ研究の第一人者・山極寿一さんと、武道家で思想家の内田樹さんによる白熱対談。高齢化社会における人間の在り方について、両氏の専門分野からの知見を交えながら語り合う。
◆◆◆◆

人間の体はちくわみたいもの!?
内田 ちょっと話は変わるんですが、『老いの思考法』を読んで「まさにそう!」と手を打ったのが、「消化器官は体の外部」という指摘でした。たしか養老孟司先生から「人間はちくわみたいなものだ」という話を伺ったことがありました。口腔から肛門まで通っているのが「ちくわの穴」で、そこを通る養分を吸収するのが「ちくわの身」という話です。この身体イメージ、僕にはとても腑に落ちるものでした。たしかに消化器って外部ですよね。
山極 そうです。だって、腸にはバクテリアが棲んでいて共生しているのだから。ある意味我々はバクテリアを食べさせていて、バクテリアが消化したものを人は取り込んでいるだけとも言えます。
内田 ゴリラのドラミング行動、あれは自分の身体を楽器として使うということですけれど、人間は自分の身体を外形化することで最初の楽器を作ったのではないかと僕は思うんです。もし人間が自分の身体を「ちくわ」みたいな円筒形のものだとイメージしていたのだとしたら、それを外形化、道具化したら「太鼓」になるはずです。
たしかに自分の身体を打楽器だと感じることがあるんです。僕は江戸時代の禊教の流れを汲む一九会という修養団体の「禊祓い」の修行に時々参加してるんですが、そこでは「トホカミエミタメ」という祝詞を唱えます。これを延々と朝から晩まで3日間唱え続けるという荒行がありますが、この祝詞の唱え方が、人間の身体を打楽器に見立てたもののように僕には思えるんです。声帯で声を出すのではなくて、全身を打楽器にして、呼気とともに祝詞を唱えて、あわせて自分の中にある邪気を全部祓ってて、心身を透明にする。実際に、呼気が弱いと、先輩たちが背中を思い切りひっぱたくんです。背中をたたかれて呼気とともに祝詞を唱えると自分がほんとうに打楽器になったような気になる。
人類が最初に作った楽器はたぶん太鼓と笛だったんじゃないかと思いますけれど、これはどちらも「円筒形のものの中を強い呼気が通り抜ける」というイメージを外形化したものですよね。たぶん太古の人間たちも、ゴリラのように自分の体を円筒形だと思って叩いて遊んでいるうちに、円筒形のものを叩けば、音が出るのではないかと気がついた。円筒形のものを叩いてみたら大きな音が出た。細い円筒形のものに穴をあけて呼気を強く吹き込んだら甲高い音が出た。そうやって太鼓と笛ができた。そういうことじゃないかという気がするんです。
ゴリラのドラミングは儀礼化された行為
山極 身体を打楽器にするって、ゴリラのドラミングが分かりやすいですが、実はあれは、九つの動作からなる非常に儀式化された行為です。
まず横に揺れて、ウーウッフフフフと息を吸い込む。すると、胸の共鳴袋に息がたまって胸が張りまるで太鼓のようになります。それから立ち上がって胸をタタタタって叩いたあと、走り出す。まわりの草や枝を引きちぎって空中にボーンと放り投げて、横走りに走って、最後に地面をバターンって叩く。こういう一連の儀式があるんです。
チンパンジーも胸は叩きませんが、足でリズムをパカパカパカパカってとり、板根(板のような根を持つ木)を叩いたりします。要はパフォーマンスとして、ある程度、目立つ定式的な行為が、ゴリラやチンパンジーにはあって、人間の祖先にもそれはあったと思います。
内田 狂言に三番叟というのがあります。たぶん今に伝わる中で最も太古的な舞の一つだと思うんですけれども、この動きがまるでサルなんです。延々と同じリズムを繰り返して、鈴を鳴らしながら、時々キーッキーッっと猿のような声を発する。見ているうちに、タイムスリップして、古代の呪術的空間に誘われてしまうような舞なんです。
山極 ここで面白いのがサルやゴリラやチンパンジーの声の出し方で、人間と一番異なるのが、彼らは呼気と吸気を音にできるんです。でも、人間は呼気しか音にならない。サルなどは、ハーモニカのように呼気と吸気の両方で音を出せるんです。
人間は二足歩行を選択して、喉頭が下がって色んな声を出せるようになった代わりに、吸気で声を出そうとすると気管支と食道に一緒に空気が流れてしまって音が出せなくなりました。だから「誤嚥」が起こるんですね。その代わり人間は、生後様々な声を学習できるようになった。サルや類人猿は、生まれつき持っている声しか出せません。
だからサルに「猿真似」はできない。相手の声や動きをまねて、学習できるのが人間に固有の特徴なんです。
身体的共鳴と武道の境地
内田 そうなんですか。僕が稽古している合気道は相手との身体的同期能力を利用する技術なんです。相手の動きにシンクロナイズすると、浅い瞑想状態に入る。そうなると、個体識別できなくなって、二人の身体が一つのものに溶け合って、それが場の「気の流れ」に従って動くようになる。うまく同期ができると、すごく気持ちがいいんです。まるで原始の時代に、人間たちが火のまわりを動きをそろえて群舞しているような陶酔感もあって。
山極 ダンスの共鳴って、人類が最初にもった重要なコミュニケーション法だと思います。その共鳴状態をつくりだすのにリズムが重要なんですね。たとえばチンパンジーはスコールがくると興奮して、集団で「ウーッホ、ウーッホ」と吸気も声にしながらレインダンスをします。あるいはゴリラは、夜になるとあちこちの群れで胸をたたいてドラミングをして、「俺はここにいるぞー」と言わんばかりに心を同調させている。
森でそういう共鳴のただなかにいると実に味わい深いものがありますが、人類においても、そういう集団的共鳴は共同体の人々への共感を高め、自己犠牲を払ってでもここの一員でありたいという帰属意識を高めたように思います。
内田 武道では「我執を去る」ということをうるさく言いますけれど、それは修行において成長の妨げになる最大の要因は「我執」だからなんです。人間関係を対立的にとらえて、目の前にいる相手に技をかけて勝とうとすることが武道では禁忌とされる。
武道家の必読書である沢庵禅師「太阿記」の冒頭には「蓋し兵法者は勝負を争わず、強弱に拘わらず、一歩も出でず、一歩も退かず、敵我を見ず、我敵を見ず」とあります。「勝負を争ってはならない」という教えから始まるんです。この章句は、僕の理解だと、勝負強弱遅速といったデジタルな二分法を排して、「天地未分陰陽不到の処に徹せよ」、つまり、まだ天地が分かれず、陰陽二極で世界が整序される前の、アナログな状態に戻れと、そう教えているんです。当然、自我もないし、他者もない。対立もない、差異もない。武道家はそういう境地に立たなければならない。
ゴリラの遊び方と合気道の共通点
山極 それを聞いて思い出したのが、ゴリラの遊び方です。たとえば、太い大木の周りを2頭の子どもがグルグル回って遊ぶとき、一方が速度を変えると、追いかけてる子が追いかけられる役割になります。ターンテイキングといって、役割を交代しながら、流れを自在に調節して遊んでいるんです。そういうやり取りは、相手の身体と同調し、調整しないと成立しません。そういう遊びのなかで、身体の共鳴ははぐくまれてきたもののようにも思いました。
内田 合気道の場合はまさにターンテイキングですね。入門して何十年という古参の門人も、初心者も、同じ技を稽古するんですが、相手の体力や練度を見ながら、互いに一番楽しく、一番高いパフォーマンスが発揮できるように役割を交代しながら身体の使い方を工夫する。技をかける人と、かけられる人を、「刀と砥石」に喩えることがあります。砥石が粗すぎたら刃は欠けてしまうし、砥石がつるつるで摩擦がなければ、それでも刀は研げない。適度な抵抗があってはじめて刀は研げる。それと同じように、相手の練度に合わせた技の使い方が必要なんです。
山極 遊びで役割交代が起きるには、「ハンディキャッピング」といって、体格のいいほうの子が、わざと動きを遅くしたりして、身体の小さいほうに合わせる必要があります。つまり、遊びにおいては小さい方がイニシアティブを握っているんですね。強いほうはハンディを付けて、遊びという対等の世界を作ってきた。
そもそも遊びは、はじめからルールがあるわけじゃない。ルールは、その場で立ち上がってくるもので、それは互いに相手の状態を推し量る中で生まれてくるものなんですよね。
ヨハン・ホイジンガが『ホモ・ルーデンス』で述べているように、遊びが人間の文明史的なルーツと考えてみたときに、こと現代社会でハンディを付けて相手に合わす「譲る心」を取り戻すことがとても大切だと僕は思っています。なんでも自分自分で権利主張をするのではなく、相手の意見を聞きながら合意をはかっていくような力。これが良い老い方だと思うし、内田さんのいう成熟にも近いように思います。
自分のパイを確保することに必死な社会
内田 そうですね。いまはほんとうにいい歳して幼児みたいな人が増えましたからね。
山極 自分のパイを確保することに一生懸命に精を出している人が多い。自分が手にしたものは手放さないぞと言わんばかりに。僕はね、つくづく戦後日本は大きく間違えたと思うんですよ。右肩上がりに経済成長し続けられると思って地球環境を破壊し、数少ない所有物を争ってパイを奪い合って、こんな悲惨な社会になってしまった。
内田 今の政治家は、さまざまな社会矛盾はすべて経済成長さえすれば解決すると思い込んでいる。それはたしかに一理あって、高度成長期はパイがどんどん大きくなっていたので、自分の取り分が増える限り、パイの分配方法についてあれこれ文句を言うやつはいなかった。でも、パイが縮みだしたら、一斉に「誰かがオレの取り分を横取りしている」と言い出した。分配の仕方がおかしい、生産性や社会的有用性を基準に分配しろ、フリーライダーを叩き出せ…という卑しい話ばかりするようになってきた。この陰惨な状態をなんとかするためには、もう一度パイを大きくするしかない。そう信じている人が日本の過半を占めている。でも、もう二度とパイが大きくなることはないんです。だったら、「仲裁人」が出てきて、誰もが同じくらい不満な適切な落としどころを提示するしかない。
民主主義ってもともと「みんなが同じくらい不満足な解」にたどり着くために熟議するというシステムなんです。「みんなが同じくらいに不満」な資源分配が、パイが縮んでいる局面で共同体の内部で対立が起きないようにするためにはたぶん最も有効な方法なんです。
隠居制度という日本の知恵
山極 そこで振り返ってみたいのは、江戸時代の知恵なんです。ヨーロッパの列強が領土を広げて各地を植民地にしていた時代に、日本の江戸時代は265年間「節約」型で領土を拡大しようとはせず、中期以降3000万人ほどの人口を養っていた。身の程をわきまえる社会性や精神性が育ったし、それが「達老」という老人の域なんですね。
内田 本にも書かれていましたけれど、それ面白い考え方ですね。
山極 「達老」の初出は11世紀の北宋時代ですが、「ものごとに通じ、俗事を自在に超えうる力をえた老人」をさす言葉です。この精神性を体現したのがまさに江戸時代の隠居制度でした。
隠居があるのは日本くらいのものですが、まだ社会で活躍できる年齢であるにもかかわらず、若い世代に自分の権利を譲り渡して、あとは趣味や教養に生きる。ご隠居さんは社会のなかで別格の存在で、たとえばお茶の世界とか、お祭り事とか共同体のまとまりを維持するうえで重要な役割を担っていたんですね。それは節約型の社会だからこそ実現できた優れた知恵だと思います。
永遠にパイを増やすことを求めて、高齢者たちが自分たちのパイを手放さなければ、やっぱりギスギスした窮屈な社会になってしまいますから。
内田 我々はもう老人なわけですけど、高齢者の仕事って物を持つことじゃないと思うんです。権力も財貨も僕たちには不要なんです。それより若い人たちに進むべき道を示すことが老人の仕事だと僕は思っています。
僕が年長者として武道で示しているのは、「天下無敵」という目標です。これは誰も到達できない無限消失点のような目標ですが、それでも武道家が進むべき道はそれしかない。そういうふうに行く先を示すことが老人に託されている大きな仕事のようにも思います。
共同体が存続するために必要なものとは?
山極 やっぱり人は共同体とのつながりが命なんですよね。最近は、自己実現、自己責任という言葉が流行っていて、「個々の能力や資産を拡大して、老後に備えなさい」と言われるけど大間違いです。人が最終的に頼るのはご縁。地縁、血縁、社縁……人と人とのつながりを大事にして、互いにもっと助け合うことを常識とするような社会をつくらなくてはいけない。そこで高齢者が貢献できることは大きいし、貧しくともお互いに頼りあっていけば幸福に生きられると思います。
内田 全く同感です。そして共同体が存続するためには、単に「一緒にいる方が安全だ。一緒にいると楽しい」というだけでなく、この共同体を毀損することなく次世代に伝えるというミッションが必要なんです。
僕の場合は武道と哲学の教育共同体ですけれども、僕はここで師から学んだ武道の哲学と技法を門人たちに「パス」しています。大学の仕事もまだしていますけれども、これも建学者がこの学校に託した建学の理念を次世代に伝えるということが僕のミッションだと思っています。
ただ自己保存のために存在するのではなく、存続することを通じて「何としても伝えるべきことがある」という「使命感」を持つ共同体は強い。ただメンバー同士で助け合う相互扶助共同体というだけの設計では必ず「あいつはフリーライドだ」「オレはずっと持ち出しで割を食ってる」と言い出す人が出てくる。今ここでの利便性をめざして作った共同体は資源分配をめぐっていずれ必ず瓦解する。でも、僕のような「ミッションを伝えるための共同体」は持ち出しで、割を食うのは制度設計の前提なんです。僕は師から豊かな贈り物を無償で頂いた。それを次世代に伝えるのは「反対給付義務」の履行なわけです。だから、僕が持ち出しで当然なんです。
共同体づくりって、大変なんですけれども、どういう共同体が豊かで楽しいものになるのか、知恵を絞って考えてゆきたいです。人はご縁で生きる存在ですからね。
山極 ひとりではなくて、つながりの中で生きることが、美しく老いることにもなると思いますね。
内田 では今日の結論は、多様なご縁を張り巡らせていく生き方が「よい老い」の作法だということで(笑)。
山極 はい、今日はよいご縁をありがとうございました。
内田 こちらこそ、ありがとうございました。
(MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店にて)
(山極 寿一,内田 樹/ライフスタイル出版)