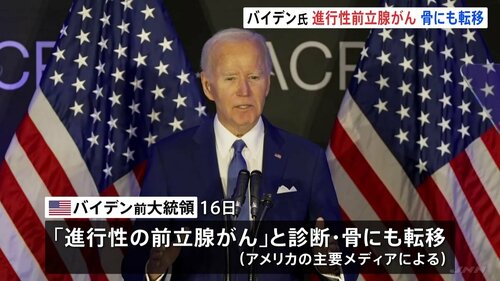村田喜代子 3年前に夫が旅立ち《背骨》のような存在が消えた。友だちの言葉から『遺された妻たちの小説を書きたい、書かなくては』と強く思って
2025年5月18日(日)12時30分 婦人公論.jp

村田喜代子さん(撮影:本社・武田裕介)
1977年「水中の声」で九州芸術祭文学賞を受賞後に本格的な執筆活動に入り、1987年に「鍋の中」で芥川賞を受賞した村田喜代子さん。近年では『飛族』で谷崎潤一郎賞、『姉の島』で泉鏡花賞を受賞。新刊『美土里倶楽部』では、夫を亡くした主人公・美土里と同じ境遇の友人の生きる姿が描かれています。執筆に際しての思いとは——(構成:田中有 撮影:本社・武田裕介)
* * * * * * *
書くことは「亡き夫探し」
夫を亡くして3年ほど経った友だちが、「気分はまだ、じゃんじゃん降りの土砂降りよ。まるで太い雨が庭に次々刺さるみたいで、如雨露(じょうろ)や鉢もひっくり返ったまま」と、夫を喪って日が浅い私に言いました。
バリバリ働く活動的な彼女が、陰では泣き暮らしていたなんて。その時「ああ、遺された妻たちの小説を書きたい、書かなくては」と強く思ったのです。
主人公の美土里(みどり)は、夫の寛宣(ひろのぶ)を亡くし、同じ境遇の友人2人と「未亡人会」とでもいうべきつきあいを始めます。お墓や供養のこと、娘とのすれ違い、喪失との向き合い方などを語り合い、さまざまな交流を通して、美土里が夫の死とともに生きていく姿を描きました。
ときどきフラッと死にたくなるなど、深い喪失のただ中にいる美土里。友人に電話で「毎日泣いてる……」と涙声で訴える彼女のように、私自身、不意にわけもわからず涙が止まらなくなり、ただもう泣きたいから泣く、ということが結構ありました。
夫は3年前、寛宣と同じく、病を得て麻痺状態からの回復途上でリハビリに励んでいたのに、肺炎を患い、ものの半月ほどで逝ってしまって。今までずっと近くにいた連れ合いがいなくなる、そのショックというのは大きなものです。
《背骨》のような存在が消えて
帰宅した美土里が、自宅の階段で転倒する場面があります。実は私も2回、階段から落ちました。私は幸い骨折せずにすみましたが、夫が亡くなると、女は「骨を患う」ことがある。車椅子生活になった人や、脊椎を傷めた人もいます。
夫婦の関係がどうあれ、長い間らにいた、《背骨》のような存在が消えて、精神的に参ってしまうのでしょうか。かと言って、生きている間に夫を大事にしろといわれても難しい話ですけどね。(笑)
同じ未亡人仲間の友だちに話を聞き、ネットや本で調べれば調べるほど、女たちの嘆き方、悼み方は千差万別であることが見えてきます。書きたい場面や題材が、次々と湧きあがりました。
仏壇に灯したロウソクの赤く揺らぐ火。娘夫婦と初めて読経したコロナ下の初盆。家にあった『地獄草紙』の図版。お盆に故人の魂を子孫が背負い、墓地から家へと連れ帰る「お精露(しょうろ)さま」の風習。
それらを繋げて物語にするのに、ひとつひとつ、納得がいくまで資料を読みこみました。
美土里と同じころに未亡人となった美子(よしこ)は、亡夫が時計職人の仕事と野鳥を観察する趣味三昧(ざんまい)の、「離れ小島の住人」だったと話し、心が通わなかった結婚生活を匂わせます。
それでも、夫がこよなく愛したタカの一種・ハチクマの渡りを美土里たちと見送りながら、そっと涙を流すのです。実際に「ハチクマが来るよ」と私に声をかけてくれる人があり、「行く行く」と駆けつけては、美土里のように空を眺めました。
気が付けば未亡人だらけ
未亡人会の最高齢、87歳の辰子(たつこ)は、亡夫を追悼する句集を編んでいる、という設定です。となると、文中に出す俳句を用意しなくてはなりません。亡き伴侶を詠んだ数多の句にあたったものの、ピンとくる作品がない。
プロが作っても、個人の深い悲嘆や孤独という感情は芸術にはなりにくい、としみじみ思いました。というわけで、辰子や美土里たちの句はすべて、楽しんで作った私の素人俳句です。
執筆にあたって、あらゆる分野で勉強の日々でした。仏壇のロウソクの火から燃焼という現象について考え、物理の先生に伺うと、もっとも遅い「燃焼」は、「呼吸」なのだそう。生きるために酸素を吸って、二酸化炭素を吐いているはずなのに、体はそれによってゆっくりと錆びていく。老化ですね。
また、人が地獄へ落ちる絵を見て、ふと深さが気になって調べると、落下まで2000年以上かかるのだとか(笑)。そのほか、お経を調べ、樹木葬を調べて。私がしていたのは結局、「亡き夫探し」だったのです。
気がつけば、私の周りも未亡人だらけ。わが家には近くに住む娘夫婦や弟たちがしょっちゅう顔を出してくれるので、ひとり暮らしの寂しさはありません。そして、最近はしゃくりあげるように泣くのが止んだことにも気がつきました。
友人たちに比べて早く立ち直れたのは、この本を書いたから。だから同じ境遇の人はみなさん、死について、夫について、書いてみるのがいいと思います。小説や俳句に限らず、日記とか、エッセイでもいい。これは本当におすすめしたいですね。
関連記事(外部サイト)
- 湊かなえ「介護ミステリに挑戦。他のおばあさんには親切にできるのに、自分の祖父母にはできない…感情と行動を分けたほうがうまくいくこともある」
- 横尾忠則「難聴や腱鞘炎も全部受け入れ、心筋梗塞で死が怖くなくなった。執着や欲望から自由になって、無為でいられる今の人生は《いい湯加減》」
- 垣谷美雨「63歳の主婦が《昭和》にタイムスリップ。不条理に抗い、中学生から人生をやり直す物語。『ふてほど』『虎に翼』のヒットに背中を押され」
- 水村美苗「日本に帰国した時、とにかく《醜い》ことに驚いた。主人公が現代日本を前にして受けた衝撃は、多くの西洋人が共有するもの」
- 久坂部羊「外務省医務官、終末期医療の医師を経て48歳で作家デビュー。上手に老いるコツは、知性を持って現状を受け入れること」