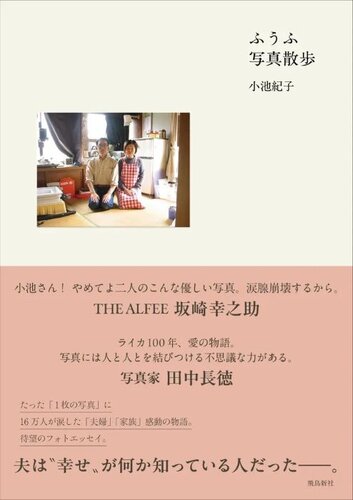人に優しくし過ぎて「相手に都合のいい人」や「優しさの押し売り人」になっていませんか?禅僧が説く<本当の優しさ>とは
2025年5月28日(水)12時30分 婦人公論.jp

(写真提供:Photo AC)
心配し過ぎる、気をつかい過ぎる、怒り過ぎる──。「私たちは日々、何かを『し過ぎる』ことで、知らず知らずのうちに心をすり減らしています。でも、ほんの少し意識をはたらかせて『し過ぎない』ことを心がけるだけで、私たちはもっとラクに生きられるのではないでしょうか」と語るのは、禅僧の枡野俊明さん。そこで今回は、枡野さんの著書『「し過ぎない」練習』から一部を抜粋し、適度なバランスを見つけるヒントを紹介します。
* * * * * * *
優しさも過ぎると、優しくなくなる
「人に優しくしなさい」
誰もが子どもの頃から教えられてきました。
「優しさ=善」と刷り込まれてきたのです。
だからでしょうか。多くの人は、優しさが足りないなんてもってのほか、優し過ぎるぐらいがよいことだと思っているようです。
「優しい人」を貫きたいあまり、自分を犠牲にして相手に優しくしたり、相手の頼みごとをすべて受け入れたりする人もいます。しかしそれは、相手にとって都合のいい人なだけです。第一、自分自身にとって優しい人ではありません。
優しさの押し売り
さらには、頼まれていないのに優しさを押し売りするような人もいます。
たまたま入った蕎麦屋さんで食べた蕎麦がとてもおいしかったとしましょう。そのことを知人に「**屋の蕎麦、とてもおいしかったですよ。機会があれば食べてみてはいかがですか」と言うのは優しさです。
ところが、「おいしかったから、これから一緒に食べに行きましょう」と、相手の事情も考えず無理に誘うのは優しさの押し売りといえます。
とてもおいしいと感じた蕎麦を、知人にも食べさせてあげたいと思う優しさは同じでも、表現の仕方ひとつで優しさが過ぎてしまいます。余計なおせっかいも、優しさの押し売りです。
本当の優しさとは、相手の気持ちに寄り添い、損得を考えず、見返りを求めず、相手のためになることを行うことです。
それは、自分を犠牲にしてまで相手に尽くし、相手の要望を何でも聞き入れることではありません。困っている人がいたら自分のできる範囲で手助けしてあげるのは当然ですが、相手に依存心を抱かせないことが、相手のためにもなる本当の優しさです。
また、相手に悪い点があるなら、それをきちんと指摘してあげることも優しさでしょう。
「優しさ」と「思いやり」は似て非なるもの
人に優しくするのはとても大切なことですが、前述のように、意識して優しくし過ぎて「相手に都合のいい人」になってしまったり、優しさを利用して自分の価値を高めようとする「優しさの押し売り人」になってはいけません。
私は「思いやり」を大切にすることで、本当の優しさに近づけるように思います。

(写真提供:Photo AC)
「優しさ」と「思いやり」は、似て非なるものです。
優しさとは相手のためになることを行うこととすれば、思いやりは、相手の身になって考え、察して、気づかうことです。思いやりは、行為や言葉よりも、「思い」が優先されます。ですから“し過ぎる”ことはありえないのです。
まずは思いやりの気持ちから
仏教の教えの根本には「慈悲」があります。
慈悲の「慈」は、生きとし生けるものの幸福を願う心、「悲」は、生きとし生けるものが苦しみや困難から解放されることを願う心です。
つまり、慈悲とは「生きとし生けるものすべてが苦しみから解き放たれ、幸せになれるように」と願うことです。
行為や言葉を含めて優しさであると思いますが、まずは思いやりの気持ちから始めてみませんか。
※本稿は、『「し過ぎない」練習』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。