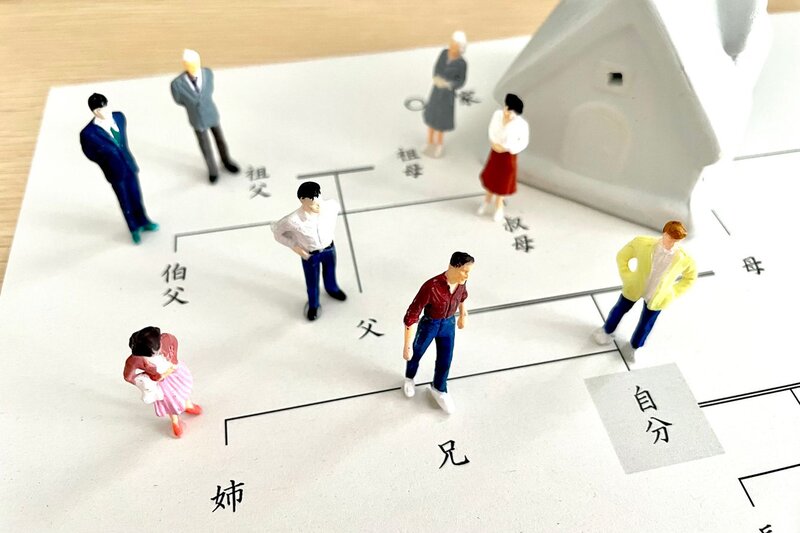「仲の悪い兄弟姉妹に1円も相続させない」は可能か…「子のいない人」が相続の仕組みで知っておくべきこと
2024年5月25日(土)9時15分 プレジデント社
※本稿は、曽根恵子監修『子のいない人の相続準備』(扶桑社)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/78image
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/78image
■「マイナスの財産」に要注意
「相続」は相続開始のとき(亡くなったとき)に存在した人に属する「財産」の一切の権利義務を継承することです。この「財産」は亡くなった人が有していた財産すべてのことで、「物」以外の契約上の地位など(賃貸借契約の貸し主・借り主の地位など)も引き継がれます。
注意したいのは、財産には「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」もあるということです。
図表1のように、プラスの財産となるのは不動産、動産、預貯金、有価証券など、マイナスの財産となるのは借金、滞納した税金などです。マイナスの財産がプラスの財産を上回ることもあるため、すべての財産を把握しておく必要があります。マイナスの財産のほうが大きい場合は、生前に返済や自己破産などで処理したいところですが、残っていれば相続放棄することもできます。
出所=『子のいない人の相続準備』
■優先順位は配偶者→子ども→両親→兄弟姉妹
相続人となるのは誰なのかを把握しておくことも重要です。相続人は民法により定められています。配偶者がいる場合は、配偶者が必ず法定相続人となります。
配偶者も子どももいない場合、親や祖父母などの直系尊属、被相続人の兄弟姉妹がいれば相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子(甥・姪)までが代襲相続できます。
出所=『子のいない人の相続準備』
■家族以外の「大事な人」に相続させる方法
子どもや孫、両親や祖父母、兄弟姉妹や甥・姪もすべていないという人の場合、まずは、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が、本当に相続人がいないかどうかを確認します。
相続では、原則として法定相続人しか財産を受け取ることができません。被相続人に法定相続人がいなければ誰も財産を受け取ることはできないということです。しかし、法定相続人ではないが被相続人と特別親しい人がいて、その人が特別縁故者と認められた場合は財産の分与が認められます。
特別縁故者と認められるのは、「内縁の配偶者、義理の息子・娘など被相続人と生計を同じくしていた人」「被相続人の療養看護につとめた人」「その他、被相続人と特別密接な関係にあった友人や知人、地方公共団体、学校法人、福祉法人などの法人」などです。
ただし、特別縁故者の要件に該当するからといって自動的に特別縁故者になれるわけではありません。家庭裁判所に申し立てを行ったうえで、特別縁故者と認められる必要があります。
被相続人に法定相続人も特別縁故者もいない場合、財産は最終的に国庫に納められます。
自分の財産を誰かに託したい場合は、遺言書に残すことで特定の相手に「遺贈」することもできます。相手は相続人以外を指定することができ、お世話になった人など個人のほか、病院や教育機関、地方自治体など団体や法人にすることもできます。
出所=『子のいない人の相続準備』
■配偶者が100%相続できるとは限らない
子どもがいない夫婦の場合、夫婦のどちらかが亡くなったとき残された配偶者が財産をすべて相続できるとは限りません。配偶者は必ず相続人となります。しかし、故人に親や兄弟姉妹がいれば、配偶者とともに相続人となります。
先ほども説明した通り、配偶者とともに相続人となれる人の範囲や順位、相続の割合「法定相続分」は民法で定められています。相続人となる人の順位は、第1順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)、第2順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)、第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥・姪)です。
法定相続分は、相続人が配偶者と第2順位の人の場合は、配偶者3分の2、第2順位の人3分の1となり、相続人が配偶者と第3順位の人の場合は、配偶者4分の3、第3順位の人4分の1となります。
■夫の母親には「遺留分」を支払わなければならない
兄弟姉妹、甥や姪と仲が良くない、交流がないなどの理由で相続させたくない場合は「財産をすべて配偶者に相続させる」という内容の遺言を残すのが有効です。
注意すべきなのは、最低限度の遺産取得割合「遺留分」があるということです。遺留分は遺言より優先され、ほかの相続人から遺留分を請求された場合は支払わなければなりません。
たとえば、「配偶者に全財産を相続させる」という遺言書があっても、故人の親など直系尊属から遺留分を請求されたら支払わなければなりません。ただし、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書が効果を発揮します。
出所=『子のいない人の相続準備』
■兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は…
子どもも配偶者もなく、直系尊属(父母や祖父母)がすでに亡くなっている場合は、自分の財産は兄弟姉妹が相続する権利を持つ法定相続人になります。また、子どもはいないけれど配偶者がいるという場合も、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるため、兄弟姉妹に財産が相続されることになります。
兄弟姉妹との諸事情や自分の意思により財産を渡したくないという人もいるでしょう。そういう場合は、「遺言書を作成し、兄弟姉妹以外の人に財産を遺贈する」「兄弟姉妹以外の人に財産を生前贈与する」といった方法で対策することができます。兄弟姉妹には遺留分(相続できる財産の最低保障額)がないので財産が相続されることがなくなります。
出所=『子のいない人の相続準備』
また、兄弟姉妹からひどい仕打ちを受けている場合は、家庭裁判所に「相続廃除」を申し立てることで、兄弟姉妹の相続権をはく奪することができる制度があります。さらに、兄弟姉妹が「相続欠格(相続を自分に有利にするために罪を犯し相続権を失うこと)」となった場合、当然のことながら財産が相続されることはありません。
ただし、相続廃除や相続欠格により兄弟姉妹が相続権を失ったとしても、その子である甥・姪がいる場合、代襲相続によって甥・姪が相続権を取得することになるので注意が必要です。甥・姪にも財産を渡したくない場合は、兄弟姉妹が相続廃除や相続欠格となったとしても、遺言書で財産の渡し方を決めておきましょう。
■生前贈与したい人は早めに着手を
事実婚のパートナー、甥や姪、親しい友人、慈善団体など第三者に財産を譲りたい場合、前述の遺贈のほかに「贈与」という方法もあります。
贈与には大きく分けて「生前贈与」と「死因贈与」があります。
生前贈与は存命中に他者に財産を渡すものです。受け取る側に贈与税がかかりますが、年間に受け取った贈与額が110万円以下の場合は非課税になるため、110万円超えの金額を贈与したい場合はこの制度を利用して1年単位で少しずつ贈与していきます。これを「暦年贈与」といいます。
出所=『子のいない人の相続準備』
ただし、受け取るのが相続人の場合は、贈与者の死亡前7年以内の贈与に贈与額が加算(生前贈与加算)されてしまいます。生前贈与したい場合は早めに行いましょう。
■「死因贈与」は書面を作成したほうがいい
曽根恵子監修『子のいない人の相続準備』(扶桑社)
相続や遺贈を受けない人は生前贈与加算の対象外です。また、婚姻20年以上の夫婦が、居住のための住宅や住宅購入資金を配偶者に贈与する場合は、最大2000万円が非課税になります。
死因贈与は、「私が死んだらこの財産を贈与する」という契約を結び、死後に贈与することです。「介護してくれたら財産を贈与する」といった条件付きの「負担付死因贈与」にもできます。契約は口約束も認められていますが、トラブルを避けるため書面を作成すると確実です。
ただし、契約となるため18歳以上(親の同意があれば未成年でも可)に限られます。また、相続税の課税対象となります。
----------
曽根 恵子(そね・けいこ)
相続実務士
夢相続代表取締役。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士。出版社勤務を経て、1987年に独立。これまで1万4600件以上の相続相談に対処してきた。著書に『いちばんわかりやすい 相続・贈与の本 '19~'20年版』(成美堂出版)など。
----------
(相続実務士 曽根 恵子)
関連記事(外部サイト)
注目されているトピックス
-
三流の管理職は「優れた前任者」と自分を比べて悩んでしまう。では、超一流の管理職は?
「仕事が遅い部下がいてイライラする」「不本意な異動を命じられた」「かつての部下が上司になってしまった」――経営者、管理職、チームリーダー、アルバイトのバイトリー…
6月17日(月)6時0分 ダイヤモンドオンライン
-
世帯年収1500万円でも「貯金ができない」という声 生活費に「毎月60万以上」かかる世帯も
物価高が続くなか、世帯年収が1500万円でも余裕はない。世帯年収1500万円の4世帯の資産状況や暮らしぶりを見てみよう。画像はイメージ東京都の40代後半の男性(…
6月15日(土)19時23分 キャリコネニュース
-
年収1100万円でも「部屋着が破れるまで着てる。靴下も穴が空いたまま」と語る女性
画像はイメージ高収入でも極限まで節約している人は多い。千葉県の40代後半の女性(事務・管理/年収1100万円)は、食品は「割引されている物しか買いません」と明か…
6月15日(土)19時22分 キャリコネニュース
-
元芸人がバイト3か月でマネジャーに昇進した納得の理由とは?
「圧倒的に面白い」「共感と刺激の連続」「仕組み化がすごい」と話題の『スタートアップ芸人お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった…
6月17日(月)6時0分 ダイヤモンドオンライン
-
【精神科医が指南】完璧主義の人が自己嫌悪に陥る「納得の理由」
誰しも悩みや不安は尽きない。寝る前にイヤなことを思い出して、眠れなくなるなんてことも……。そんなときの助けになるのが、『精神科医Tomyが教える30代を悩まず生…
6月17日(月)6時0分 ダイヤモンドオンライン
-
指原莉乃、アイドルの卒業時期に言及「“◯◯までいてほしかった”って言われるの嫌だった」「思うのは自由、本人に言うのは違う」
タレントの指原莉乃さんが7月3日、自身のツイッターで卒業に関する思いを呟いた。昨年12月にアイドルグループHKT48からの卒業を発表し、今年4月に卒業した指原さ…
7月3日(水)11時57分 キャリコネニュース
-
【精神科医が指南】アナタの隣の「面倒くさい人」への対処法・ベスト1
誰しも悩みや不安は尽きない。寝る前にイヤなことを思い出して、眠れなくなるなんてことも……。そんなときの助けになるのが、『精神科医Tomyが教える30代を悩まず生…
6月15日(土)6時0分 ダイヤモンドオンライン
-
仕事中に彼氏とLINE、3時間以上サボる後輩......逆ギレを恐れて注意できない上司にウンザリ
画像はイメージ今や、軽く指導しただけでハラスメントと言われてしまう時代である。「ハラスメントハラスメント」という言葉もある。しかし、明らかに仕事をサボっている部…
6月15日(土)19時34分 キャリコネニュース