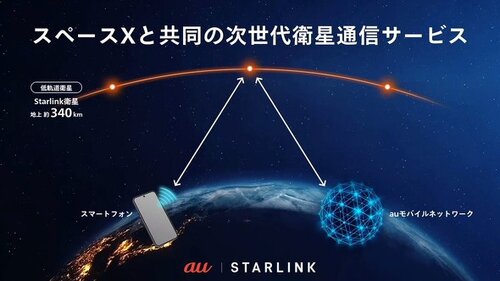温室効果ガス、来月打ち上げの衛星で観測強化…3日で地球全体を網羅し都市単位に排出量測定
2025年5月10日(土)15時0分 読売新聞
政府は新たな人工衛星「
環境省は2009年に温室効果ガス観測衛星「GOSAT」を、18年に2号機を打ち上げ、二酸化炭素(CO2)やメタンなどの大気中の濃度を測定してきた。一度に調べられるのは約200キロ・メートル間隔の「点」にとどまっていたため、国単位の観測が限界だった。
これに対し、3号機は「面」の観測が可能だ。国立環境研究所によると、幅約900キロ・メートルを同時に観測できるセンサーで地球表面をくまなく調べる。面積あたりの解像度は最大100倍に高まるため、都市単位の排出量を測定できるようになる。
また、温室効果ガスの排出源や排出量をより正確に推定することに役立つ、大気汚染物質「二酸化窒素(NO2)」も観測できる。NO2は火力発電所などで化石燃料の燃焼後に発生する物質で、3号機はCO2と同時に調べられる世界初の機能を持つ。
データは、国環研がAIなどを使って解析した上で2〜3日後にインターネットでの公開を目指す。3号機は6月24日に打ち上げられるH2Aロケット50号機に搭載される予定だ。
温暖化対策を巡っては、国際的枠組み「パリ協定」の加盟国・地域は、国連に温室効果ガスの排出量を報告しなければならない。昨年からは途上国も対象になったが、正しい統計を準備できない国もある。さらに米国が協定からの離脱を表明するなど、対策の遅滞が懸念されている。
政府は既にモンゴルやキルギスなど5か国に排出量の解析結果を提供しており、衛星を用いた検証方法の国際標準化を目指している。国環研の谷本浩志・地球システム領域長は「衛星観測による客観的なデータを国内外に発信することで、各国や企業による脱炭素への取り組みを後押ししたい」と話している。