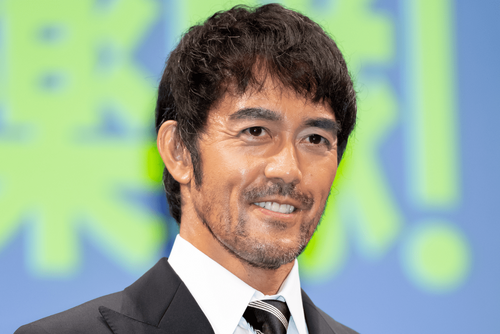「毎日1回のハグで寿命が延びるんですって」にじり寄る妻に76歳夫が後ずさりして返したザ・日本人夫婦の言葉
2025年5月28日(水)10時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Tinica
※本稿は、本川裕『統計で問い直すはずれ値だらけの日本人』(星海社)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/Tinica
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Tinica
■日本人夫婦ほど大切なことを相談しあう国民はない
国際意識調査をいろいろ調べていると、日本の夫婦については、他国の夫婦よりも相互に良好な関係を維持しているという意外とも思える結果に行き当たる。当節では、この点についての真相を探ってみよう。
まず、文部科学省所管の統計数理研究所によって行われたアジア・太平洋の11地域を対象とする価値観調査によって、各国の国民が、悩みごとをまず第一に相談する相手として、夫婦、親、友人などのいずれを挙げているかを見てみよう(図表1)。
出所=『統計で問い直すはずれ値だらけの日本人』
日本人の回答の最大の特徴は、「夫婦」と回答した者が53.2%と多く、唯一、半数を越え、最多になっている点である。
この特徴はたまたまの結果ではない。5年前にも同じ対象地域で同じ設問の調査が行われたが、「夫婦」という回答は、日本の場合、60.4%と2番目に高い台湾の47.3%を大きく引き離していたのである。
日本の回答では、「友人・知人」は13.7%で2番目の高さとなっており、他国と比較してもそう低いわけではない。むしろ、親・きょうだいに相談する割合が低い。11地域の中で「父親」は最下位、「母親」、「きょうだい」は下から2番目の割合になっているのである。日本以外では、韓国では「友人・知人」の割合が非常に高い点、また米国では「夫婦」の割合が29.8%と、11地域中、最下位である一方で「母親」が18.0%とベトナムに次いで高い点などが目立っている。米国の回答については、後段でもう一度ふれるので覚えておいて欲しい。
■夫婦同士のトラブルについて悩まない日本人
次に、以上のような、一見、仲が良さそうに見える日本人夫婦の夫婦関係の内実を探るため、別の国際比較データを見てみよう。
内閣府では、少子化対策の政策立案に資するため、5年毎に、日本を含む数カ国を対象とした国際比較調査を実施している。少子化の一因は結婚しない男女が増えているからである。そこで、「結婚生活について何が不安か」という問が設けられている。この設問で判明した不安を取り除けば結婚が増えて子どもも増えるだろうという意図である。
最新2020年の結果では、日本の場合、「結婚生活にかかるお金」への回答が42.3%と最も高く、各国比較でも他国を大きく上回る1位となっており、経済的な不安を取り除くことが特に日本では重要であることが判明している。
ここで注目したいのは、このことではなく、選択肢のうち「二人の間で起こる問題の解決」や「二人の相性」への不安が、日本の場合、かなり低く、他国と比較しても最低となっていた点である(図表2参照)。
出所=『統計で問い直すはずれ値だらけの日本人』
少なくとも2010年の段階では、当人同士のトラブルについては他国と比べてかなり心配度が低かったのである。これは図表1と同様に、夫婦仲が良い結果だったと見なすことも可能だが、単純にそうともいえない。
日本と対照的なのは米国である。米国対象の調査は2010年にしか行われていないが、米国人夫婦にとっては、日本人夫婦とは大きく異なり、生活上の困難を上回って当人同士の関係が円滑かどうかに不安が集中している結果となっていた。
世界の家族関係について実地調査を行った著名な社会人類学者である中根千枝氏によると、親から独立した小家族を古くから理想としてきた米国では、家族の中で夫婦関係は何よりも優先されるべき関係だという信条に立っており、夫婦関係は「夫婦自身の子供ですら遠慮する関係」といわれる(『家族を中心とした人間関係』講談社学術文庫、129頁)。
だから、ここで見られるように、夫婦同士がうまくいくかは、大変な心配であるようなのである。米国人が、大事なことを最初に妻あるいは夫に相談し、意見が食い違って夫婦関係が壊れるなんてことは避けたいと思うのが当然である。
従って、図表1のように、気軽に夫婦が相談しあうというようなことにはならないのであろう。言い争いになったとして最も関係が壊れにくい母親への相談が多くなるのもうなずける気がする。米国人にマザコンが多いからではない。お互い構えることのない空気のような存在が理想であるような日本人の夫婦関係とは対極的なかたちだといえる。
つまり、米国人夫婦は、必ず仲良くしなければならないと思うから夫婦間に問題がいろいろ生じるのに対して、日本人夫婦はそう仲良くしなくともよいと思っているから、結果としてトラブルも生じにくいのであろう。「夫婦喧嘩は犬も食わない」ということわざは英語にはない。
■夫婦にとって必ずしも誠実が一番とは考えていない日本人
そんなことが本当なのだろうかと思われる向きに、夫婦関係に関するもうひとつのデータを紹介しよう。
先の内閣府の調査では、2015年以降には削除されたが、2010年には「結婚生活を円滑に送る上で大切なこと」について13項目の選択肢のうち3つ選ぶ問いを設けていた。
図表3には、この結果から、13項目のうち重要性の大きな5項目のデータを掲げた。結婚生活を円滑に送る上で夫婦が「互いに誠実」であることが重要であるのは当然であろう。洋の東西を問わず、裏切りや嘘が夫婦の破綻にむすびつく例は当然多い。そこで、3つの選択でこれを挙げた回答者は、日本以外ではいずれの国も、ほぼ8割前後と最も多かった。
出所=『統計で問い直すはずれ値だらけの日本人』
ところが、日本は、これが他を上回る最多項目である点は共通であるが、回答率は何と6割以下と例外的に低かった。
男だけが誠実さを余り重視していないのではという疑いを抱く人もいるであろうから、図には、男女別の結果も付しておいた。男女でそう違いがないことが分かる。「家事・育児の分担」では各国とも女性の方が男性より大切だと思い、「性的魅力の保持」では女性より男性の方が重視しており、男女の特性差がうかがわれるが、「互いに誠実」では若干女性の方が重視している傾向にあるものの、各国ともさほどの男女差はないのである。
なお、日本人の見方のもうひとつの目立った特徴は、「性的魅力の保持」への回答率である。日本人の回答率は2.6%と極端に低く、回答率が40.6%にのぼる米国人とは極めて対照的である。夫と妻がお互いに、いつも、男としての魅力、女としての魅力にあふれていなければ結婚生活が円滑に送れないとしたら、日本人夫婦はほとんど存続不能であろう。
結論としては、日本人の夫婦は世界一「仲が良い」のではなくて、世界一「仲が悪くない」のだといえる。普通は、両者は、裏表一致するものであるが、日本人の場合は、必ずしも一致していない点が国民性のあらわれなのである。
東京新聞の「つれあいにモノ申す」という毎週掲載される投稿コラムは日本人の夫婦関係をよく映し出している。例えば、2013年3月27日「白髪が嫌いな訳」では、
伯父の葬儀に参列した時のこと。大勢の親類に会った後、夫が小声で「次からは髪の毛を染めてこい。おれが苦労させているように見られるだろ」とのたまった。その通りよ。絶対染めないわ。(もっと楽がしたい妻・65歳)
この夫にとっては、夫婦協力して、幸せな「家」の体裁を保つことが夫婦関係そのものなのである。そのためには妻に喜ばれることを頑張って行ってもいるから妻はついていけるのであろう。誠実とはいえないが、不仲ともいえない。日本人にとって夫婦は「中身」ではなく「入れもの」である。欧米人の夫婦ではこんな会話がありうるだろうか?
■「家制度」がつくった日本的な夫婦関係
このように日本人の夫婦関係が極めて風変わりなのは、私の考えでは、江戸時代中期に武士だけでなく農民や商家にまで広く普及・定着したと考えられている「家制度」の遺産である。
世界の中でも日本独自だと考えられている「家制度」は、同居する親夫婦と長男夫婦とからなる直系家族が、長子単独相続を通して、永続的に家の財産や家名を継承していく家族システムである。兄弟や親類でヨコ方向に血縁でつながる社会関係より、タテ方向の家の存続・継承そのものを優先し、場合によっては、血縁のない養子(しばしば婿養子)に家を継がせる点に他国に見られない特徴があった。
戦後、核家族化と呼ばれる動きの中で、親・きょうだいとの同居は少なくなった。家制度の下では同居して一緒に家を支えている者のみが家族と見なされる傾向が強かった。図表1で、別居している親・きょうだいでも相談相手となっている場合が多い米国と異なり、日本の場合は、家制度の影響で、親・きょうだいでも別居すると関係が疎遠になる傾向が強く、結果として、唯一同居している夫婦の相互依存が高まってきているのだといえよう。日本人の夫婦が仲良く見えるのは、「家」を支える家族が夫婦だけになってしまったからである。
本川裕『統計で問い直すはずれ値だらけの日本人』(星海社)
家制度を法制化した家か督とく制度が、戦後廃止され、相続も長子単独から男女均分に変化した。また、思想的にも愛の上に成り立つとされる欧米の夫婦関係の影響を受けるようになった。それでも、なお、日本の夫婦が古くからの独特な特徴を保っているのは、夫婦が日本的な社会関係の基礎単位として組み込まれた存在だからだと考えられる。
かつて、家制度が定着していた時代、日本の地域社会の基礎組織であるムラ(村落共同体)は、安定的に存続する序列化された同一メンバーの家々から構成され、そのため他国には例がないほどの高い社会経済機能を果たしていた。そして、近代化の中で、ムラを手本としてタテ社会を特徴とする日本の企業社会も出来上がったといわれる。
善悪の問題は別にして、日本の夫婦は、米国のように夫婦関係それ自体が人生の目的なのではなく、ムラ社会やその特徴をひきつぐ日本社会における最小単位の下位システムの役割を引き受けるという側面が強かったし、今も強い。このため、社会習慣として、夫婦はなるべく正面切って向き合わないなど、仲が悪くならないような工夫がはりめぐらされている。日本の夫婦が「仲が悪くない」のもその結果だといえよう。
■歴史的な転換点にある日本の夫婦
日本の夫婦が「仲が悪くない」といっても、それで満足している訳ではない。夫婦愛という点では先の「つれあいにモノ申す」にもうかがえるように不満が大きいのである。
愛情生活についての国際比較調査をパリに本社を構える世界的なマーケティング・リサーチ会社であるイプソス社が行っているので、それを見てみよう(図表4)。
出所=『統計で問い直すはずれ値だらけの日本人』
愛情生活に関しては「恋愛や性生活」、「愛されていると感じること」、「配偶者やパートナーとの関係」という3項目への満足度を聞いている。驚いたことに、日本は、世界最低の満足度となっている。中でも「恋愛や性生活」に対する満足度は各国と比較してもかなり低く、日本人の性生活満足度の低さを裏打ちするデータとなっている。
なお、世界の中ではタイ、ペルー、インドといった途上国で満足度が高く、主要先進国G7諸国の中で満足度の高い英国や米国も世界の中では中位水準となっている。
日本人もいつまでも満足度の低い従来型の夫婦関係にとどまってはいられない。家制度が解体してから多くの年月を重ね、前述のように社会的な脈絡から互いが空気のような存在となっていた日本人の夫婦もさすがに欧米の夫婦のように愛情を求めあう存在へと変化してきていると考えられる。
図表2で見たように、結婚生活における「二人の間で起こる問題の解決」や「二人の相性」への不安は日本でもかなり増えており、いまや、フランスやスウェーデン並みとなっている。こうした点にも愛情を重視する夫婦関係へと転換しつつある動きをうかがうことができるのである。
「つれあいにモノ申す」からもうひとつ(2020年11月18日「口は災いのもと」)。
「毎日1回ハグすると、寿命が延びるんですって」と妻。テレビで見たらしい。「私たちも……」と近づく姿に「これ以上、延びなくてもいいんじゃない?」と言いながら、思わず後ずさりした。(口が滑った・76歳)
----------
本川 裕(ほんかわ・ゆたか)
統計探偵/統計データ分析家
東京大学農学部卒。国民経済研究協会研究部長、常務理事を経て現在、アルファ社会科学主席研究員。暮らしから国際問題まで幅広いデータ満載のサイト「社会実情データ図録」を運営しながらネット連載や書籍を執筆。近著は『なぜ、男子は突然、草食化したのか』(日本経済新聞出版社)。
----------
(統計探偵/統計データ分析家 本川 裕)