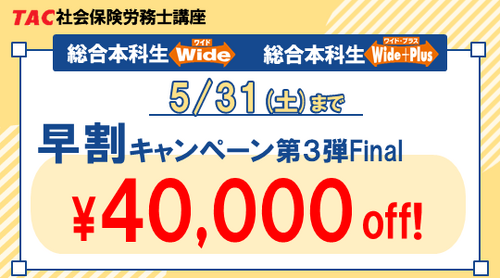休みは長く「週に4日は授業なし」も。お気楽な仕事と思われがちな<大学教員の実態>とは?考古学者「人間を扱う教員は多忙。特に私立大学は…」
2025年3月13日(木)6時30分 婦人公論.jp

(写真はイメージ。写真提供:Photo AC)
遺跡や遺構から歴史を研究する<考古学>。日々発掘調査に出かけていると思われがちな考古学者ですが、古代エジプトを専門とする駒澤大学文学部歴史学科の大城道則教授によると、ここ数年は10日連続で時間を取ることができないほど多忙を極めているそうで——。そこで今回は、考古学者の青山和夫さん、角道亮介さんとの共著『考古学者だけど、発掘が出来ません。 多忙すぎる日常』から、大城教授のリアルな日常を一部お届けします。
* * * * * * *
大学教員はお気楽で楽しげな仕事?
一般的なイメージでは、好きなことを仕事としている大学教員とは、お気楽で楽しげな仕事のように思えるだろう。
確かに7月後半から9月半ばまで夏休みがあり(大学によってその期間に前後はあるが)、2月と3月には春休みがある。なんなら年末年始に冬休みというのもあるし、上手く調整すれば週に4日は授業なしの日が作れる。
世間では残業に苦しめられている医師や医療関係者が多いと聞く。「働き方改革だ」「労働時間短縮を」と政府は叫ぶが、ニュースではこの数十年間、過労死の話題が後を絶たない。
しかし、人間を扱わねばならない大学教員も昨今は目が回るほど忙しい。ぐるぐるだ。特に私立大学の教員は、総じて仕事が多い気がする。気のせいか??? いや、絶対気のせいじゃない気がする……。
だって学生からも「先生、仕事しすぎですよ! それじゃ過労死しますよ!」と心配の言葉を聞くことがしばしばだからだ。
仕事が多い大学教員
学内業務も多岐にわたる。
ここでは詳しい内容を明らかにすることを差し控えざるをえない仕事も多い。大人の事情というやつだ。
個人情報やコンプライアンス、あるいはFD(Faculty Development)やBYOD(Bring Your Own Device)などの、耳で聞くだけではすぐには意味がわからないような単語・略語が学内の至るところで飛び交っている。
会議の数については言わずもがなである。
担当授業数
わかり易いところでは、国公立大学と比較すると担当授業数が多いというのがある(ただ大学から支給される個人研究費は総じて私立の方が多いというメリットもあるが)。
単純に授業数だけで言えば、小中高の教員の方が圧倒的に多い。しかし、彼らにはよい意味でも悪い意味でも国が判定・制定した教科書という存在があり、同じ内容を繰り返して授業することができる。

(写真はイメージ。写真提供:Photo AC)
もちろんやる気のある優秀な小中高の先生は創意工夫に溢れているし、事前の準備も厚いことであろう。
そのような先生方に教わった生徒たちは、学問の面白さや重要性を知るようになるのだ(ゆえに大学前教育が大切なのだ! 特に高等学校での!)。
隙間時間で海外調査
その一方で大学の教員は、自分の専門分野とその最前線の状況を受講生に伝える。特に歴史学や考古学という分野はまさにそういうものだ(資格に関する授業とは根本的に異なる)。だからそれらの合間(隙間)を縫って海外調査に出掛ける。現場に身を置くのだ。
しかしここ数年は、夏休みとはいえ10日連続で時間を取ることもできないほどだ。これでは継続的な現地調査はできない。発掘ならなおさらである。というか事実上不可能だ。
その現実のなかでも何とか時間を見つけて、それを研究に当てようとする。国内を主要な研究フィールドにしていればチャンスもあるが、エジプトのような海外が相手ではなかなか困難なのである。日帰りの調査は望むべくもない(韓国・台湾ならば可能か)。
※本稿は、『考古学者だけど、発掘が出来ません。 多忙すぎる日常』(ポプラ社)の一部を再編集したものです。
関連記事(外部サイト)
- 何もできないのに根拠なく、いつかチャンスが来ると信じがちな学生がエジプトの発掘調査に連れて行ってもらう方法とは?考古学者「おススメはあるアルバイトで…」
- 世間的に人気の「古代エジプト文明」。しかしヒエログリフが読めても<仕事>があるわけではなく…厳しい就職事情を考古学者が語る
- 大学職員が「ラクな職業ランキング上位」なのは当然?転職してきたら労働時間半分で年収は200万円アップ?元職員の二人が語る「理想と現実」
- 大学職員は9時5時「ラクラク勤務」で年収1000万円?後輩のお世話をしたいのに幼稚園や病院へ配属されることも?元職員の二人が語る「理想と現実」
- 「有力私大職員なら誰でも40代で年収1000万超え」の噂は事実か?すべてが嘘とは言えないが、達成には「アレ」が不可欠