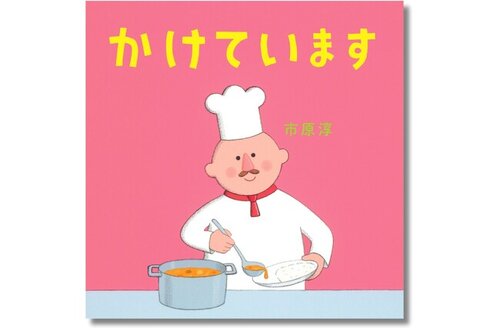13歳の殺人「アドレセンス」が描く「有害な男らしさ」見過ごす危険
2025年5月27日(火)11時0分 大手小町(読売新聞)
これは誰が少女を殺したのかを探るミステリーではない。イギリスを舞台にしたドラマ「アドレセンス」は今年3月にNetflixで配信が始まると、たちまち世界中で話題となり、各国で視聴ランキング1位に浮上。キア・スターマー英首相が製作者と懇談し、全英の中学校で無料視聴できるようになるなど「社会現象」となった。

4月上旬、引っ越しするとの連絡をくれたイギリス人の友人ジェニファーが「そういえば」とでも言うように、“Have you watched Adolescence?(アドレセンスは見た?)”と尋ねてきた。エンタメなんて興味なさそうな天才工学研究者の彼女の口から、ドラマのタイトルが出るなんて珍しい。これは、ただごとではないな、と感じた。
物語は13歳の少年ジェイミーが、クラスメートの少女を殺害した容疑で逮捕されるシーンから始まる。戸惑いを隠せない加害者家族、犯行の動機や証拠を捜査する男性刑事、ジェイミーの精神状態と判断能力を探る女性臨床心理士……。あどけなさを残す主人公を取り巻く大人たちの葛藤をわずか4話に収め、途切れなくカメラを回し続ける「ワンカット」で撮影された映像が、社会にはびこる不安や緊張を浮かび上がらせる。
「インセル(不本意な禁欲の略語)」、「ミソジニー(女性蔑視)」、「トキシック・マスキュリニティ(有害な男らしさ)」、そしてそれらの総称である「マノスフィア」が、「アドレセンス(思春期)」の若者たちの複雑で繊細な感情によって浮き彫りにされた。
マノスフィアとは、「man(男)」と「sphere(領域)」を合わせた造語で、主にインターネット上で「男らしさ」にこだわる考え方に用いられ、フェミニズムや女性に対する偏見の強い「男性至上主義」を指す。「非モテ」などと嘲笑の対象とされる理由を女性のせいと恨む考え方がある一方、腕っぷしの強さや
ジェイミーはそれらをソーシャルメディアで学び、アルゴリズムによってさらに過激なものに触れ、影響されていったと想像される。「一生童貞!」などとクラスメートからいじめられていたことも描かれる。コントロールの利かない感情、突発的な怒り、そして孤独。さらに、思春期の若者とどう向き合えばよかったのかと悩む大人たちの姿からは、教育現場や家庭のコミュニケーションに問題があったのだろうかとも考えさせられる。
女性の臨床心理士ブライアニーとジェイミーとの対話シーンを中心とする第3話は、特に思春期らしい悩みの背後にマノスフィアを想起させられた。会話が「男らしさ」になると、ジェイミーは鋭く意図を嗅ぎ取り、「父親に影響されたわけじゃない」と断言する。「モテ」「性的なこと」「SNSの絵文字の意味」などに話題が及ぶと、感情が抑えられず怒りを爆発させる。
聴く側の目的が何であれ、相手に耳を傾け、理解しようとして空間と時間を差し出す行為は、聴かれる側の生き方や欲求を吐露させる。「女性に受け入れてほしい、でも女性が自分に従わないのは許せない」、そしてもっと根本にあるものは「誰でもいい、誰かに受け入れてほしかった」という思い。自分が温めていた自分なりの「優しさ」「親密な感情」(それがどんなにエゴイスティックなものであれ)を受け止めてほしかった、と。
第3話は、人の行為や感情を「インセル」や「ミソジニー」という一言でカテゴライズする危うさを教えてくれるエピソードでもある。SNSカルチャーやマノスフィア、孤独や不安、不安定な自尊心のやり場に悩む思春期の子どもに手を差し伸べられない社会では、若い男の子たちは誰でも「ジェイミー」になり得るのだ。
製作者の一人、ジャック・ソーンは、以前の作品でも、「male rage(男性の怒り)」を一つのキーワードとして描いている。それがミソジニーやホモフォビア(同性愛者嫌悪)と結合すると危ない。
思い出した人がいる。私がスコットランドのグラスゴー大学で修士課程にいた時の元カレのことだ。ドラマの主人公のようなmale rageを持っていて、一度だけ、感情が
環境系のコンサル会社で働いていた彼は、背が高く、目の青い、いたって普通の大学出のアイルランド系イギリス人男性だった。父は医者で家は裕福だった。ただ彼は、時々感情が異常に昂ることがあった。それは怒りだったり、喜びだったり。
そのことが起きたのは、スコットランドの涼しい夏の日だった。ムスリムの友人たちにインタビューをしていた私は、彼らと一緒にラマダーン(断食)をしていた。日没の遅いスコットランドの夏のラマダーンは、食事を口にできるのが日没後の夜の9時も過ぎてからだ。
その日、「断食明けを待つから、一緒に中華料理を食べよう」とご飯を食べずに待っていてくれた彼は、うれしそうに中華屋に電話してデリバリーを頼んだ。しかし、からっぽのおなかに脂っこい中華料理を急に入れてしまったせいで、私は5分もしないうちに吐き気を催した。「ごめん、気持ち悪い。ちょっと横になるね」と言って私はベッドルームに行った。
すぐにドアがバンッ!と開いた。「俺が待っててやったのに、なんで食べられないんだよ。ふざけるな!」とどなり、彼は左手で横たわっている私の首をつかみ、右手に持った大きなプローンクラッカー(
混乱した。一体何が起きているのか理解できなかった。気持ち悪さが高まった。どう反論していいかもわからず、そしてけんかできるほどの英語能力も当時はなかった。ほんの1分もなかった。彼は部屋を去り、私は混乱と気持ち悪さのうちに眠りについた。
ただ不愉快だったのなら、彼はその辺りの物でも投げつけ、蹴り飛ばしていただろう。私が男友達なら、手を出さなかっただろう。ジェイミーもそうだったように、「女性に受け入れてほしい、でも女性が自分に従わないのは許せない」のだ。自分より下等なものが自分の“優しさ”をありがたく受け止めないなら、自分が怒るのは正当。心のどこかに隠れているミソジニーは、ひょんなことで顔を出す。
ケンブリッジで私が教える学生の一人がこう言った。
「ロンドンのワーキングクラスの多い地域の中学校に通っていましたが、在学中に学生2人と、学生の父親1人が地元の若者にナイフで刺されて殺されています。特に11〜12歳頃になると、男の子たちが急に変わりだすんです。ナイフを持っていることは、クールだと思っている様子でした。社会学の授業で『女は家庭に戻れ!』って叫んだ男の子もいたし。男の子たちは確かにミソジニーや有害な男らしさ、ソーシャルメディアや同調圧力の中にいるように見えました」
友人のイギリス人男性は「思春期」のもどかしさについてこう語った。「中学や高校時代、『インセル』『バージン』って言われるのが一番の侮辱だった。女の子にモテるってのは大切なことで、それは『あいつは普通だ』って思われるためだったと思う。正直、数年生まれるのが遅かったら、もっとおぞましいネット情報やいじめに絡まれてたんじゃないかって思う」
「最近のイギリスでは、何人もの女性が若い男性に殺されているからね。ドラマはイギリスのリアルな闇を映し出しているんだと思う」。冒頭の友人ジェニファーはそう言って、「でもね、よかったことは、このドラマが多くの人を団結させて、意識を高めたってこと」
私は10年近くイギリスにいるのに、イギリスのそんな闇など知らなかった。それほどオープンに語られてこなかったからに違いない。議論のチャンスすらなかったのかもしれない。このドラマを機に、イギリスでは子どもを持つ親や政治家らが、「有害な男らしさ」やSNSのあり方について、活発に議論するようになった。私はここに、イギリスの希望を見る。さて、日本はどうかな、と思う。(ケンブリッジ大講師 代田七瀬)