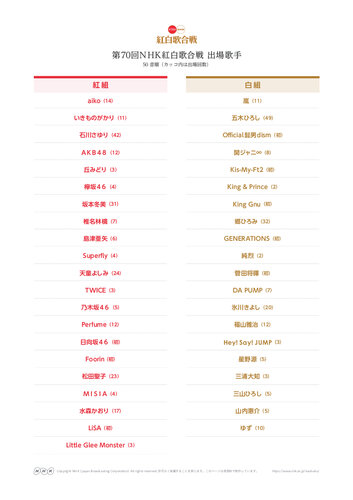カネでもない、気力でも体力でも時の運でもない…美空ひばりの分刻みのスケジュールを支えた昭和の鉄道
2025年4月18日(金)9時15分 プレジデント社
戦後の大スターだった美空ひばり=1981年、東京・日本武道館[出典=『歴史のダイヤグラム〈3号車〉』(朝日新書)]
■夜行列車を重宝した美空ひばり
一九五八(昭和三三)年三月二〇日、京都22時55分発東京ゆき急行「彗星(すいせい)」に、美空ひばりが乗った。数ある夜行急行のなかで、「彗星」は唯一、ほぼすべて2・3等寝台車で編成されていた。この寝台車は快適だったようで、「汽車の音を子守唄に、グッスリ寝こんでしまい」(『胸に灯りをともす歌』上)、8時31分着の横浜で降りた。
ひばりはすでに大スターの座にあった。鉄道を使い、公演の旅に出ることも少なくなかった。地方では、列車が駅に停(と)まっている間に大勢のファンが車内になだれ込み、サインをせがまれることもあった(『ひばり自伝』)。そのせいか、夜行列車を重宝するようになった。
太秦(うずまさ)の東映京都撮影所での仕事が多かったひばりは、東海道本線の夜行列車をしばしば利用した。五六年から東京と九州を結ぶ寝台特急が走り始めたが、関西に行く場合は東京と大阪や神戸を結ぶ急行のほうが便利だった。
一九五七年から六〇年まで月刊誌に連載されたひばりの日記には、東京で仕事を済ませてから夜行の急行に乗り、翌朝京都に着くや太秦の撮影所に向かう記述がいくつもある。最も利用したのは、東海道新幹線開業前日の六四年九月三〇日まで走っていた「彗星」だった。快適なうえ、下りも上りも時間帯がよく、利用しやすかったからだろう。
当時、ひばりはまだ二〇代前半で、寝ている間に移動できる夜行列車はありがたかったに違いない。だが年齢を重ねるにつれ、その移動が苦痛になっていったようだ。
■分刻みのスケジュールを支えた国鉄ダイヤ
一九八三年五月一一日朝6時、上野に着いた列車からひばりが降りた。青森を前日の20時15分に出た寝台特急「はくつる2号」だった。
「ああ疲れた!/昨夜の汽車の寝台ではとてもねむれなかった……/体が小さいくせにせまいベッドが嫌いだ!/どちらを向いても手が痛い!/椅子のくぼみで腰が痛い!/なんとねづらいベッドよ……」(『川の流れのように』)
若いころとは異なり、ほとんど眠れなかった様子がひしひしと伝わってくる。
ひばりが乗ったのは、昼間は普通の特急として走り、夜間は寝台車に変身する583系という車両だった。ボックス型の席が寝台になるため、下段だとどうしても窪(くぼ)みができてしまう。これが耐え難かったようだ。
美空ひばりが歌手として活躍した時代は、公共企業体としての国鉄の時代とほぼ重なっていた。それはまだ新幹線網が確立しておらず、全国の主要幹線に夜行列車が走っていた時代でもあった。ひばりの分刻みのスケジュールは、昼夜を問わずダイヤ通りに走る国鉄によって支えられていたと言っても、過言ではないだろう。
戦後の大スターだった美空ひばり=1981年、東京・日本武道館[出典=『歴史のダイヤグラム〈3号車〉』(朝日新書)]
■谷崎潤一郎、戦況悪化で再疎開へ
時は遡る。兵庫県魚崎町(現・神戸市東灘区)に住んでいた谷崎潤一郎が静岡県熱海市に別荘を購入したのは、太平洋戦争が勃発した翌年の一九四二(昭和一七)年四月だった。
谷崎は家族を魚崎に残し、単身で熱海に移住して小説「細雪」の執筆に没頭した。戦況が悪化する四四年からは空襲を避けるべく、家族も熱海に疎開させた。しかし四五年になり、東京などで空襲が激しくなると、海沿いの熱海も安全でないと判断し、五月に魚崎にいったん帰ってから岡山県の津山に家族で再疎開することを決めた。
熱海から魚崎に帰るには、まず東海道本線の列車で大阪まで行き、大阪で同線の普通電車に乗り換えて魚崎の最寄り駅である住吉まで行く必要があった。当時の時刻表を見ると、熱海—大阪間を直通する下り列車は七本あった。このうち四本が、熱海を夕方から未明にかけての時間帯に出る夜行列車だった。
谷崎は話し合った末、五月六日に熱海21時39分発の大阪ゆきに乗ることにした。他の夜行に比べて停車駅が少ないことから、谷崎はこれを「準急」と記した(『疎開日記』)。空襲、特に小型機の機銃掃射の可能性を考えれば昼行よりも夜行のほうが安全とされたうえ、前日の夜に東海道各所で空襲があり、連日はないと判断したことが決め手となったようだ。
■関西ならではの風景に戦争の影なし
大阪ゆきの列車は混んではいたが便所に行けないほどではなく、静岡で席が空いたので谷崎自身が座った。浜松、名古屋でまた席が空き、家族全員が座ることができた。名古屋駅付近は一面焼け野原になっているのが、深夜の車窓からもわかった。谷崎はウトウトしただけで目覚めると、もう夜が明けていた。
「米原を過ぎて近江路に入れば新緑の空美しく晴れて真になつかしき関西の景色なり。木々の枝ぶり若葉の色等到底関東辺のものならず矢張此方へ逃げて来てよき事をしたりと思ふ。熱海の小庵の柿若葉も美しかりしが此処(ここ)のは一層鮮(あざや)かなり。熱海を立つ時は流石(さすが)に後髪を引かるゝ思ひもせしが此れにて未練なく関東を思ひ切るを得たり」(同)
朝の光を浴びて美しく輝く五月の若葉に、谷崎が目を見張っている様子が伝わってくる。久々に目のあたりにした関西ならではの風景に、戦争の影はなかった。
京都の東西本願寺も、東寺の塔も、鉄橋で渡る鴨川や桂川の流れも変わっていなかった。京都府から大阪府に入る山崎や高槻のあたりも同様で、「素晴らしき初夏の景色」(同)だった。
列車はダイヤ通りに走り、8時過ぎに大阪に着いた。「幸にして警戒警報だにも遇(あ)はず、大阪駅頭より見たる街上も何等(なんら)変りなし」(同)。谷崎は移りゆく車中からの風景に現実をしばし忘れることができたのだ。
「細雪」を執筆中の谷崎潤一郎=1948年、京都の自宅で[出典=『歴史のダイヤグラム〈3号車〉』(朝日新書)]
■「飛び恥」で見直される欧州の夜行列車
二〇二三年五月二五日にベルギーの首都ブリュッセルとドイツの首都ベルリンを結ぶ夜行列車が走り始めたのに続き、一二月一一日にはフランスの首都パリとベルリンを結ぶ夜行列車が九年ぶりに復活した。
欧州では、格安で乗れる航空機が増えたことでいったん廃れた夜行列車が、見直されつつある。二〇二一年一二月には、パリ—ウィーン間に一四年ぶりに復活した。いまではウィーンから欧州二〇都市に向けて走っている。
背景にあるのは、「飛び恥」(フライト・シェイム)という意識の広がりだ。温室効果ガスを多く排出する航空機での移動を恥じる一方、排出量が少なく、ゆったりと移動できる夜行ならではの旅が見直されているのだ。
日本ではどうか。現在走っている定期の夜行列車は、東京と高松・出雲市を結ぶ特急「サンライズ瀬戸・サンライズ出雲」しかない。東京や大阪から九州、東北、北海道などに向かっていた夜行は、全廃されてしまった。
■スピードだけがサービスではない時代へ
東京と九州を結ぶ夜行として最後まで残っていたのは、東京—熊本・大分間に走っていた特急「はやぶさ・富士」だった。この特急が二〇〇九(平成二一)年三月のダイヤ改定で消えることが発表されると、NHKのニュースにも取り上げられた。
西鹿児島(現・鹿児島中央)発東京行きの寝台特急「富士」=1979年4月23日、東海道本線の三島—函南間、著者撮影[出典=『歴史のダイヤグラム〈3号車〉』(朝日新書)]
驚いたのは、熊本県八代市出身の八代亜紀さんが、ニュースで夜行の思い出を語っていたことだ。ぜひともお会いして、直接話をうかがいたいと思った。その願いは、「夜汽車と演歌と人の情……」(『中央公論』二〇一〇年一一月号)でかなえられた。
原武史『歴史のダイヤグラム〈3号車〉 「あのとき」へのタイムトラベル』(朝日新書)
八代さんは、地方コンサートのため乗った夜行で過ごした時間がいかに豊かだったかを力説されつつ、「東京—九州間の寝台特急を、もう一度走らせることはできないものでしょうか?」「これからは“リタイア組”がどんどん増えるわけでしょう。寝台特急で九州に旅したいという人は、たくさんいるんじゃないですか」などと夜行復活への思いを語られた。
それから一五年が経ち、八代さんの言葉はいよいよ現実味を帯びている。時代がようやく、スピードだけを売りにしないサービスを求めるようになってきたからだ。
インバウンドが拡大すれば、「リタイア組」ばかりか外国人にも夜行列車が広く受け入れられるだろう。いや日本人の出張族にも、夜行復活は朗報になる。
なぜならいまや、東京でも地方でもホテル代が高騰しているからだ。欧州のように車内設備を充実させれば、夜行列車のイメージが変わる可能性は十分にある。あとは鉄道会社がいかにスピード一辺倒を脱し、時代の変化に応じたサービスができるかどうかにかかっている。
----------
原 武史(はら・たけし)
政治学者
1962年生まれ。放送大学教授、明治学院大学名誉教授。早稻田大学政治経済学部卒業、東京大学大学院博士課程中退。専攻は日本政治思想史。98年『「民都」大阪対「帝都」東京──思想としての関西私鉄』(講談社選書メチエ)でサントリー学芸賞、2001年『大正天皇』(朝日選書)で毎日出版文化賞、08年『滝山コミューン一九七四』(講談社)で講談社ノンフィクション賞、『昭和天皇』(岩波新書)で司馬遼太郎賞を受賞。他の著書に『皇后考』(講談社学術文庫)、『平成の終焉』(岩波新書)などがある。
----------
(政治学者 原 武史)