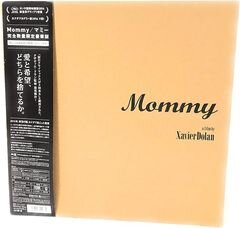スーパー戦隊50周年記念『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』特撮監督・佛田洋が語る、巨大ロボのアイデアを生み出すための秘訣とは?
2025年5月8日(木)11時30分 マイナビニュース
今年はスーパー戦隊シリーズ第1作『秘密戦隊ゴレンジャー』(1975年)が放送開始してから50年というアニバーサリーイヤー。カラフルに色分けされた仮面のヒーローがチームワークを活かし、人類を脅かす邪悪な敵を倒すというヒーロードラマは、時代と共に装いを少しずつ変えながら、子どもたちの「純粋な夢」と「正義の心」を育み続けてきた。
スーパー戦隊50周年記念スタッフインタビューの今回は、「特撮研究所」の代表を務め、『地球戦隊ファイブマン』(1990年)以降、歴代スーパー戦隊シリーズの特撮演出を手がけてきた佛田洋さん。毎回、奇想天外な変形や合体をする戦隊ロボの、巨大で雄々しい姿はいかにして創造されるのか。最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』(2025年)の特撮演出を中心に、「スーパー戦隊 特撮の秘密」を佛田監督に尋ねてみよう。
——『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の「テガソード」はゴジュウジャーの変身アイテム&武器でもあり、同時にゴジュウジャーが乗り込む巨大ロボットでもあるという、一風変わった存在になりましたね。バンダイと商品開発を行う段階で、佛田監督からはどのようなアイデアを出されたのですか。
テガソードって、玩具商品だと「手」の前にソードがつき出ている形状なんです。僕はまず、手の形状をはっきり見せたかったので、ソード部分を後ろに折りたたんだ形で登場させたかったんですよね。
商品のギミックだとソードの開閉はロボット形態のときに行うもので、手の形態だと指の部分に干渉して、うまく後ろに回らない。でもバンダイさんからは「映像は映像、商品は商品」と割り切ってくださったので、映像で見せられるようにしました。完全にソードが後ろに回らないけれど、できるだけ商品でも再現できるようにしていただけるように、考慮してもらいまして。それが企画の初期のころに僕が出した意見です。
とにかく「手」であることをアピールしようとして、巨大戦でもソードで斬ったりせず、全体を使ってチョップとかするでしょう。そういうのが面白いかなって話し合いましたね。
——スーパー戦隊シリーズの巨大ロボットは、鎧武者のような無骨なデザイン・造形というイメージがありますが、今回のテガソードは下半身がスリムで、ずいぶんフットワークが軽そうな印象を受けました。このシルエットについて、狙いを教えてください。
ここ数年、プロデューサーや監督は「動けるロボがいい」って言うんです。最近だと
『騎士竜戦隊リュウソウジャー』(2019年)の「キシリュウオー」が一番動けるし、好きなキャラクターですから、テガソードも「キシリュウオーを目指そう」と頑張った結果、まあまあ動けるスーツができました。造型は商品の設計途中段階から作り始めていて、デザインが完成するのと同じくらいのタイミングで出来上がるんです。
僕個人の好みとしては、ゴーカイオー(海賊戦隊ゴーカイジャー/2011年)や大獣神(恐竜戦隊ジュウレンジャー/1992年)のような、ゴツゴツしていてやや動きにくそうなのがよくて、ビクトリーロボ(救急戦隊ゴーゴーファイブ/1999年)なんか、これぞ戦隊ロボの醍醐味だと思っているんだけど、そういうのばかりやっているわけにはいきませんから、今回の『ゴジュウジャー』は動けるロボのほうに振り切りました。
——通常の作品では、まずヒーロー(主役側)が変身して、その後に巨大ロボ戦がある印象ですけれど、第1話はそのパターンではなく、最初に巨大ロボ戦、続いて遠野吠がゴジュウウルフに変身していましたね。
プロデューサーの松浦(大悟)くんが最初のころから、そういうこと言っていたんだよね。『特命戦隊ゴーバスターズ』(2012年)を例に挙げて、巨大戦と等身大戦を別々にわけて描きたいという。演出的には難しいんだけどね。僕は等身大戦をやって、やがて敵が巨大化して、ロボが出て……というのをやりたい派なんです。古いから(笑)。でも「こういうことやりたいけど、できますか」と発注されたら、臨機応変に対応します。
放送が始まって何人かの反応をうかがいましたが、パターンをあれだけ崩してもみんな面白がってくれるんだなあと感心しました。僕はどうしても巨大戦の特撮のことばかり気にするんですけど、試写でエピソード全体を観ていると、ゴジュウジャーそれぞれが手にテガソードを持っていたり、喫茶店「テガソードの里」の神棚にテガソードが祭られていたり、まんべんなく存在がアピールされていて、ちゃんと考えられているなあと思いましたね。
——ゴジュウジャーが召喚すると、雲間から巨大な手の形をした飛行物体が出現するという映像イメージのインパクトが強烈です。あのテガソードはどのようにして撮影されたのですか。
今回、実物を作ったのはロボット形態のテガソードだけで、巨大な手はCGです。最初に松浦くんと、いかにテガソードの「手」の部分を印象付けるかのアイデアを出し合いました。ただのメカではなく「神秘のメカ」なんだということで、表面のディテールをいつものCGよりも細かく描きこんだりして、ただものではないものがやってきたぞというイメージを大事にしています。雲の中からテガソードが飛来するカット、あれを最初に作りましたね。
昔からの「スーパー戦隊」ファンの方ならピンとくるかもしれませんけど、あれはジャガーバルカン(太陽戦隊サンバルカン/1981年)やゴーグルシーザー(大戦隊ゴーグルファイブ/1982年)のような、巨大母艦が暗雲を突き破りながら発進する、まさにあのカットの再現です。CG制作チームが子ども時代にあのころの作品で育ってきたから、もうこちらから何も言わなくても「あれだよね」「あれですね」でわかっちゃう(笑)。何十年も前から、そういった種をまいていたというわけです。
——テガソードが巨大な手から人型ロボに変形するシークエンスは、重たい金属がゆっくり形を変えていくプロセスが丁寧に描かれているのが強く印象に残りました。
指がガチャン、と動いたあと、自重で少し戻ったりするでしょう。ああいう動きがあるとすごくリアル感が出ます。あれもこちらから何か要望を出したわけじゃないんです。CGチームが優秀だからこそ、表現できた動きです。アングルも一発目に出してくれたものが、もう正解でした。これですねって(笑)。
——とほうもなく大きな「手」が空を飛んでくるビジュアルについて、佛田監督的には矢島信男特撮監督(特撮研究所・創設者)が手がけた『ジャイアントロボ』(1967年)の敵「巨腕ガンガー」がイメージとしてあったりしましたか。
巨大な手といえばガンガーだなって、僕が子どものころは矢島監督の特撮で頭の中にすりこまれていましたからね(笑)。松浦くんは『勇者ライディーン』(1975年/東北新社)の「大魔竜ガンテ」のイメージだって言っていたなあ。シンプルなものが一番子どもの心に響くんだ、という考えは、今も昔も変わらないです。
——変形後のテガソードレッドの「目」にあたる位置に、ゴジュウウルフ(吠)のコクピットがせりあがってくるカットがカッコいいですね。まるで70年代の合体ロボットアニメを思わせるシャープな演出だと思いました。
ちょうど制作中にフィリピンの実写版『ボルテスV レガシー』が劇場公開していたんです。松浦くんから「コクピット移動やりたい」とリクエストがあったので、じゃあやってみようと。実写ボルテスVは上からコクピットが降りてくるので、こっちは下からせりあがる。まったく同じではいけませんからね。と思ったらアニメのボルテスは下からだった(笑)。
——第1話冒頭では、歴代「スーパー戦隊」巨大ロボット群や、バリドリーンなどのメカが力を出し切って動けなくなっている図が見られました。あれはどのようにして撮影しているのでしょうか。
中央のところだけは、過去のスーパー戦隊シリーズに出てきたロボたちのスーツを置いています。特撮研究所の美術の松浦君チームが相当頑張って配置してくれましたね。見事でした。更に周りにいる無数のロボやメカたちは、商品を写真に撮ったものをはめこんでいるんです。これは助監督の小串(遼太郎)君が凝ってくれて、画面上のロボとかメカはひとつもダブっていないんです。あれだけの数だから、僕もひとつひとつチェックできるものではないんだけど、そこは彼のこだわりでやってくれました。
——『ゴジュウジャー』は現在放送中の『仮面ライダーガヴ』と同じく、スケジュールの見直しが図られているとうかがいました。従来よりも特撮シーンの撮影スケジュールも前倒しになったはずですが、それによって撮影そのものに何か影響が出たりしましたか。
ただクランクインが早くなるだけなので、特撮班としては問題なかったです。何かあったとすれば、打ち合わせが前倒しになるため、撮影スタートの時点で第1,2話の台本がギリギリ上がった、みたいなタイミングになってしまったことかな。特撮は先のエピソードの分も撮りますから、今日は第10話のロボ戦を撮影するけど台本がない……なんて場合もありました。
そこで松浦くんと相談しながら、この話にはこういう戦闘シーンが必要になるだろうと、台本に出てくるであろう描写を想定しつつ、画コンテを描きはじめるんです。それを意識してもらい、脚本の(井上)亜樹子さんが台本に反映してくれるという。ただ台本でもロボット同士の格闘をどうするか、までは書かれていないですから、ある程度は僕たちスタッフで考えるんです。
——設定やビジュアルがシナリオより優先する場合もあるんですね。逆に、シナリオの中で佛田監督が「面白い」と思ったロボの描写なんてありますか。
第2話で、吠が操縦するテガソードレッドが自分のソードで地面を掘り起こし「お宝」がないか探すカットがあるでしょう。ああいう発想は僕にはないですから、こりゃ面白いと思って撮っていましたね(笑)。
——第2話のテガソードイエローは敵のアイアイザー・クロサンドラとパワーファイトを展開しました。決め技が相手の両手両足をホールドしながらパイルドライバーを決めるという、『キン肉マン』の「キン肉ドライバー」に酷似したものになったのは、佛田監督のアイデアなのですか。
最初に言い出したのは田﨑(竜太)監督ですね。最初に僕が描いたコンテでは、テガソードイエローは怪力が自慢だから、殴り飛ばされたアイアイザーがすごい勢いで向こうに飛んでいく、みたいなシーンだったんですけれど、これを観た田﨑監督から「犬神家(の一族)みたいになるのはどうですか」とアイデアをもらいました。『犬神家の一族』の、湖から逆さに足が突き出ている有名な場面のことですね。
そして、ちょうど深夜にテレビで放送していた『キン肉マン』を観ていて、ふと「テガソードイエローにキン肉ドライバーをやらせよう」と思いついたんです。テガソードイエローのスーツアクターの藤田洋平くんごとクレーンで吊り上げて、アイアイザーのほうは危険なのでスーツの中にスポンジをつめて、よーい、ハイ! ってキン肉ドライバーを決めると、田﨑監督の要望どおりにアイアイザーが逆さまになって、とても面白いカットになりました(笑)。こういうアイデアのキャッチボールが戦隊特撮の面白いとこですね。
——テガソードイエローとアイアイザー・クロサンドラが廃ビルをはさんでパンチをぶつけあう場面は迫力がすごかったです。これはデジタル合成やCGではなく、ミニチュアを直接破壊する「撮りきり」カットなのでしょうか。
ビルに火薬を仕込んで、生の一発撮りでやりました。ああいうカットはCGでは迫力が出せません。立ち回りをやっている間は、この廃ビルは画面に出てこなくて、壊すところで急に出てくる。でも勢いで押しているから、誰も気づかないでしょう。ミニチュアを廃ビルという設定にしたのは、さすがに人が大勢働いているビルだと、粉々に壊してしまうのはよろしくないかなと思ったから。せめてもの、僕らの良心です(笑)。
——今や、CGやデジタル技術の発達によって想像力のおもむくまま、無限のスケールでロボットや敵怪獣のバトルシーンが描けると思うのですが、スーツによる肉弾戦やミニチュアを直接爆破するような、昔ながらの撮影手法も大切にされていますね。
もうCGはどんな物体でも作れるし、デジタル合成でいくらでもエフェクトがかけられるんです。打撃を受けて火花が散る、なんていうのも合成で作ることができるのですが、すべての映像がCGだけになると、迫力の面で弱くなる。できるだけ現場で実物を撮って、そこで足りない要素をちょっと足すくらいがちょうどいいんです。そういうところ、昔はできなかったから、今の環境はほんとうに助かっています。
——テガソードのスーツが目の前に存在するからこそ生まれる重み、質量感というものも大切なんですね。
第1話でテガソードが必殺技を決めて、爆発を背に受けて着地するシーンがあるでしょう。あそこは敵を貫いて空中でソードからロボに逆変形して降下してくるところまでがCGで、着地する直前スーツに切り替えているんです。ずっとスーツのままでもなく、ずっとCGというわけでもない、こういう画面が観たいなら、こことここにどういう技術を用いるか、みたいな考え方でやっています。
第1話で僕が一番好きなのは、戦いを始める前、正面を向いて歩いてくるテガソードレッドのカットです。ただ、ゆっくり歩いてくるだけなんだけど、ロボットらしさ、重みが感じられるよね。個人的には、もうちょっとゆっくり歩いていてもよかったかなって、今は思いますけど。
——また、リアリティの対極で、巨大ロボが市街地で戦っているのに背景がいきなり格闘技のリングや応援席に変わったりする、イメージ優先のビジュアルも「スーパー戦隊」ではおなじみの演出ですね。
「K-1」や「RIZIN」などを意識してね(笑)。ああいった理屈抜きの部分もまた、スーパー戦隊ならではの演出だと思っています。ロボットを街の中に置いて、巨大に見せる撮影手法にもこだわりますが、ときどきこういうのをやると楽しいじゃないですか。
——佛田監督が「スーパー戦隊シリーズ」で特撮監督になったのは『地球戦隊ファイブマン』(1990年)ですから、今年で35周年になりますね。1年に一度、合体・変形メカや巨大ロボを演出する中で、毎回ユニークなアイデアを生み出すための秘訣を教えてください。
特撮やCGクリエイターを志す人へのアドバイスみたいになるかもしれないけれど、特撮ジャンルの作品だけを観ていると、作る画が同じになってしまいかねません。普通のテレビドラマ、映画とか、いろんな作品を観ることで、その中からときどきフッといいヒントが出てくる場合が多いんです。
わかりやすい例で言うと戦闘機の空中戦や時代劇での燃える城とかを可能な限り「本物」らしく表現するのが特撮の根本ではあるんですが、スーパー戦隊の場合は独特の世界観があって、リアルだけでなくとことん「面白さ」を追求するってところも大事かなと思います。『ゴジュウジャー』でもロボ戦でいろいろ素っ頓狂な演出をつけたりすると、現場スタッフから笑い声が出てきますしね(笑)。みんなが楽しんで、盛り上がりながら作品を作っていく。そういった環境があるからこそ、いいものが生まれるんだと思います。
——「スーパー戦隊シリーズ」も今年で誕生50周年を迎えます。佛田監督が手がけられた作品の中で、お気に入りを挙げるならどれになりますか?
『五星戦隊ダイレンジャー』(1993年)の「気伝獣 龍星王」とかは今でも好きですね。あれはミニチュアモデルを吊って、クネクネと動かしているんだけど、あの動きはCGだとなめらかになりすぎて、あの独特の雰囲気にはならないんです。龍星王のミニチュアは動きにクセがあって、ふと気を抜くと進行方向からそれていくので、そうならないよう無理にひっぱったりしていました。そういった、実物の予測できない動きをすべてCGで表現するのは難しいんです。
龍星王のほかにも、『轟轟戦隊ボウケンジャー』(2006年)のゴーゴービークルの地下ドックからの発進シーン、『鳥人戦隊ジェットマン』(1991年)のジェットマシンが飛びまくるオープニング、『超獣戦隊ライブマン』(1988年)のランドライオンのしなやかな走りなんて、今も気に入っています。
——将来的に、佛田監督が演出してみたい「特撮映画」のアイデアがあれば、ぜひ教えてください。
往年の『ジャイアントロボ』みたいな「巨大ロボット特撮映画」をやってみたいという思いはありますよ。『救急戦隊ゴーゴーファイブ』の第1話みたいに超巨大災害から逃げ遅れた人たちを救うため、新しい現代の99マシンが「TOKYO MER」ばりに活躍して最後はやっぱりレスキューロボに合体して救出!みたいなやつ。ミニチュアワーク主体の特撮でやったら面白くなるでしょうね。あ、それじゃまるでサンダーバードだ(笑)
(C)テレビ朝日・東映AG・東映
秋田英夫 あきたひでお 主に特撮ヒーロー作品や怪獣映画を扱う雑誌・書籍でインタビュー取材・解説記事などを執筆。これまでの仕事は『宇宙刑事大全』『大人のウルトラマンシリーズ大図鑑』『ゴジラの常識』『仮面ライダー昭和最強伝説』『日本特撮技術大全』『東映スーパー戦隊大全』『上原正三シナリオ選集』『DVDバトルフィーバーJ(解説書)』ほか多数。 この著者の記事一覧はこちら