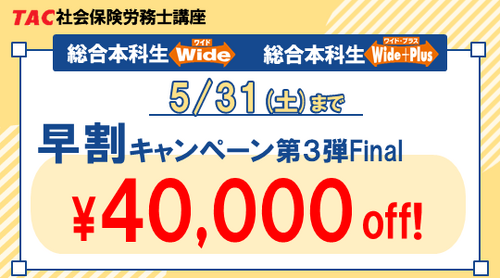何もできないのに根拠なく、いつかチャンスが来ると信じがちな学生がエジプトの発掘調査に連れて行ってもらう方法とは?考古学者「おススメはあるアルバイトで…」
2025年3月11日(火)6時30分 婦人公論.jp

(写真はイメージ。写真提供:Photo AC)
遺跡や遺構から歴史を研究する<考古学>。日々発掘調査に出かけていると思われがちな考古学者ですが、古代エジプトを専門とする駒澤大学文学部歴史学科の大城道則教授によると、ここ数年は10日連続で時間を取ることができないほど多忙を極めているそうで——。そこで今回は、考古学者の青山和夫さん、角道亮介さんとの共著『考古学者だけど、発掘が出来ません。 多忙すぎる日常』から、大城教授のリアルな日常を一部お届けします。
* * * * * * *
考古学を学ぶ最高のアルバイト
「エジプトの発掘調査にはどうすれば連れて行ってもらえるのか」
若い頃の自分もそのような質問を持って先生の研究室にやって来る学生と同類だった。完全に気持ち先行型の学生で漠然と海外で発掘調査することを夢見ていた。実際は何もできないのに……。
しかし何もできないし実力もないのに根拠もなく、いつかチャンスが目の前に来ると信じていた。古代ローマの喜劇作家ティトゥス・マッキウス・プラウトゥスが言うように「大事なこととは、そのチャンスが来たときに眼を開けていること」だと信じて疑わなかったのだ。
だからチャンスが来たそのときには必ずこの手で確実につかみ取るために目を光らせていた。おそらくそれは同じ大学の先輩たちがペルーのクントゥル・ワシ遺跡やエジプトのアコリス遺跡で発掘調査に参加していることを私が知っていたからだ。たとえ低くとも可能性があることはわかっていたのだ。
幸運なことに私は自分の実力のなさ、勉強不足を自覚していた。ゆえに何が足りないのかを理解していたのである。何よりも大事なのは己を知るということだ。たとえ痛いほど力不足を自覚させられたとしてもである。
発掘調査のアルバイトを探す
そこでまずやったのが、所属大学のある市町村で発掘調査のアルバイトがないかを探すことであった。
現在のようにインターネットで検索することもできなければ、アルバイト情報誌に掲載される求人にも偏りがあり、発掘バイトなどいくら探してもどこにも見当たらない時代だった(そう言えば私が大学生であった頃は、大学の掲示板にアルバイト募集の紙が貼られており、毎日そこで情報を集め、よいものがあれば自分でアルバイト先に電話したものだ)。

『考古学者だけど、発掘が出来ません。 多忙すぎる日常』(著:青山和夫、大城道則、角道亮介/ポプラ社)
そこで思案した私は思い切って市役所の文化財保護課に直接出向いて発掘のアルバイトを募集していないかを尋ねた。そして幸運にもタイミングよく目的のものを手に入れたのだ。まだ一般向けに募集をかける前であったのであろう。振り返るとよくそんな行動力が当時の自分にあったものだと思う。
かくして偶然か必然かはわからないが、私は望んでいた発掘アルバイトの仕事を得ることができた。その足で当時お世話になっていたアルバイト先の心斎橋の釣具店を退職してきたのだ。店長、あのときはごめんなさい。
何より幸運だったこと
私が新しいアルバイト先としたのは、文化財保護課がある大阪府の吹田市立博物館であった。そこから市内の遺跡に派遣された。大学から歩いて発掘現場に行けるような近場や電車で5分も行けば最寄りの駅に到着するような場所で足掛け10年近くお世話になった。
大学院生になってからは、お願いして午前中だけ働かせてもらい、午後から大学の研究室に行った。お金がなかったので、お昼過ぎに大学に着くと食堂などには行けず、研究棟備え付けのコンロで買い置きしておいた蕎麦の乾麺を茹でて食べた。
お金に余裕があるときは、近くのスーパーで200円ほどの安い天ぷら盛り合わせを買って天ぷら蕎麦にした。お金がないときは、マルちゃんの「黒い豚カレーうどん」を食べた。
毎日終電の時間まで研究し、電車賃を浮かすために最寄りの駅から阪急電車には乗らず、丘の上にあった校舎から坂道を20分走り、自宅の最寄り駅まで直通であったことから、阪急電鉄よりも少し運賃の安いJRの駅から乗車し自宅に帰った(もちろん学割の利く定期券で)。それが私の大学院生時代のルーティーンだった。
午前中だけ働かせてもらうなどわがままを聞いていただいたアルバイト先の博物館の皆さんと調査員の皆さんには今でも大変感謝している。
そして何より幸運だったことは、考古学素人であった私のような学生に一から手取り足取り考古学の実践の基礎を教えてくれたことだ。それは本当に一からだった(0からのスタートであったとも言える)。後から知ったことだが、単なるアルバイトにそのような丁寧な指導をしてくれるところはほとんどないそうだ。
平板の立て方もトータルステーションの設定の仕方も三脚の立て方も図面の描き方もすべて教わった。土器の注記の仕方も遺構の白線の引き方もだ。こちらが勉強させてもらっているのに一円の月謝も払うことなく、逆にお給料がいただけたのだ。考古学を学ぶ学徒としては最高の待遇であった。
アルバイト先で先輩や後輩ができた。皆でよく飲んで食べた。今でも交流のある人たちもいる。そのうちの幾人かは、プロの考古学者になって今も日本各地の埋蔵文化財センターや教育委員会で活躍している。私のように大学の教員になった者もいれば、博物館の学芸員になった人もいる。
今から考えると人を育ててくれるスタッフに恵まれていた場であったのだと思う。
日本で発掘の実践を積む
このような経験をしてきたこともあり、件の「エジプトの発掘調査にはどうすれば連れて行ってもらえるのか」という質問に対して、最近「日本の発掘現場でアルバイトして、経験を積んでおいて下さい」、あるいは「駒澤大学の考古学研究会に入って、考古学の基礎を学んでおいて下さい」と付け加えることも多い。
たとえ日本の現場でもそれは海外発掘の際に間違いなく役に立つことを私自身が身に染みて知っているからである。
もちろん、だからといって調査のためにエジプトに連れて行けるかどうかはわからない。協調性や忍耐力など個人の適性を見極めなければ後々大変であるからだ(保護者からの許可も重要だ)。
ただ日本であろうが、エジプトであろうが、シリアであろうが、イタリアであろうが、中国であろうが、韓国であろうが、考古学で使用する道具や機器には大差がないし、発掘調査の手順もそれほど変わりがないことも事実だ。
日本独自に発展し使用されている真弧(まこ)(土器の形状を実寸で写し取ることができる竹の実測道具)(写真)のような珍しい実測道具もあるが……。
ということで、やたらと忙しい最近は、YouTubeチャンネル(『おおしろ教授の古代エジプトマニア』)で質問を受け付け、そこでいろいろ回答するようにしている。皆さん、あまり難しくない質問をお待ちしております。可能な限り懇切丁寧にお答えいたします。お気に召したら駒澤大学を受験して下さいね!
※本稿は、『考古学者だけど、発掘が出来ません。 多忙すぎる日常』(ポプラ社)の一部を再編集したものです。
関連記事(外部サイト)
- 大学職員が「ラクな職業ランキング上位」なのは当然?転職してきたら労働時間半分で年収は200万円アップ?元職員の二人が語る「理想と現実」
- 大学職員は9時5時「ラクラク勤務」で年収1000万円?後輩のお世話をしたいのに幼稚園や病院へ配属されることも?元職員の二人が語る「理想と現実」
- 「大学職員はラクな仕事」との噂は本当か?労働基準法違反、ハラスメント、いじめ…。知られざる「人気職」の実態
- 「有力私大職員なら誰でも40代で年収1000万超え」の噂は事実か?すべてが嘘とは言えないが、達成には「アレ」が不可欠
- 年収1000万円以上で仕事もラクと言えば「大学職員」?定員割れ、経営難、改革…。18歳人口激減の中で知られざる「人気職」は今