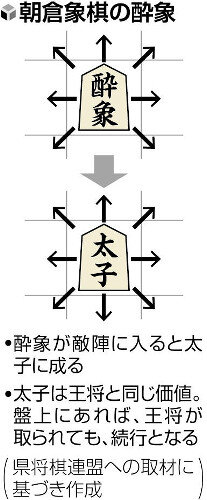戦国時代の「軍制」はどのように進化したのか?〈領主別編成〉から〈兵種別編成〉へ、その違いと過程
2025年4月29日(火)6時0分 JBpress
(歴史家:乃至政彦)
いつから〈兵種別編成〉があったのか?
今回のテーマは戦国時代の軍制である。これまで私も強調していた「戦国時代の軍隊は〈領主別編成〉から〈兵種別編成〉へ変化した」とする通説だが、ここに若干の修正をしておきたい。
〈領主別編成〉と〈兵種別編成〉の違い
まず一般的に知られる〈領主別編成〉について説明しよう。この用語は、戦国軍事史を考える上で欠かせない概念となっている。
簡単にいうと、武士の軍隊は、戦国時代のある時期まで、それぞれ自由に手下を連れて戦場に集まり、私兵と私兵が寄せ集まっただけの雑多な集団だった──とする解釈、これが〈領主別編成〉の特徴である。
「今回の戦に、ぜひとも参加させていただきたい」
中世にはこのように地元の武士が、大軍のもとに参陣することがよくあった。
しかし、彼らが総大将の望む武装と人数を揃えているわけではない。弓、槍、馬の数はおそらくバラバラだった。こんな状況で兵数が無計画に集まっても「弓隊」「鉄砲隊」「騎馬隊」という編成などできなかったのではないか。中世の武士は未熟な軍隊しか構成できなかったはずだ──。
こうしたイメージを広めたのは、戦国時代に純粋な「騎馬隊」はなかったとする新説を提唱した鈴木眞哉氏だろう。
特に騎馬隊懐疑説は非常に広く支持された。
そして「騎馬隊を編成できないなら、鉄砲隊だって編成できなかったはず。長柄を揃えた槍襖(やりぶすま)などなおさら難しいだろう」となり、中世の武士は〈領主別編成〉だったとする認識が定着した。
個人戦から集団戦へ
戦国大名のもとには、足軽や雑兵といった「武士」ではない歩兵が集まるようになり、集団戦向きの編成と運用が本格化していった。かつて個人戦でのみ使われていた鉄砲も大量に揃えられるようになってきた。すると、戦国大名は計画的な〈兵種別編成〉の軍隊を構成できるようになった(図1:〈領主別編成〉と〈兵種別編成〉のイメージ)。
私はこうした議論を受け入れて、拙著『戦国の陣形』に、旗隊、鉄砲隊、弓隊、長柄隊、騎馬隊という五つの兵種が創出される様子を描き出し、日本中に〈兵種別編成〉が定着したという解釈を披露した。
この説明は、いくらか普及したようで、歴史博物館で当たり前に取り入れられているのを見たこともある。
ただ、再検証をしているうちに、私の中で別の解釈が現れてきた。結論から先にいうと、基本的な解釈(兵種別の部隊の編成が本格化したという理解)は今も変わらないが、〈領主別編成〉は実際には存在しなかったのではないかという解釈である。
律令制の兵種別編成
時代をかなり遡らせることになるが、9世紀前半成立の『令義解』軍防令「軍団条」の一文をみてみよう。
凡軍団、毎一隊、定強壮者二人、分充弩手、均分入番
(【意訳】すべての軍団は、1つの隊に技術者を2人ずつ置き、弩の使い手を均等に編成して、番に入れておくこと)
弩の扱いに、2人の力ある兵士に技術者を添えて、複数名で使うよう定めたのである。連射を目的とした集団運用である。「鉄砲三段撃ち」のような扱いはこの時代からすでに常用されていた。
同じく『令義解』軍防令「陣列之法」には、次の一文がある。
陣列之法、一隊十楯。五楯列前、五楯列後。楯別配兵五人。即以前列廿五人為先鋒。後列廿五人為次鋒之類
(【意訳】陣列の法について。1隊につき楯を10配置する。楯5つは前列に、楯5つは後列に置き、楯の後ろに兵を5人ずつ配する。すなわち前列の25人は先鋒、後列の25人は次鋒とする編成にする)
古代史の専門家たちの研究をもとに図示化すると図2の形状になる(図2:「陣列之法」における「一隊」の基本隊形)。
これは〈兵種別編成〉である。同じ9世紀の史料『貞観儀式』(859〜877)に、当時の軍令が説明されている。時報・起床・着装(武装せよ)・集合(集まれ)・出陣・進撃・布陣(止まれ)・戦闘態勢・戦闘開始・戦闘停止・戦場退去・戦闘集結・帰陣・解軍、これらの号令が具体的に記されているのだ。
ここに古代の日本が、集団を集団として編成して運用する仕組みを本格的に作ろうとしていたことを確かめられる。〈兵種別編成〉は古代から採用されていた。
中世武士の起こり
ところが中世になると、武士が台頭してくる。
彼らは公的な兵ではなく、私兵である。地方ごとで寄り集まる「地元ファースト」の民間人で、いわば武装勢力である。
ここで雑多な〈領主別編成〉をイメージしてしまいそうになる。だが、よく考えなおしてみると、彼ら武士は、無数の個人戦だけで軍隊を構成するわけではない。
もちろん必要な時には雑多な構成になることもあった。だが、盾は盾だけで、弓も弓だけで集合する布陣が、10世紀の平将門時代ですでに常用されていた。
例えば『将門記』を見ると、将門と戦った平良兼が部隊のうち楯だけを「垣のように盾を並べた」布陣しており、将門はこれを騎兵で突破して、良兼隊を蹂躙している。同書では、騎兵と歩兵(ふひょう)がそれぞれ別個の集団を構築して戦う描写が繰り返されている。
どうやら9世紀の国軍と、10世紀の私軍は乖離しておらず、どちらも〈兵種別編成〉を常用していたようなのである。
その割合は不定としても、武士が戦争をする生き物であるならば、最小単位の〈領主別編成〉タイプの兵員たちも自分だけでミニマムな軍隊を構成するはずだ。
兵数がたった3人しかいなくても、盾を使う者が最低1人はいるに違いない。鎌倉時代ならば、騎兵が必ずいる。これを補佐する歩兵が欠かせない。定数ではないが、武士は常に〈兵種別編成〉を構成する。映像作品のスタッフもカメラマン、出演者、照明など、分業が当たり前なように、武士の軍隊もそれをやっていた。
そして大将の指揮下に入って集団化した時、大将が命令するなら、武士たちは即座に武器を持ち替えて、弓は弓、長刀は長刀、騎馬武者は騎馬武者で集まり直しただろう。
なぜなら、武士は万能の戦士である。弓、刀、馬の達人でなくてはならない。勝利するためならば、武器の持ち替えぐらい受け入れて当たり前だ。むしろ当たり前でなければ武士ではない。
南北朝時代の〈兵種別編成〉
これをよく示すのが、南北朝時代の合戦記録である。
元弘3年(1333年)閏2月11日、播磨国の赤松円心は敵軍と対峙したとき、野戦に備えて軍隊の編成を組み替えさせた(『太平記』)。
態敵を難所に帯き寄ん為に、足軽の射手一二百人を麓へ下して、遠矢少々射させて
(【意訳】山の上に陣取った赤松円心は、わざと敵を戦いにくいところへ誘導するため、足軽の弓兵1〜200人を山の麓へ降ろし、遠いところから矢を控えめに射かけさせ)
ここでは単に弓兵を臨時に編成しただけだが、軍隊の再編成はその場の考えで柔軟に変化できたのである。
幕府軍と楠木正成との合戦である正平(しょうへい)3年・貞和(じょうわ)4年(1348)1月4日の四條畷合戦では、佐々木道誉の部隊の運用が完全に〈兵種別編成〉となっている(『太平記』)。
佐々木佐渡判官入道は、二千余騎にて、伊駒の南の山に打上り、面に畳楯五百帳突並べ、足軽の射手八百人馬よりをろして、打て上る敵あらば、馬の太腹射させて猶予する処あらば、真倒に懸落さんと、後ろに馬勢控へたり
(【意訳】佐々木道誉は2000騎以上の侍たちと一緒に、生駒の南の山へと登り、前面に盾をびっしりと500個ならべ、足軽の弓兵800人を下馬させた。ここまで乗馬して登ろうとする敵がいたら馬の腹を射たせ、そこに隙があるなら蹴散らしてやろうと後ろに騎馬武者たちを控えさせた)
ここにあるように、山の上へと2000騎以上の侍を連れて布陣した佐々木道誉は、これを盾隊500人、弓隊800人、そして騎馬隊に再編させた。ほかにも下馬した歩兵はあっただろう。
その場での臨時編成が可能ということは、侍たちは日頃から柔軟に武装を使い分ける用意があったことになる。
ということは、〈兵種別編成〉というのも固定的ではなく、形を自由に変化させることができたのだ。
ここに、既存の〈領主別編成〉はいくらか修正が必要で、〈兵種別編成〉と単純に区別できないことが見えてきたと思う。
しかし、戦国時代に、こうした編成が臨機応変にではなく、完全分担化して定着することになる。戦争が非日常のものではなく、日常のものとなり、貴重な万能戦士たる武士たちが死んだあとと戦争が繰り返されるので、これを穴埋めするため、素性が不安定な兵員を補充する必要が生じたからである。
ここにいわゆる足軽・雑兵が普及することになった。彼らは、「武器を弓に持ち直せ」「みんな馬に乗れ」「100人で集まれ」と言われても、用意すらしていない者もいて、まごまごすることになるだろう。
加えて鉄砲の伝来もある。鉄砲は弓より使える武器として日本中に広まった。だが、こちらは足軽どころか武士ですら簡単に扱えず、手に取ったことのない者も少なくなかっただろう。「とりあえず鉄砲だけで50人ここに並べ」と言われてもすぐに対応できたとは思われない。
ここで軍事改革というほどのこともなく、分業化が進んでいく。大将が家臣たちに初めから「あなたの鉄砲は何人、騎馬は何人」と武装と定数を設定しておいて、その通りの構成をするように準備させるのだ。
こうやって戦国時代に、編成の思想が大きく変わっていく。こうした変化は、天才がいたとか合理的な編成を研究したとかではなく、自然な時代の流れへの対処として生じたのである。
とはいえ、戦国時代は英雄の時代である。上杉謙信と武田信玄が、さらなる変化を促進することになる。
【乃至政彦】ないしまさひこ。歴史家。1974年生まれ。高松市出身、相模原市在住。著書に『戦国大変 決断を迫られた武将たち』『謙信越山』(ともにJBpress)、『謙信×信長 手取川合戦の真実』(PHP新書)、『平将門と天慶の乱』『戦国の陣形』(講談社現代新書)、『天下分け目の関ヶ原の合戦はなかった』(河出書房新社)など。書籍監修や講演でも活動中。現在、戦国時代から世界史まで、著者独自の視点で歴史を読み解くコンテンツ企画『歴史ノ部屋』配信中。
筆者:乃至 政彦