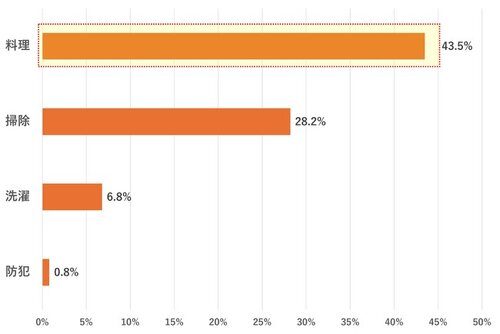自炊に<壁>ができた理由。「今の時代、料理という言葉に、確定申告ぐらい重たい響きがあるかもしれません」
2025年5月2日(金)12時30分 婦人公論.jp

(写真はイメージ。写真提供:Photo AC)
厚生労働省が発表した「令和元年 国民健康・栄養調査」によると、週1回以上外食を利用する人の割合は20代が最も高かったそう。若い世代を中心に自炊をしない人が増えているなか、今回は、ミニマリスト・佐々木典士さんと自炊料理家・山口祐加さんが、「自炊の壁」ひとつひとつを言語化し、その解決策を練った共著『自炊の壁 料理の「めんどい」を乗り越える100の方法』から一部を抜粋し、<自炊を楽しく続けるコツ>をお届けします。
* * * * * * *
料理はプロセスが多すぎる?
佐々木 今まで生きてきて、料理に向き合うのを後回しにしてきてしまいました。ぼくの部屋はものが少ないので、掃除機をかけるのも一瞬で終わるし、洗濯も乾燥までかけたら畳むのも数分で終わります。でも料理は調理だけではなく、買い物、下ごしらえ、皿洗いに至るまで本当にたくさんのプロセスがあります。だからどうしても難しく、複雑なものに見えてしまっていたんですよね。
山口 昔は、食材の種類も今ほど多くなかったし、洗い物だって、お茶碗にお湯を入れて拭うぐらいで、少なかったと思うんですよ。料理にまつわるプロセスが今ほど複雑ではなかったんだと思います。
佐々木 他の家事と比べると覚えることも多くて、最も複雑な家事であるのは間違いない。忙しければ、今までできなかったとしても仕方がない家事だという認識は、まずあってもいいのかもしれません。
山口 今は自炊をする理由が、歴史上でも最も弱い時代だとも思うんです。日本では外食が安いし、コンビニで買えるお惣菜もどんどん美味しくなっています。
佐々木 もはや「料理」という言葉に、確定申告ぐらい重たい響きがあるかもしれません。「料理とか……します?」と恐る恐る聞いたり。
「料理がめんどい」人たち
山口 日本は現在、ひとり暮らしが世帯全体の約4割を占めているんですよね(令和2年国勢調査・世帯の状況/総務省統計局)。私だって自分ひとりのためには、手間がかかるオムライスは作りません。自分ひとりのためにオムライスを作れるのは、オムライスが本当に大好きな人ですよ。
佐々木 単身世帯も増えたし、家族を持ったとしても共働きの人が増えましたよね。

『自炊の壁 料理の「めんどい」を乗り越える100の方法』(著:佐々木典士、山口祐加/ダイヤモンド社)
山口 私の料理教室の対象者は「料理が苦手な方、初心者」限定なのですが、参加者が料理が苦手だと感じたり、料理が嫌いになってしまった理由は本当にさまざまです。自分ひとりのためだけに料理を作るのが時間の無駄に感じる、食材が余って使い切れない、献立を考えるのが大変、切るのが遅くて嫌になるなど理由を挙げればキリがありません。でも総じていえば「料理がめんどい」のだと思います。
佐々木 何もわからない最初の状態は、本当に苦しいんですよね。ぼくだって、ついこの間まで、鶏のむね肉ともも肉がどう違うのかもよくわかってなかったし。スーパーへ行っても、必要な分量すらわからなかった。でも1か月、2か月と続けているとだんだんコツをつかんできて、自分が初心者を脱していると思えるようになりました。いざ入門すると、これは一生物の趣味を得たなと思うこともあります。外食しても、それがどんな風に味付けされているのか考えたり、料理をする人との話題も増えました。プロセスが多いからこそ、語ることも尽きない。
山口 人生楽しいですよね、料理ができると。食べることは毎日誰でもやっているわけだから、日々の営みが全部インプットになる。海外に行っても、市場を見たり、その国の基本調味料がなんだろうかとか考えたりして、楽しみが増えます。
佐々木 そう考えると、人生の一時期でも料理をやってみることは恩恵が大きくて、とても価値あることだと思います。対話を通じて、複雑で難しくなりすぎた料理から、シンプルさや親しみやすさを取り戻すことができればと思います。
資本主義に抗う自炊?
佐々木 なぜ料理が、こんなに敬遠されるようになったんでしょうね?
山口 大げさに言えば、自炊することは、資本主義の仕組みと戦っているようなところもあります。今は一分一秒でも時間が生まれたら、ついスマホを見たくなって、コンテンツ産業に時間を奪われてしまう。料理はそこから少し距離を置いて、自分に食べさせていく、自分の命を生かしていく行為ですね。
佐々木 資本主義の枠組みでは、すべての作業を分業したほうが効率的ですよね。岡本太郎は、絵画だけではなくて彫刻や建築や民族学など、なんでもやった人ですけど、その理由を「人間の職業分化に反対だからだ」って言ってたんですよ。
山口 「本職? 人間だ」ってやつですね。
佐々木 何かの仕事をするときに、作業が単調であるほど覚えやすく、誰でもできる。だからできるだけ作業を小さい単位に分けて、担当する仕事だけに集中したほうが、効率は高まるのかもしれない。高度成長期に、女性が家事を一手に担っていたときもそうだと思うんです。そのほうが料理の質も高まりやすかったはず。
でも今は、単身世帯が増えて、共働きも多くなって料理を一手に担える人が少なくなってきた。だから、料理というものが家庭を超えて、さらに外部の専門的な人に集中的に任され始めている、ということかもしれません。効率だけ考えたら、野菜を育てる人、それを切る人、調理する人、食べる人の役割は、きっちり分かれていたほうがいいでしょうからね。
山口 人より機械が切ったほうが速いですからね。
佐々木 家庭の小さい鍋で作るよりも、給食センターがデカい鍋で作るほうが効率的だし、もっと大きな企業が工場でまとめて作ったほうがさらに効率的。でもそれは経済の論理で、人間が本来どうありたいかとはまったく別の問題ですね。自炊をするために必要なのは、岡本太郎のような考え方かもしれません。
食べ物を残すことへの罪悪感
山口 食材を無駄にしてしまうという罪悪感も、自炊を避ける理由として大きいですね。ひとり暮らしだと、どうしても大根とかキャベツとか、1回では使い切れなくて余っていく。でも毎日自炊できるわけじゃないから、ダメにしてしまったりする。学校給食でもそうですが、日本人は、食べ物を残しちゃいけない、無駄にしちゃいけないという意識をすごく強く持っていると思うんです。でもその罪悪感があると、なおさら自炊から離れてしまうかもしれないですね。
佐々木 確かに「自分はすぐに植物を枯らしてしまう」と思っていたら、新たな植物は買いづらい。でも無駄が出ないことだけを目的にすると、誰かに工場でまとめて管理してもらったほうがいい、ということになってしまうかもしれません。
山口 手間のかかるコロッケを1個だけ食べるために、じゃがいもや玉ねぎ、ひき肉、卵、パン粉を買って作るのは本当に労力に見合ってないと、私も思います。私は家に人が来ても、コロッケは面倒だから作りません。ハンバーグが限界(笑)。
佐々木 おでんの卵1個だけを作るんだったら、コンビニで買ったほうが確かにいいかもしれない(笑)。それでも手間や面倒、コスパやタイパを超えるものが、自炊にはあるのではないか? ということを考えていければと思います。
※本稿は、『自炊の壁 料理の「めんどい」を乗り越える100の方法』(ダイヤモンド社)の一部を再編集したものです。
関連記事(外部サイト)
- 鍋1つに切って煮るだけ。シニアの《隠れ栄養失調》予防にも。不足しがちな栄養素を詰め込んだ、柔らかく飲み込みやすい〈からだが整うスープ〉のススメ
- 品数多くても栄養不足に?管理栄養士が教える、健康長寿のための食事とは。砂糖は白より黒、みそは長期熟成タイプを【2024年下半期ベスト】
- 和田秀樹が「高齢者こそ肉を食べて!」と主張してきたワケ。長年目の敵にされた<コレステロール>だが、むしろ高齢になると…【2024年下半期ベスト】
- 糖尿病の名医が実践する生活習慣「若いときは、絵に描いたような糖尿病予備軍でした。食事は野菜サラダをプラス、20分の通勤は早歩きで」
- もうすぐ105歳。20年前に夫を亡くしひとり暮らしの日々が映画になった石井哲代さん。「なぜ家から畑に続く坂道を毎日草むしりするの?」と訊ねたら…