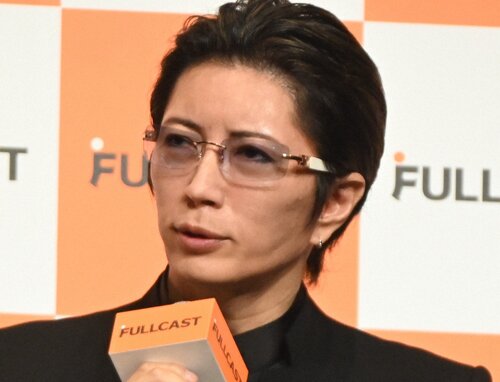107人死亡の“凄惨な電車事故”を起こしたJR西日本は「人が死んでるのに、問題をなかったことにしようと…」遺族が対応に“不満”を覚えたワケ
2025年5月28日(水)7時20分 文春オンライン
〈 電車が時速120kmの猛スピードで“暴走”→脱線→マンションに激突して107人死亡…「凄惨な電車事故」で息子を亡くした父親が、JR西日本に抱いた“怒り” 〉から続く
乗員乗客107人の死者を出した、JR史上最悪の惨事・福知山線脱線事故から20年。脱線・転覆の10秒間に、いったい何が起きていたのか。生死を分けたものは何だったのか。重傷を負った生存者にふりかかった様々な苦悩と、再生への歩みとは——。
ここでは、遺族、重傷を負った被害者たち、医療従事者、企業の対応など、多角的な取材を重ねてきたノンフィクション作家・柳田邦男氏の著書 『それでも人生にYesと言うために JR福知山線事故の真因と被害者の20年』 (文藝春秋)より一部を抜粋。JR西日本と遺族が行った「福知山線列車脱線事故の課題検討会」の内容を紹介する。(全3回の3回目/ 1回目から読む )

◆◆◆
「開通時分」「停車時分」についての課題
課題検討会でダイヤ担当課長による説明が一通り済むと、淺野が質問した。
「事故を起こした電車の運行状況に関することだが、配布資料によると、始発の宝塚駅における発車までの停車時分、いわゆる『開通時分』ですね、それと他の駅での『停車時分』について、『課題があるものでした』と書かれているけれど、これは具体的にどういうことなのか」
課長「1つには、宝塚駅での発車までの停車時分を1分30秒としていたのですが、先に発車する福知山方面から来る急行列車が遅れがちなので、快速はどうしても1分30秒では発車できないことが多かった。そこで1分35秒なり1分40秒なり、停車時分をもう少し長くしたダイヤにすべきではないかということ。
もう1つは、途中の停車駅の『停車時分』についてですが、中山寺駅での15秒、川西池田駅での20秒、伊丹駅での15秒という設定になっていましたが、いずれの駅でも、乗車しようとする客の多さや駆け込み乗車などでダイヤ通りの『停車時分』では足りないことが多かったということです」
淺野「なぜ『停車時分』を変えなかったのか」
課長「例えば伊丹駅については、事故の2年前の暮れのダイヤ改正に当たって、現地調査をしたところ、『停車時分』は設定の15秒より長くかかり、平均で17秒から18秒かかっていることがわかったのですが、その程度なら駅員が整列乗車をさせたり『基準運転時分』に含まれる『ゆとり』の時分で補ったりすれば、ダイヤの遅れを生じさせないで済むと判断して、15秒の設定のままにしました」
宝塚駅〜尼崎駅間で「余裕時分」が設定されていなかった
こうした説明は、木下には辻褄を合わせているに過ぎないとしか思えなかったので、発言の口調は厳しくなった。
「『停車時分』が実際には17秒から18秒かかっているのに、ダイヤに設定されている15秒という短い秒数を変えようとしないで、整列乗車や『ゆとり』の時分でやりくりしようというのは、いかにも姑息なやり方じゃないですか。
事故を起こした電車が宝塚駅から伊丹駅に向かってどう走っていたかについては、説明でわかった。しかし、わからないことがある。
ダイヤを作るに当たっては、無理なものにならないように、『基準運転時分』の中に『ゆとり』の時分を何秒か含ませるだけでなく、停車駅での乗客の乗り降りに予想以上の時間がかかるとか、線路工事などの影響で徐行を余儀なくされるといった場合に備えて、別枠で『余裕時分』というものを設定することになっていると、はじめに説明しましたよね。
だけど、宝塚駅〜尼崎駅間の快速電車のダイヤについて、配布された資料を見ると、その区間には、『余裕時分』が設定されてないじゃないですか。一体、『余裕時分』を設定してある区間とない区間とは、どういう理由で分けてるんですか」
課長「『余裕時分』というのは、一定の区間で遅れが生じた場合でも、終着駅にはダイヤの時刻通りに着くようにするために、終着駅の1つ手前の停車駅の発車時刻やその後の走行時分の中に含ませる形で設定するようにしているのですが、宝塚駅〜尼崎駅間の上り快速電車については、尼崎駅の手前の駅からの『余裕時分』を設けていませんでした」
JRの説明資料と事故調の「報告書」の違い
木下「その理由を知りたいんです」
課長「私共も今回調べてみたらなかったということを知ったのでして、なぜないのかまではまだ明らかにすることができていないのです。ともあれこの区間を特別扱いしていたわけではないと思います」
木下は、怒りが込み上げてくるのを懸命に抑えながら、質問を続けた。
「説明資料によると、宝塚駅発の上り快速電車は、尼崎駅到着が定常的に分単位で遅れるという状態にはなっていなかったと記されている。しかし、事故調の『報告書』には、『事故前65日間の半数以上の日に1分以上遅延して尼崎駅に到着するという、定刻どおり運転されることが少ないものであったと考えられる』と書かれている。
JRが説明資料に記している快速電車の運転時分の数字と事故調が『報告書』に記している運転時分には違いがある。おかしいじゃないですか。この違いは、どういうことなのか」
課長「事故調がどういうデータを根拠にしているのかはわかりません。独自の方法で計算したのだと思われます。私共は私共なりに分析したものを示しました」
木下「宝塚駅〜尼崎駅間のダイヤには無理はなかった。運転士がストレスを感じるほどのものではなかったというために、都合よく計算してるのではないかと思えてならない」
課長「そんなことはないです。事故調がどういうデータで計算しているのかは、私共にはわかりませんので、事故調の指摘について評価することはできません」
JR側は理論と机上の計算で数字をはじき出すばかり
木下は、自分の感情の防波堤が決壊寸前になっているのを感じた。自分は息子のいのちを奪ったものは何か、その真相を何としても捉えたくて、自分のいのちを賭けるほどの思いで、ダイヤの実態を明らかにしようとしているのに、JR側は理論と机上の計算で数字をはじき出し、問題はなかったとしようとしている。
机上の計算結果がどんなものであろうと、自分が毎朝快速電車に乗って、走行と停車の時分を計測し記録してきた現実は、きれいごとで済ませることなどできないものだった。途中の停車駅での停車時分が10秒や20秒では、足りない状況だということは、議論の余地のないものだった。
利用者の利便は、乗客のいのちを賭けて成り立っていた
当然、発車が遅れ、電車の遅延は恒常的になってくる。整列乗車の呼びかけや「ゆとり」の時分でやりくりできる問題ではない。それでもなお、尼崎駅にダイヤ通りに着いていると言うなら、途中の「回復運転」のために、運転士が相当に電車のスピードを上げているはずだ。ダイヤの速達化と本数増加で利用者の利便をはかるという営業施策は、乗客のいのちを賭けて成り立っていたに過ぎない。
事故調の『報告書』は、福知山線の直線区間やカーブ区間における電車の暴走を防ぐATS‐Pの設置遅れという状態の中でのダイヤの問題点を、次のように厳しく論じているのを、木下はいつも頭に浮かべていた。
〈定刻どおりに運転されることが少ない列車運行計画とするべきでないことは言うまでもないことであるが、曲線速照機能(筆者注・ATS−P車上装置のこと)等の運転操作の誤りによる事故を防止する機能がない列車を時速120キロという速度で運転させるのであれば、その運行計画は相応の時間的余裕を含んだものとすべきである。〉
「逃げ口上ばかり並べる説明なんか聞いていられない」
木下は、このまま議論を続けると、自分が怒鳴り声を上げるだろうと直感した。だが、わずかながら残っていた冷静さが、その感情を抑えた。
《ここで自分が爆発して、会議の進行を行き詰まらせたら、せっかく淺野さんが我慢に我慢を重ねて、責任追及を棚上げしてでも、事故の真相を解明し、JR西日本を安全性の高い鉄道事業者にしようとして対話の場である検証会議を発足させたのに、その対話の場を決裂させ破壊させかねない。だが、自分はこの席に座っていたら、感情を抑え切れないだろう。》
そんな思いが頭の中で渦巻くのを自覚した木下は、
「人が死んでいるのに、そんな逃げ口上ばかり並べる説明なんか聞いていられない」
と投げ棄てるように言うと、机の上の資料をまとめて鞄に入れるや、席を立って会議室から出て行った。一瞬、沈黙が支配し、会議のテーブルが凍りついた。
(柳田 邦男/ノンフィクション出版)
関連記事(外部サイト)
- 【つづきを読む】「電車のスピードが速い」「立っていられない」107人死亡の“凄惨な電車事故”はなぜ起きたのか? 息子を亡くした父親が指摘した、“過密ダイヤ”の実態
- 【あわせて読む】電車が時速120kmの猛スピードで“暴走”→脱線→マンションに激突して107人死亡…「凄惨な電車事故」で息子を亡くした父親が、JR西日本に抱いた“怒り”
- 【衝撃写真】ブルーシートには血まみれの人たちが…107人が死亡した“凄惨な電車事故”の事故現場を見る
- 【画像】グチャグチャになった車両から救出される乗客
- 「白いスカートが血で赤く染まり、呼吸困難に陥りそうに…」107人が死亡した“凄惨な電車事故”19歳女子大生が語った、事故直後の壮絶な状況