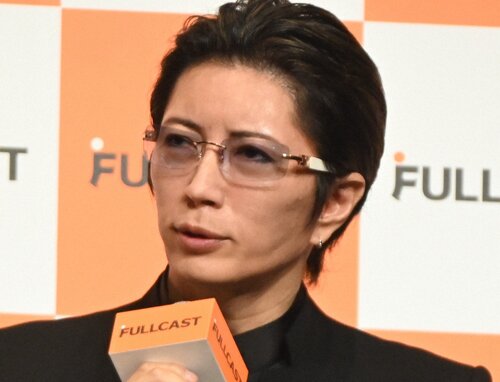「電車のスピードが速い」「立っていられない」107人死亡の“凄惨な電車事故”はなぜ起きたのか? 息子を亡くした父親が指摘した、“過密ダイヤ”の実態
2025年5月28日(水)7時20分 文春オンライン
乗員乗客107人の死者を出した、JR史上最悪の惨事・福知山線脱線事故から20年。脱線・転覆の10秒間に、いったい何が起きていたのか。生死を分けたものは何だったのか。重傷を負った生存者にふりかかった様々な苦悩と、再生への歩みとは——。
ここでは、遺族、重傷を負った被害者たち、医療従事者、企業の対応など、多角的な取材を重ねてきたノンフィクション作家・柳田邦男氏の著書 『それでも人生にYesと言うために JR福知山線事故の真因と被害者の20年』 (文藝春秋)より一部を抜粋。JR西日本と遺族が行った「福知山線列車脱線事故の課題検討会」の内容を紹介する。(全3回の1回目/ 2回目に続く )

◆◆◆
西川副社長からついこぼれた言葉「疲れますなぁ」
第6回の課題検討会は、5月24日にいつも通り弥生会館で開かれた。
長いテーブルをはさんで、会社側と4・25ネットワーク側が向き合って席に着くと、西川副社長が、正面の淺野の顔を見て、ぼそっと言った。
「疲れますなぁ」
確かに会社側の代表者ともなれば、遺族側からぎりぎりと錐を刺し込まれるように質問や疑念をあびせられ、それに対して精一杯の回答を示さなければならないのだから、精神的なストレスは決して小さくはない。
事故後の垣内社長の時代のように、組織防衛のために「説明拒否」の姿勢を貫くだけだったら、それはそれで職務に忠実なのだから、内面的に苦悩するまでもないと言えよう。
しかし、西川は、JR西日本を開かれた真っ当な会社にしなければならないという思いと、遺族に対して可能な限り誠実に説明責任を果たそうとしつつも、論理的に正当と考えるところはきちんと筋を通さなければならないという経営幹部としての責任感とがからみ合う中で、毎月の課題検討会に臨んできたのだから、つい「疲れますなぁ」という言葉も出てきただろう。
事故直後であったなら、加害企業の幹部がそんな言葉を吐いたら、遺族たちは直ちに怒りをぶつけただろうが、課題検討会での率直な議論が6回目ともなると、互いに相手の人柄もわかってきたからか、淺野も木下も、西川がさらに、「疲れんためにも、急いでいきましょう」と言葉を継いでも、角を立てることなく「始めましょう」と答えた。
通いなれた通勤電車で抱いた違和感
この日から、議題は列車ダイヤの問題に移された。4・25の遺族側は、運転士を追い込んだ背景には、列車ダイヤの高速化、過密化の進行という問題があったとかねて指摘していた問題だ。この問題に特に強くこだわっていたのは、木下だった。
木下は、大阪に本社のある会社の中堅幹部になっていたが、事故の数年前に、東京支社勤務を命じられ、しばらく関西から離れていた。しかし、事故の前年2004年に再び本社に戻り、自宅のある市から福知山線で大阪に通っていた。
通いなれた通勤電車だったが、すぐに電車の様子に違和感を抱くようになった。物凄いと言いたくなるほど、電車のスピードが速くなっていたのだ。立っていると、吊り革かポールにつかまっていないと立っていられないほどの加速感と揺れがある。
そればかりか、停車駅での停車時間がやたらに短い。乗降客が多くない駅では、ドアが5秒程度で閉まってしまう。数年ぶりの福知山線だが、利用者がかなり多くなった印象があるのに、各駅とも停車時間が以前より短くなった感じがあり、いかにもあわただしい。乗客はドアがすぐに閉まってしまうのを知っていてか、なだれ込むように乗り込み、駆け込みで無理に乗ろうとする客も目立つ。
各電車の走り方を記録してみると…
《これはダイヤに無理があるのではないか》
そう感じた木下は、朝の出勤時に、乗車する新三田駅から上り快速電車の停車する宝塚、中山寺、川西池田、伊丹、そして尼崎までの各区間ごとの走行時間と、各駅での停車時間を記録してみた。特に駅での停車時間については、停車後のドアが開けられてから閉じられるまでの時間も記録した。
時刻の正確さを期すために、時間の計測は携帯電話の表示を利用した。勤め先が通信機器メーカーだったので、製品の品質のデータなど数値を正確に把握する習性が身についていた。
このような電車の走行時間と停車時間の実測値を記録してみると、各電車の走り方は、必ずしもダイヤ通りになっていない場合が極めて多いことや停車駅でドアの開いている時間が所定の停車時間より短いこと、ドアが閉まりかかっているのに駆け込む乗客が多く、ドアの閉め直しをするために停車時間が長くなり、ダイヤの遅れの原因になっていることなどがよくわかった。
快速電車のダイヤ通りではない走り方に疑問を抱きつつも、一乗客に過ぎない木下は、どうしたらよいか、すぐには思いつかないまま、毎朝福知山線での出勤を続けていた。そして、翌年2005年4月25日、大事故が発生し、学生だった長男・和哉のいのちが奪われた。
事故後、改めて快速電車がどのような走り方をしているかを測定
無理なダイヤについては、和哉の死と重なりあい、ますます問題視する意識が強くなった。
木下は、事故から2年後の2007年6月に、事故調が発表した事故調査報告書を読んだ時、やはりダイヤに無理があったことが詳細に分析されていると感じ、改めて毎朝自分の乗る快速電車がどのような走り方をしているかを測定してみようと、乗車する度に、最前部の車両の運転席のすぐ後ろに立って、事故前にやったのと同じように、停車駅区間ごとの走行時間、停車駅における停車時間、ドアの開閉に要する時間を差し引いた実際にドアの開いている時間の測定をして記録することを始めた。運転台にある速度計もウォッチした。
事故後は福知山線のダイヤの修正がなされ、途中停車駅の停車時間は、15秒だった駅もすべて20秒に変更されていたが、それでも20秒ではドアを閉められずに、5秒から10秒遅れることが少なくなかった。
新たに気づいたのは、ダイヤで計画された停車時分20秒の中には、停車してからドアが開き切るまでの時間とドアが閉じる時間が含まれていないということだった。開く時間と閉まる時間を足すと、1秒ないし1秒程度であっても、停車駅が3カ所になれば、合わせて5秒前後の時間になるのだ。
もう1つ重要な気づきは、ダイヤの遅れが生じると、次の停車駅までの区間で運転士が遅れを取り戻すために、速度を時速100キロから120キロの高速で走行させる傾向があることだった。
木下は、こうした電車の走行の実態を、2年間にわたって記録し続け、その結果を、一度JR西日本の社長宛に手紙に書いて提出し、安全性の危機感を訴えた。しかし、受け取った返事は、「列車ダイヤは安全性を十分に考慮して編成しています」という、一般的な説明をしてあるだけだった。
それでも木下は、無理なダイヤが運転士のヒューマンエラーの大きな要因になっていたはずだという思いを強く抱き続けた。そして、2009年の暮れ近くなって、4・25ネットワークの要請をJR西日本がようやく受け入れ、課題検討会が開かれることになった時、淺野に4・25の代表メンバーに入ってほしいと声をかけられると、2つ返事で承諾したのだった。
過密ダイヤの落とし穴
5月24日の第6回課題検討会は、まずダイヤ担当の課長が、配布した資料に沿って、ダイヤの作り方の概要を、「これは事故調に提出したものと同じ資料です」という枕言葉を付けて詳しく説明した。
ダイヤの編成作業は、旧国鉄時代から高度なプロの世界の仕事とされてきた。大都市圏では、通勤電車に特快、快速、各駅停車などの種類があって、各停の電車はしばしば途中駅で特快や快速に追い越されるのを待たなければならない。
長距離の特急や急行を走らせる時には、一般の電車をどこかの駅で待機させなければならない。線路が合流するところでは、電車の優先順を調整する必要がある。電車加速性能は、車種によって微妙に違うし、停車駅間の線路にカーブが多いか少ないかによって、区間走行時間に違いが生じる。
列車ダイヤは、こうした様々な条件をしっかりと考慮に入れて作成しなければならない。しかも、そこに経済性の要請という条件が加わる。乗客の多い通勤時間帯には、運航させる電車の間隔を可能な限り短くして、運転本数を増やすとともに、同一地域を走る私鉄との競争に勝つために、高速化(JR西日本は速達化と称した)を可能な限り追求したのだ。乗客を増やすことは、営業成績を大幅に向上させることになる。
達人たちが作るダイヤは、科学的に合理性があるとされた
これだけ多くの条件を満たす列車ダイヤの図表は、横軸に取った時間の経過に対し、縦軸に取った一列車ごとの速度の変化を示す(駅出発後の加速による上昇曲線、最高速度の若干デコボコのある水平線、減速による下降曲線、駅停車中の速度ゼロの経過)が、無数と言ってもよいほどに、ほとんど重なり合うほどの密度で描き込まれている。それは、まるで精魂込めて描かれた“芸術的作品”と言ってもよいような図になっている。
そのような列車ダイヤを作成する担当者は、プロ意識が強く、専門外の社員の目には、まるで別格の達人のように映るのだ。だから、そういう別格の達人たちが作るダイヤは、科学的に合理性があるとされ、言わばアンタッチャブルの世界になっていた。
その世界に、門外漢の木下が大胆にも切り込もうとしていたのだ。ただ、木下はランカーブの理論闘争ではなく、連日電車に乗って実測したダイヤの実態を“武器”にしての闘争だった。
ダイヤ編成課長による説明で、特に強調されたのは、列車の一区間を走るに当たって必要とされる時間の幅「所用時分」というものは、「基準運転時分」「余裕時分」「停車時分」によって構成されているという基本的な事柄だった。
「基準運転時分」とは、線路の曲線部や直線区間などによって決められている速度制限とか車両の性能によって作成された区間内の運転時分のこと。
単なる目一杯の計算値でなく、1〜2秒程度から時には10〜20秒もの「ゆとり」を加えて設定されるという。(「ゆとり」は、はっきりと秒数で明示されるものでなく、「基準運転時分」の中に含まれているという説明がなされているだけのものだ。)
「余裕時分」とは、駅での乗降客の混雑で停車時間が長引いたり、線路の工事で徐行を余儀なくされたりした場合に備えて、所定のダイヤの範囲内で運転できるようにするために、予め設定してある秒数のこと。運転士には明示されている。
「停車時分」とは、駅で停車している時分のこと。一般の人々が予想する時分よりはるかに短い秒数が設定されている。混雑する長いところで1分30秒、短いところでは15秒程度と、予想していた値より短時間の停車になっている。
会社側は、こうしたダイヤの作り方に従うなら、ダイヤはほとんど遅れることなく運航されると考えていて、それを「定時運転」と呼んでいるというのだ。
〈 電車が時速120kmの猛スピードで“暴走”→脱線→マンションに激突して107人死亡…「凄惨な電車事故」で息子を亡くした父親が、JR西日本に抱いた“怒り” 〉へ続く
(柳田 邦男/ノンフィクション出版)
関連記事(外部サイト)
- 【続きを読む】電車が時速120kmの猛スピードで“暴走”→脱線→マンションに激突して107人死亡…「凄惨な電車事故」で息子を亡くした父親が、JR西日本に抱いた“怒り”
- 【最後まで読む】107人死亡の“凄惨な電車事故”を起こしたJR西日本は「人が死んでるのに、問題をなかったことにしようと…」遺族が対応に“不満”を覚えたワケ
- 【衝撃写真】ブルーシートには血まみれの人たちが…107人が死亡した“凄惨な電車事故”の事故現場を見る
- 【画像】グチャグチャになった車両から救出される乗客
- 「白いスカートが血で赤く染まり、呼吸困難に陥りそうに…」107人が死亡した“凄惨な電車事故”19歳女子大生が語った、事故直後の壮絶な状況