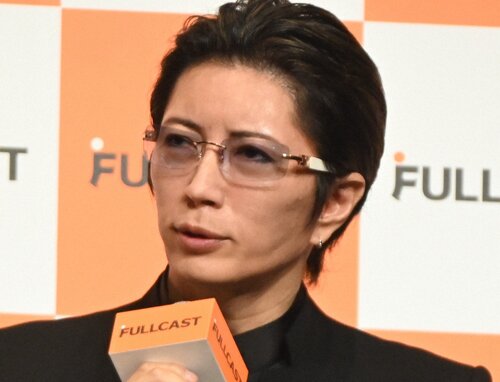電車が時速120kmの猛スピードで“暴走”→脱線→マンションに激突して107人死亡…「凄惨な電車事故」で息子を亡くした父親が、JR西日本に抱いた“怒り”
2025年5月28日(水)7時20分 文春オンライン
〈 「電車のスピードが速い」「立っていられない」107人死亡の“凄惨な電車事故”はなぜ起きたのか? 息子を亡くした父親が指摘した、“過密ダイヤ”の実態 〉から続く
乗員乗客107人の死者を出した、JR史上最悪の惨事・福知山線脱線事故から20年。脱線・転覆の10秒間に、いったい何が起きていたのか。生死を分けたものは何だったのか。重傷を負った生存者にふりかかった様々な苦悩と、再生への歩みとは——。
ここでは、遺族、重傷を負った被害者たち、医療従事者、企業の対応など、多角的な取材を重ねてきたノンフィクション作家・柳田邦男氏の著書 『それでも人生にYesと言うために JR福知山線事故の真因と被害者の20年』 (文藝春秋)より一部を抜粋。JR西日本と遺族が行った「福知山線列車脱線事故の課題検討会」の内容を紹介する。(全3回の2回目/ 3回目に続く )

◆◆◆
事故電車の走行記録の主なポイント
ダイヤ担当の課長が、ダイヤの編成の基本的な考え方についての説明を終えると、すぐに淺野が質した。
「ダイヤの作り方はわかった。ただ、私たちが知りたいのは、当日の運転状況はどうだったかということ。事故を起こした電車の実際の運転経過ですよ。
事故を起こした現場に差しかかった時の速度は、時速116キロとされているけれど、事故調の調査では、速度計に異常があって、運転台の速度計の表示は実際の速度より数キロくらい低く出ていたという。となると、時速122キロから124キロくらい出ていたのではないか。
そうなると、運転士はどんな運転をしていたのか。そこをしっかりと説明してほしい」
ダイヤ担当の課長が、事故を起こした電車から回収した速度記録計などのデータを基に分析した「当日の当該列車の運行状況について」と題する事故電車の走行経過表を使って説明した。それによると、事故電車の走行記録の主なポイントは、次のようになっていた。
・始発駅の宝塚駅では、ホームに入る前に、信号無視によるATS作動で非常ブレーキが発動するトラブルがあって、出発が定刻より15秒遅れた。
・最初の停車駅の中山寺駅では、ダイヤ通りなら15秒で発車すべきところを、駆け込み乗車があったことなどから発車までに10秒多い25秒かかり、累積で15秒+10秒=25秒の発車遅れとなった。
・次の停車駅の川西池田駅までの区間で、運転士の判断で計画より速度を上げ(制限速度の範囲内)、25秒の遅れのうちの6秒を取り戻した。
・川西池田駅では、停車時間計画の20秒に対し、駆け込み乗客などの影響で発車までに16秒多い36秒かかり、累積で25秒-6秒+16秒=35秒の遅延となった。
・発車後、速度を上げ、停車しない北伊丹駅通過時迄にわずかに1秒を取り戻したが、伊丹駅ではオーバーランの修正のために34秒を費やしたため、ホームの規定位置に停車したのが定刻より1分08秒遅れとなった。
・伊丹駅での停車時間計画は15秒と設定されていたが、実際には客の乗降に計画より12秒余計にかかり、停車時間が27秒になった。結局、遅延は累計で1分08秒+12秒=1分20秒となった。
・伊丹駅発車後、運転士はぐんぐん速度を上げ、通過駅の塚口駅を過ぎる頃には、時速が120キロの制限速度を超えていた。それほど速度を上げたことによって、遅延時間を8秒だけ短縮させていた。
・その後、やや減速させたものの、速度70キロ以下にすべき急カーブに、時速116キロ(実際には120キロ以上か)の高速で突っ込んでしまったのだ。
「ゆとり」や「余裕時分」と言われるものの実態の危うさ
事故電車の宝塚駅から事故現場に至るまでの以上のような秒刻みの詳しい経過を見ると、運転士がダイヤの遅れを1秒でも取り戻そうと必死になっている状況がひしひしと伝わってくる。
会社側によるこのような実際の走行経過の微細な説明を受けることによって、はっきりと見えてきたのは、運転時分における「ゆとり」や「余裕時分」と言われるものの実態の危うさだった。
既述の「ゆとり」と「余裕時分」の定義を読んだだけでは、かなり大まかに運転の所要時間が決められているように見えるが、実際はそうではないのだ。
福知山線の宝塚駅〜尼崎駅間の上り快速電車の場合、まず電車の性能や線路の直線か曲線かによる制限速度などの条件を揃えてコンピュータで区間全体の所要時間を計算すると、15分07秒という値が出る(停車駅における停車時分を含む)。これは運転士の技量や判断の個人差などは、考慮されていない数字で、「計算時分」と言う。
これに対し、平均的な技量の運転士による実際の運転操作で走った場合の所要時間を計測すると、15分35秒(平均値)という時間になる。これが、「基準運転時分」と呼ばれるものだ。
「基準運転時分」は、コンピュータ並みの技術で運転した場合の「計算時分」より、かなり所要時間が長くなる。その差は、
(基準運転時分)(計算時分)
15分35秒- 15分07秒=28秒
となる。この28秒が宝塚駅から尼崎駅までの「基準運転時分」に含まれる「ゆとり」と言われるものなのだ。
28秒という数字だけをみると、まあまあ「ゆとり」のあるダイヤのように見える。しかし、実際の状況を見ると、そう甘くはなかった。木下が毎朝、出勤時に記録していた電車のダイヤの乱れが、現実には運転に「ゆとり」がないことを示していた。なぜ「ゆとり」がない運転になるのか。
「報告書」では宝塚駅〜尼崎駅間のダイヤ設定に対して厳しく批判
宝塚駅から尼崎駅までにかかる「所要時分」は、「基準運転時分」だけでなく、途中の停車駅での「停車時分」を加えなければならない。ダイヤに設定された「停車時分」は、既述のように、
・中山寺駅 15秒
・川西池田駅 20秒
・伊丹駅 15秒
合計 50秒
となっていた。
現実の停車時間がこのように短い秒数では対処し切れないことを、木下は実測してわかっていたから、課題検討会で取り上げることになっていたダイヤ問題については、特別にこだわりをもって臨んでいた。漠然とした議論でなく、論理的にしっかりと問題点を明らかにしようと、既に公表されていた航空・鉄道事故調査委員会の「事故調査報告書」のダイヤに関する分析の項を精読していた。
事故調の「報告書」は、宝塚駅〜尼崎駅間のダイヤの設定内容について、詳しく調査・分析した結果に基づいて、次のように厳しく論じていた。
・事故以前において、宝塚駅〜尼崎駅間の「基準運転時間」を3回にわたって合わせて50秒短縮しているが、これはダイヤ担当者が会社の営業施策を実現させるためであった。(筆者注・会社の営業施策とは、私鉄各社との競争に勝つためのダイヤの高速化・列車本数増のこと。)
・始発の宝塚駅では、快速電車をホームに停車させてから発車までの時間を1分30秒と設定してあったが、別のホームから先に出る上り急行列車の発車が遅れることが多く、その影響を受けて、上り快速電車は出発時からダイヤより遅れることが多かった。
・「停車時分」については、川西池田駅での計画の20秒では、事故以前の実態調査から発車が遅れることが多く、5秒ほど不足していた。
・また、中山寺駅と伊丹駅での「停車時分」15秒についても余裕があったとは考えられない。
・事故以前における事故電車と同じ時刻の上り快速電車の運転時分を調査したところ(65日分)、半数以上が尼崎駅に1分以上遅れて到着していた。(筆者注・1分以上の遅延の常態化は、ダイヤに無理があることを示していると言わざるを得ないだろう。)
これらの事実から、「報告書」は、「宝塚駅〜尼崎駅間の基準運転時分と停車時分の合計は、余裕のないものであった」と厳しく批判していた。
さらに、停車駅の記録された着発時刻がかなり不正確であることや通過駅の通過時刻を確認する場所が日によって違うことなどから、「ダイヤの管理が適切に行われていなかった」とまで論じていた。
ダイヤの遅れを取り戻す「回復運転」のリスク
にもかかわらず、事故前のJR西日本は会社の方針として、列車が30秒以上遅延すると、運転士に「列車遅延時刻の報告」を求め、運転士などの不手際によって1分以上の遅延が生じると、関係した者を日勤教育と懲戒処分の対象にしていた。
JR西日本のベテランの運転士や技術畑の幹部の中には、ダイヤの遅れが生じた時、区間の最終駅到着の遅延を可能な限り短縮する「回復運転」をいかにうまくこなすか、その腕の見せどころを「男のロマン」と称する気風があった。
列車の制限速度(最高速度)は、直線区間の距離やカーブの曲率などによって決められているが、ダイヤは列車を制限速度よりやや遅い速度で走行させることを前提にして設定される。そこでダイヤの遅れが生じると、運転士は自分の判断で、制限速度を超えない範囲で速度を上げて、「運転時分」を短縮するように努める。
これが「回復運転」と言われるものだ。
実際には「回復運転」に入ると、制限速度を上回る速度を出すこともあったと言われていた。
ともあれこのように各区間で制限速度まで目いっぱいに速度を上げて走行する運転は、直線区間で120キロを超えるリスク、そしてカーブに入る時には、加速のし過ぎによる制限速度オーバーとかブレーキ操作の遅れといったヒューマンエラーによって、脱線するリスクが高くなる。
つまり、「回復運転」は、ベテラン運転士の「男のロマン」を満足させるものであっても、同時に事故のリスクを高めるという矛盾を孕んたものであった。
《「男のロマン」とは、とんでもない》
木下は、このような「回復運転」に内在する危険な問題について、JR西日本の技術畑の幹部との個人的な会話の中で知った時、強い怒りの感情が頭の中に込み上げてきた。
《「男のロマン」とは、とんでもない。乗客の命にかかわることなのに。実際、私の息子はいのちを奪われたんだ!》
ちなみに、鉄道に限らず航空、船舶、装置産業などにおいて、ヒューマンエラー防止のために設計・製造・マニュアル作成に求められる安全原則がある。それは、装置類の操作は所定の教育訓練を受けた平均的な技術を身につけた作業員が、必要な時間内に無理なく処理できるようになっていなければならない、というものだ。特別に高い技術水準にある熟達者でないと処理できないようなシステムであってはならないとされている。
この安全原則に照らして、JR西日本の各路線における「基準運転時分」と「停車時分」の決め方を評価するなら、少なくとも宝塚駅〜尼崎駅間のダイヤの設定に関しては、全運転士が一人残らずストレスを感じることもなく対処できるようにはなっていなかったと言わざるを得ないだろう。木下の怒りは、当然のことだった。
〈 107人死亡の“凄惨な電車事故”を起こしたJR西日本は「人が死んでるのに、問題をなかったことにしようと…」遺族が対応に“不満”を覚えたワケ 〉へ続く
(柳田 邦男/ノンフィクション出版)
関連記事(外部サイト)
- 【続きを読む】107人死亡の“凄惨な電車事故”を起こしたJR西日本は「人が死んでるのに、問題をなかったことにしようと…」遺族が対応に“不満”を覚えたワケ
- 【あわせて読む】「電車のスピードが速い」「立っていられない」107人死亡の“凄惨な電車事故”はなぜ起きたのか? 息子を亡くした父親が指摘した、“過密ダイヤ”の実態
- 【衝撃写真】ブルーシートには血まみれの人たちが…107人が死亡した“凄惨な電車事故”の事故現場を見る
- 【画像】グチャグチャになった車両から救出される乗客
- 「白いスカートが血で赤く染まり、呼吸困難に陥りそうに…」107人が死亡した“凄惨な電車事故”19歳女子大生が語った、事故直後の壮絶な状況