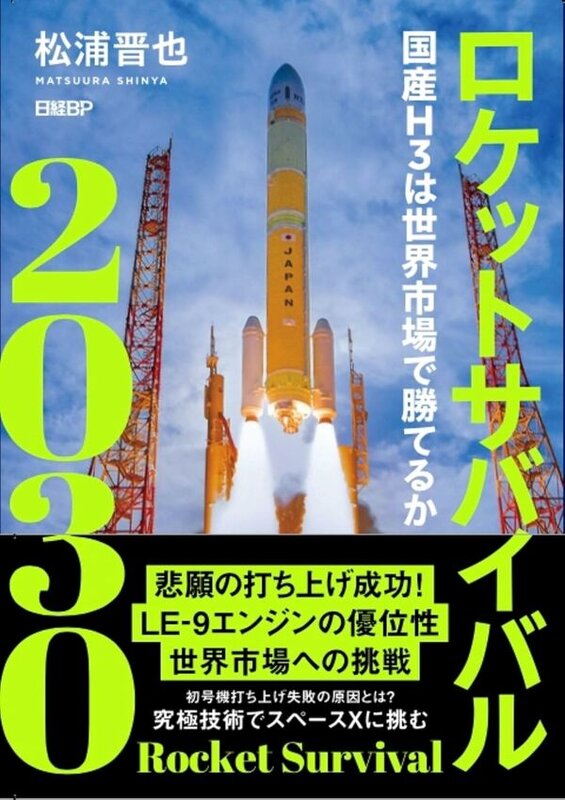トヨタやホンダも打つ「宇宙産業への布石」 開発者が挑む「ロケットエンジンに棲む魔物」とは?
2025年5月14日(水)6時0分 JBpress
イーロン・マスク氏が設立したスペースX社のロケット「ファルコン9」は、それまでの世界の宇宙ビジネスを根底から変革した。一方、日本のJAXAと三菱重工が開発した「H3ロケット」は、それまでのロケットエンジン技術の通説を覆し、新たな可能性を生み出したという。ファルコン9が巻き起こした変革、そして、日本の技術を結集したH3ロケットの戦略とは──。2024年12月、著書『ロケットサバイバル2030 国産H3は世界市場で勝てるか』を出版したノンフィクション作家で科学技術ジャーナリストの松浦晋也氏に、ファルコン9の革新性や、日本が宇宙産業に見いだすべき「勝ち筋」について聞いた。
スペースXは「ロケットビジネスを根底から変えた」
——著書『ロケットサバイバル2030』では、イーロン・マスク氏が設立したスペースX社のファルコン9について触れています。ファルコン9はどのような点が画期的なのでしょうか。
松浦晋也氏(以下敬称略) ファルコン9の最大の特徴は、ロケットの第1段を「回収・再利用する」ことです。現在の人工衛星打ち上げ用ロケットは2〜3段式の構成が主流となっていますが、そのうち第1段は最初に燃焼して機体を押し上げる重要なパートです。その第1段を回収・再利用することで、打ち上げコストの削減を狙っています。
それまでのロケットは、打ち上げた機体を宇宙空間などに投棄する「使い捨て型」が主流でした。しかし、ファルコン9はエンジンの逆噴射を活用し、最も大容量でコストの高い第1段ロケットを地上に軟着陸させて回収することに成功し、回収・再利用型を実現しました。
加えて、回収・再利用型のロケットには、もう1つの目的があります。それは、高頻度の打ち上げを可能にすることです。ロケットの第1段を回収・再利用することで、自社ロケットの生産能力を超えた高頻度の打ち上げが可能になるのです。
その結果、多数の小型人工衛星を何度も打ち上げる必要のある「衛星コンステレーション」を構築する需要に応えることができます。衛星コンステレーションとは、多数の小型人工衛星を同時に打ち上げ、それぞれを連携させ、一体として運用する衛星群を指します。
こうした需要の高まりに対応したことで、宇宙関連ビジネスの急速な発展につながりました。
スペースXが自ら衛星ビジネスを始めた「壮大な理由」と「巨大なリスク」
——スペースXは宇宙関連ビジネスの発展にどのように寄与したのでしょうか。
松浦 スペースXでは、「スターリンク」と呼ばれる、初期段階で衛星4000機以上、将来的には1万2000機以上の小型人工衛星で構成される「通信衛星コンステレーション」を構築するプロジェクトを、自ら立ち上げました。つまり、自ら自社サービスの需要をつくった、ということを意味します。このプロジェクトは2014年に開発が始まり、2019年からファルコン9を使ったスターリンク衛星の打ち上げを開始しました。
この手法は、一方のビジネスが失敗すれば共倒れになる危険性もあります。その意味では、同社は大きなリスクを背負い始めたビジネスとも言えます。しかし、結果としてスターリンクのビジネスは成功を収めました。2023年、ファルコン9は100回近く打ち上げられ、そのうちの3分の2が自社で製造したスターリンク衛星の打ち上げとなっています。
近年、小型衛星開発のベンチャー企業をはじめとした宇宙産業への参入者が爆発的に増えて競争力が激化し、そこに莫大な資金が集まるという、宇宙産業の好循環構造が生まれています。
——スペースXは大きな賭けに勝ったわけですね。同社は前例のないプロジェクトにおいて、どのように人材を集めたのでしょうか。
松浦 ファルコン9は、イーロン・マスク氏がスペースX社を設立した際にヘッドハンティングした、米自動車部品メーカー「TRW」の宇宙部門エンジニアたちによって造られた技術を基にしています。
当時の米宇宙開発事業はNASAや軍といった官需を中心としていました。そのため、民間企業のエンジニアが良いアイデアを持っていても自由に開発できず、不満が溜まっていたそうです。それを知ったイーロン・マスク氏が優秀なエンジニアをヘッドハンティングし、スペースXで彼らがやりたい開発を思い切りやらせました。そして、それが大成功したわけです。
そのように考えると、ファルコン9はエンジニアがやりたかったことを全て詰め込んだビジネスといえます。エンジニアの情熱と力を引き出したという点では、イーロン・マスク氏の技術を見る目は確かだったのかもしれません。
「究極の使い捨て型」を目指すH3ロケットの戦略
——著書では、H3ロケットが「究極の使い捨て型」を目指していることに触れています。そこにはどのような戦略があるのでしょうか。
松浦 究極の使い捨て型とは、打ち上げたロケットを回収せずに徹底したコスト削減を図った上で、商業用ロケットに求められる基本価値である「安全性」「定時性」を達成しよう、というものです。その切り札は、メインエンジンにシンプルで低コストな「エキスパンダー・ブリード・サイクル」という形式を採用した点にあります。
ロケットエンジンは燃焼サイクルの方式によって、いくつかの型に分けられます。その中でエキスパンダー・ブリード・サイクルは、高温ガスを生成するための副燃焼室が不要になるなど、構造やプロセスが非常にシンプルです。そのメリットとしては、安全性・安定性が高いことや、部品点数が少ない分コストダウンにつながることが挙げられます。
一方で、エキスパンダー・ブリード・サイクルは大型のロケットで必要となる100トンfというような大きな推力が出しにくく、「H3のような大型ロケットの第1段エンジンには向かない」と言われていました。
しかし、H3ロケットでは「安全性」「定時性」「低コスト」の全てを満たすために、通説を覆し、エキスパンダー・ブリード・サイクルをメインエンジンに採用する決断をしたのです。
——通説を覆し、メインエンジンの形式を変更する決断をした背景には、どのような出来事があったのでしょうか。
松浦 きっかけは、H3の先代機「H-Ⅱ」ロケットの打ち上げ失敗事故です。打ち上げ失敗の原因は、打ち上げ後に第1段ロケットのポンプが破損し、推力を失ったことでした。その際、エキスパンダー・ブリード・サイクルを採用していた第2段ロケットも分離後に大きく姿勢を崩し、複雑な回転をしながら落下していきました。
これを地上で見ていたJAXAと三菱重工のエンジニアは「第1段、第2段共に推力を失った」と見ていました。しかし、損傷した機体から送られてきた電波データを調べると、第2段のエンジン自体は正常に起動し、推力を発生していたことが分かったのです。
この事実を発見したエンジニアたちは驚き、その理由の解析を始めます。その結果、非力と見られていたエキスパンダー・ブリード・サイクルが、実は極めて堅牢で、安定性・安全性に優れていることが分かったのです。しかも、構造がシンプルであるため製造コストも低く抑えることができます。
こうしたきっかけで、大型ロケットの第1段用のメインエンジンにエキスパンダー・ブリード・サイクルを採用するための研究が始まりました。現在ではエキスパンダー・ブリード・サイクルを用いてコストを抑制しつつ、第1段エンジンとして十分に使える推力を出せるまでになっています。
このように、ロケット開発における技術開発は、時として失敗を繰り返しながらもひるむことなく、むしろ失敗の中に光を見い出すことで前進することが重要なのではないか、と考えています。
「燃焼現象という魔物」を飼い慣らせるか
——世界の宇宙産業は競争が激化すると同時に、大きな潮目を迎えています。今後の日本にとって、宇宙産業の発展はどのような意味を持つのでしょうか。
松浦 日本の製造業はこの30年で衰退の一途をたどり、深刻な状況に陥っています。過去に世界を席巻した家電やロボット、半導体も非常に厳しい状況です。自動車産業も電動化という大激震の波に襲われています。
そうした中で、宇宙産業は日本の強みを生かすことのできる新しい産業分野になるのではないか、と考えています。
その理由の1つは、「日本の中小企業の力」です。日本には質の高い部品を製造・供給できる中小企業が集積しており、多くのサプライチェーンが存在しています。宇宙産業にとって、この力は非常に強い味方になります。
もう1つの理由は、自動車産業で培った「燃焼技術のノウハウ」です。日本の自動車産業がここまで発展した背景には、日本の自動車企業が燃焼という物理現象を深く追究・解明してきたことがあります。それができたからこそ、日本の自動車産業は世界に誇れるようになったのです。
しかしながら、燃焼という現象は、必然的に二酸化炭素を排出します。自動車産業が電動化の方向に向かう中、「燃焼技術のノウハウ」を最大限に生かせる有力な分野として、「宇宙産業」があるのではないかと考えています。地球の重力に逆らう力を出せるロケットエンジンを電動化することは、どう考えても難しいからです。
例えば、トヨタやホンダは「宇宙産業への進出の布石」を確実に打っています。そこにはさまざまな理由があると思いますが、自分たちがこれまで解明してきた燃焼についての知見・技術を活用するための展望があるのではないでしょうか。
ロケットの開発者や技術者たちは「ロケットエンジンの開発には魔物が棲む」と話します。その魔物の正体は、燃焼という物理現象です。ロケット開発とは、その魔物を飼い慣らし、魔物と協力するプロセスなのです。そして、日本のロケット開発者・技術者たちは、失敗と挑戦を繰り返しながら、それを達成してきました。
燃焼という観点からひもとくと、そこには日本産業の強みが見えてきます。今後、政府と民間企業が力を合わせながら、いかにして燃焼の技術を生かして高付加価値産業を興せるか、という視点が重要になるのではないでしょうか。このように考えるからこそ、「宇宙産業を考えること」が今後の日本の産業の在り方を考える上で重要なヒントになると考えています。
筆者:三上 佳大