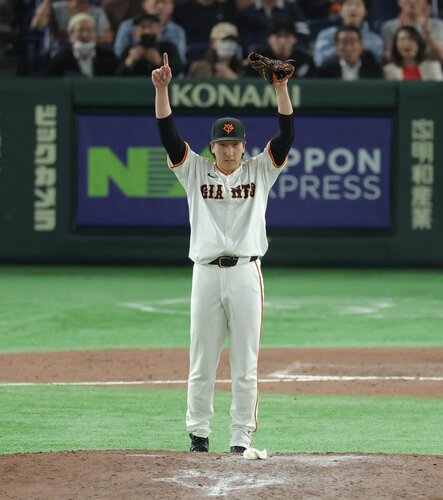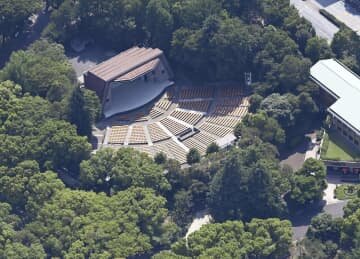何をしても砂を噛むようで、味気ない「老境のむなしさ」にも付き合い方がある 《元フォークルの精神科医・きたやまおさむ氏が告白》
2025年5月2日(金)7時0分 文春オンライン
◆◆◆
「喜怒哀空楽」としてもいい
人間の様々な感情を表す日本語に「喜怒哀楽」がありますが、私は「喜怒哀空楽」としてもいいのではないかと思っています。
空虚の“空”、すなわち「むなしさ」です。

自分の人生に意味はあるのか。自分に存在価値があるのか。何をしても砂を噛むようで、味気ない……。
ふと訪れるむなしさは、誰にでも覚えのあるものでしょう。
とりわけ若い頃はこうした感覚に敏感ですし、なんとか打ち消そうと苦闘して余計にむなしくなる。
私自身、大学時代に「ザ・フォーク・クルセダーズ」(フォークル)の一員として突然芸能界デビューすることになり、むなしさに圧倒されていました。表舞台の自分と普段の自分とではどちらが本当の自分なのか、日常の自分には価値があるのだろうか、と。結局、フォークルは一年足らずでメジャーとしての活動を終えて解散しました。
その後、作詞家として『戦争を知らない子供たち』という歌を手がけもしましたが、1946年生まれで戦争を知らない世代の私も、78歳となりました。
今では、むなしさも喜怒哀楽のようにあって当たり前の感覚だと考える一方で、人生を総括してもう取り返しがつかないと噛みしめるような、いうなれば「老境のむなしさ」も感じています。
2024年に『「むなしさ」の味わい方』(岩波新書)という本を出したところ、読者から、後期高齢者の妻が突然むなしいという言葉を発したため本書を手にした、というレビューをいただきました。
私はこれを「むなしさを味わいやすい年頃になったという発露でもあるな」と捉えました。若いうちはあまりにむなしさが痛みに満ちていて逃げてきたのかもしれませんが、ようやく慣れてきたのでしょう。
むなしさを味わうのは、人生を豊かにするために重要なことです。逆に味わわずに人生を終えるのは、自分が有るという「有り難さ」を噛みしめないことでもあります。
そこで、年を重ねた私が考える、むなしさをめぐるお話に少々お付き合いいただければと思います。
仕事や若さを失うむなしさ
むなしさは、大まかに分けると2種類あります。外的なむなしさと、内的なむなしさです。
外的なむなしさの代表例は、愛している人が去るとか亡くなることです。老境になると家族や友人の死が身近になりますし、子どもが成長して巣立っていったことに空虚感を覚える「空の巣症候群」というものもあります。
定年退職などで仕事を失うことも外的なむなしさですし、日本の景気が自分の若かりし頃のようには二度と戻らないと実感するのもこの範疇に含まれるかもしれません。自分という存在の外側に空虚なものができてしまうケースです。
物事を失う機会は、年を取るほど増えていきます。「ある」ばかりだったのが、若さを失うのとともに「ない」が増えていくのです。
内的なむなしさは、自分の内側に生じる空虚さで、多くの場合は外的なむなしさと連動して起こります。一体感が強かった身近な人が亡くなれば、相手の死は、生きている意味を見失うような自分自身の喪失にもつながります。
また、仕事一筋だった人が仕事を失うことで、アイデンティティを喪失するケースは少なくありません。私という存在が必要とされているという事実ほど、生きがいにしやすいものはないためです。
こう語る背景には、個人的な喪失体験があります。
私は医学生の頃、親友の加藤和彦らと結成したアマチュアバンドで活動していました。それがフォークルです。大学3年生になってバンドを解散しようということになり、解散記念に自主制作した300枚のアルバムが話題となって、突然メジャーデビューすることになったのです。
その300枚のアルバムに入っていた曲『帰って来たヨッパライ』がシングルカットされるや、約280万枚を売り上げ、オリコンチャート初のミリオンセラーとなりました。
当時の私はショービジネスのむなしさに圧倒されながらも、それが深刻化する一歩手前で学業の道に戻ったのでした。
一方で芸能界に残った加藤は、最終的にはむなしさに飲み込まれてしまったのかもしれません。「ロックンローラーが60歳を超えても生きているのは格好悪い」と語っていた彼は、62歳で自死しました。
(取材・構成=秋山千佳)
※このインタビュー全文(約7100字)は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています(きたやまおさむ「 むなしさにも付き合い方がある 」)。
(きたやま おさむ/文藝春秋 2025年4月号)
関連記事(外部サイト)
- 「高見沢クン、やってみなよ!」「おいおい、眉毛は剃るなよ〜」女子高生に感化されたTHE ALFEE“知られざる青春時代”【独占インタビュー】
- 「僕は中高時代とにかく挨拶ができなかった」養老孟司が「心」という言葉を使わない理由《臨床心理士・東畑開人対談》
- 「最後はスタッフから『もう無理』と…」THE ALFEEが明かした“時効の話” 10万人ライブ解散説、アンコール7回、横浜で警察から…【デビュー50周年】
- 「ユーミンの曲は“除湿機能”を備えていた」「尾崎豊は若者の演歌」五木寛之らが厳選した“昭和歌謡の名曲”とは
- 作詞家50年・松本隆「アンチの人がなにを言おうと『君たち、僕らの風呂敷の上に乗っているよ』と言いたい」