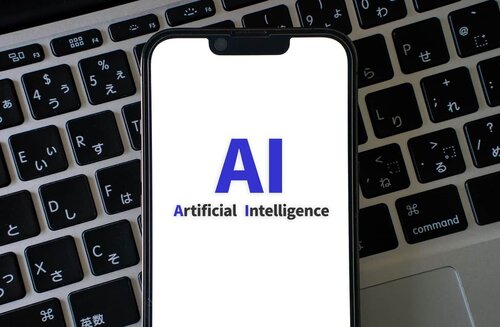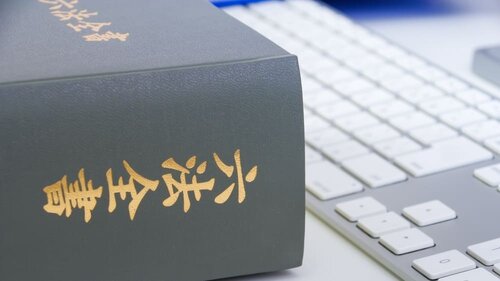朝ドラ『虎に翼』主人公のモデル・三淵嘉子の後半生、渡米、再婚、原爆裁判を担当、女性初の判事、裁判所長に
2024年8月19日(月)8時0分 JBpress
NHK連続テレビ小説『虎に翼』は、日本史上、初めて誕生した女性弁護士の一人にして、初の女性判事、初の女性裁判所長となった三淵嘉子をモデルとするオリジナルストーリーである。
SNSでも話題で、大変に評価が高いため、途中から視聴をはじめた方も少なくないだろう。
途中から視聴した方も、初回から視聴している方も、これから視聴する方も、よりドラマを楽しめるように、伊藤沙莉が演じる主人公・猪爪寅子のモデル三淵嘉子の人生を、ご紹介したい。
なお、ドラマのタイトル『虎に翼』は、中国、戦国時代末期の法家で思想家の韓非(生年不詳〜紀元前233、234年頃)の論文集『韓非子』「難勢」に登場する言葉で、「もともと強い者に、さらに強さが加わる」ことのたとえである。
文=鷹橋 忍
裁判官にはなれず
昭和22年(1947)3月、三淵嘉子は司法省人事課に赴き、松山ケンイチが演じる桂場等一郎のモデルではないかといわれる石田和外に、「裁判官採用願」を提出した。
当時、「女性不採用」という法律上の規定は存在しなかったが、司法官(裁判官、検察官)になった女性は、まだ一人もいなかった。「裁判官採用願」を提出した女性も、三淵嘉子がはじめだった。
二ヶ月後の5月3日から執行される日本国憲法では、男女平等を謳っている(公布は前年の昭和21年(1946)11月3日)。
「ならば、女性も裁判官に採用されるはず」と、嘉子は考えたのだ。
石田和外は、東京控訴院(現在の高等裁判所に相当)の院長・坂野千里に相談し、嘉子を坂野千里に面接させた。
だが、坂野からは、「女性裁判官が初めて任命されるのは、新しく最高裁判所が発足してからのほうがふさわしい(当時はまだ、最高裁判所は発足されていなかった)。弁護士と裁判官の仕事は異なるので、しばらくの間、司法省の民事部で勉強していなさい」と告げられた(『追憶のひと三淵嘉子』所収の遺文 三淵嘉子「私の歩んだ裁判官の道——女性法相の先達として——」)。
こうして、嘉子は裁判官になることは叶わなかったが、同年6月、司法省の嘱託として採用され、民事部の民法調査室に配属された。
不満を抱えながらも、多くを学ぶ
司法省民事部の民法調査室において、嘉子は日本国憲法に基づく、民法改正作業の手伝いをした。
民法の改正作業が一区切りつくと、昭和23年(1948)1月に、嘉子は最高裁判所(日本国憲法執行と同時に発足)の事務局(現在の事務総局)の民事部へ移動となる(神野潔『三淵嘉子 先駆者であり続けた女性法曹の物語』)。
昭和24年(1949)1月、離婚問題など家庭に関する事件を扱う「家事審判所」と、未成年者の事件を扱う「少年審判所」が統合された家庭裁判所が全国49カ所に設立されると、嘉子は最高裁判所の中に設けられた「家庭局」に配属となる。
家庭局の局長は、家庭裁判所の設立に尽力し、「家庭裁判所の父」と称された宇田川潤四郎である。
宇田川は、滝藤賢一が演じる多岐川幸四郎のモデルでないかといわれる。
「私の歩んだ裁判官の道——女性法相の先達として——」によれば、嘉子は最高裁判所事務局民事部や家庭局で、民事訴訟や家庭裁判所関係の法律問題や司法行政上の業務に従事した。
裁判官になれず、多少の不満は抱いていたようだが、「先輩の法曹たちから裁判官のあり方や裁判の意義など、多くのことを学べた。その経験は、後に裁判官としての根幹となった」と述べている。
日本で二番目の女性裁判官に
嘉子は懸命に働き、裁判官に必要な経験や知識を積み上げていった。
その能力は認められ、嘉子は昭和24年(1949)8月、34歳の時、東京地方裁判所民事部の判事補に任命され、日本で二番目の女性裁判官が誕生した(女性初の裁判官は石渡満子、女性初の検察官は門上千恵子。同年4月に採用)。
こうして、嘉子の裁判官としての人生がはじまった。石田和外に「裁判官採用願」を提出してから、約二年半の月日が流れていた。
嘉子は東京地方裁判所民事六部の所属となった。
民事六部の裁判長・近藤完爾は、着任した嘉子に対して、「あなたが女であるからといって特別扱いはしませんよ」と、はじめに告げたという。
本当の意味での男女平等を実現するためには、「職場における女性に対しては女であることに甘えるなといいたいし、男性に対しては職場において女性を甘えさしてくれるなといいたい」と考える嘉子にとって、近藤の言葉は嬉しいものだったのだろう。
嘉子は近藤のことを、「裁判官生活で最も尊敬した裁判官」と称し、近藤のもとで、明るくのびのびと仕事に励んでいった(三淵嘉子「私の歩んだ裁判官の道——女性法相の先達として——」)。
アメリカへ
昭和25年(1950)5月、嘉子はアメリカの家庭裁判所制度視察団のメンバーに選ばれ、アメリカへ渡った。
嘉子の留守は半年に及んだが、このとき小学校二年生だった嘉子の息子・和田芳武は、寂しい思いをしたと語っている(佐賀千惠美『人生を羽ばたいた〝トラママ〟 三淵嘉子の生涯』)。
なお、ドラマではこの頃、主人公・佐田寅子(旧姓・猪爪寅子)とその娘・佐田優未は、寅子の親友で義理の姉(亡兄の妻)・森田望智が演じる猪爪花江とその子どもたちや、寅子の実弟・三山凌輝が演じる猪爪直明と暮らしているが、嘉子と息子の芳武は、嘉子の二番目の弟・武藤輝彦とその妻・温子と同居していたという。
初の女性判事に
裁判官はまず「判事補」に任命され、その後、10年の実務を経験して、「判事」に昇進するのが、普通だという。
判事補であった嘉子も、昭和27年(1952)12月、判事となった。
嘉子は判事補となってから3年あまりであったが、弁護士であった期間も足して、10年と認められたのだ。日本初の女性判事の誕生である。
当時、東京で勤務していた裁判官は、判事になったタイミングで、地方へ転勤するのが通例だった(以上、清永聡編著『三淵嘉子と家庭裁判所』)。
嘉子も、小学校四年生の息子・芳武を連れて、名古屋地方裁判所へ転勤している。
初の女性判事の赴任は名古屋でも注目の的であり、駅前の電光掲示板のニュースに流されたという(『追憶のひと三淵嘉子』所収 大脇雅子『名古屋時代の和田(三淵)判事』)。
名古屋では六畳二間の官舎で、芳武と住み込みのお手伝いさんと、三人で暮らした。
岡田将生が演じる星航一のモデル? 三淵乾太郎と再婚
昭和31年(1956)5月、嘉子は東京に転勤となり、東京地方裁判所判事で勤務することとなった。
同年8月、嘉子は岡田将生が演じる星航一のモデルといわれる三淵乾太郎と再婚し、三淵姓を称するようになる。
嘉子41歳、乾太郎50歳の時のことである。
乾太郎も裁判官であり、沢村一樹が演じるライアンこと久藤頼安のモデルといわれる内藤頼博と同期で、嘉子と結婚した時には、最高裁判所の調査官に就いていた。
ドラマの星航一と同じように、乾太郎も戦時中、総力戦研究所のメンバーに選ばれている。
乾太郎は昭和30年(1955)に妻と死別しており、亡き妻との間には長女・那珂、次女・奈都、三女・麻都、長男・力の三女一男が生まれていた。
乾太郎の父・三淵忠彦は、ドラマの星航一の父親・平田満が演じた星朋彦と同じく初代最高裁判所長官を務め、昭和25年(1950)に亡くなっている。
いつ誰が嘉子と乾太郎を引き合わせたのか、実はよくわかっていないというが(神野潔 『三淵嘉子 先駆者であり続けた女性法曹の物語』)、内藤頼博は、「亡き忠彦の妻・静が、乾太郎の後添いとして、嘉子に白羽の矢を立てた」と述べている(『追憶のひと三淵嘉子』所収 内藤頼博「三淵さんの死を悼む」)。
嘉子と乾太郎は、どちらも転勤を伴う裁判官であったため、別居の期間も少なくなかったようだが、仲は睦まじかったという。
原爆裁判を担当
「原爆裁判」とは、昭和30年代、原爆投下の違法性が初めて法廷で争われた国家賠償訴訟の通称名である。
嘉子はこの原爆裁判を、東京地方裁判所において、第一回の口頭弁論から結審まで、一貫して担当している(判決時は、すでに東京家庭裁判所に異動)。
昭和38年(1963)12月に下された判決では、被爆者への賠償は認めなかったものの、原爆投下を、「国際法違反」と明言している。
裁判官の守秘義務からか、嘉子はこの裁判に関して、回想録などでも何も触れておらず、嘉子の息子・芳武も、内容については何も聞いていないという(以上、山我浩『原爆裁判 アメリカの大罪を裁いた三淵嘉子』)。
初の女性裁判所長に
『追憶のひと三淵嘉子』の年譜によれば、嘉子は再婚した昭和31年の12月から、東京地方裁判所と東京家庭裁判所の判事を兼務した。
48歳の時には、東京家庭裁判所に異動。
その後、昭和47年(1973)6月、58歳の時に、新潟家庭裁判所長に就任。初の女性裁判所長となった。
昭和48年(1973)11月に浦和家庭裁判所長、昭和53年(1978)1月に横浜家庭裁判所長となり、昭和54年(1979)11月、65歳で定年退官した。
退官後は、第二東京弁護士会に弁護士登録し、労働省男女平等問題専門家会議座長、東京家裁調停委員兼参与員などを歴任。
夫の乾太郎と国内外を旅するなど余生を謳歌し、闘病を経て、昭和59年(1984)5月28日に、69歳でこの世を去った。
同年6月23日に、東京の青山葬儀所で行われた葬儀と告別式には、2000名以上が参列した。
会場には、嘉子が好きだったチャイコフスキーの音楽が流されたという。
翌昭和60年(1985)には、乾太郎も亡くなった。
嘉子の遺骨は彼女の生前の希望により、乾太郎が眠る霊寿院(神奈川県小田原市)の「三淵氏の墓」と刻まれた墓と、丸亀にある死別した最初の夫・和田芳夫の墓に分骨された。
茨の道を切り開き続けた女性法曹の先駆者・三淵嘉子は、長い闘いを終え、愛する二人の夫と共に、安らかに眠っているのだ。
筆者:鷹橋 忍