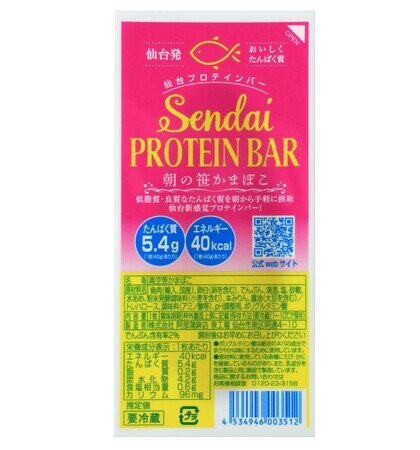逆流性食道炎は「年齢のせい」ではない…脂っこい料理を避けても"イヤな胸やけ"が続く人が摂取しているもの
2025年3月5日(水)17時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Hammarby Studios
※本稿は、比企直樹『100年食べられる胃』(サンマーク出版)の一部を再編集したものです。
■なぜ? 20代も「逆流防止弁」が緩くなっている
一口に、胃の痛み、不快感といっても症状も原因もさまざまですが、胸が焼けるように痛む場合は「逆流性食道炎」が疑われます。
逆流性食道炎とは、胃酸を含む胃の内容物などが食道へ逆流することによって、胸やけや呑酸症状(酸っぱいものや苦いものが込み上げてくるような症状)などを引き起こす病気です。かつては中高年の病気だと思われていましたが、昨今は20代の患者さんも増えています。
胃酸などの逆流は、食べた物が食道から胃に入る入り口にある“逆流防止弁”が破綻しゆるんでしまうことで起こります。食道の壁を荒らすことで症状を引き起こしますが、逆流防止弁をゆるませてしまうのは、喫煙や食の欧米化が原因であると言われています。
よく知られている症状は、胸やけや呑酸ですが、ほかにも次のような症状があります。
■「狭心症のような胸痛」も逆流のサイン
〈みぞおち・胸・背中の痛み〉
逆流防止弁がある噴門部はちょうど「みぞおち」あたりです。逆流性食道炎でこの部分に炎症が起きた場合には、みぞおち、胸、背中に痛みを感じることがあります。また、人によっては狭心症のように、胸が締め付けられるように痛む場合もあるようです。
写真=iStock.com/Hammarby Studios
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Hammarby Studios
〈喉がいがらっぽい、咳が出る、声がかすれる〉
逆流した胃酸が喉に炎症を起こすと、喉がいがらっぽくなったり、頻繁に咳が出たり、喉が痛くないのに声がかすれたりします。
〈喉・胸に何かがつかえているように感じる〉
喉や胸に何かがつまっている、あるいはデキモノがあるかのように、飲食物がうまく落ちて行かない感じがします。
ひと言で逆流性食道炎と言っても、その症状は、胸が焼けるような痛みに限らず、いくつもの症状があるのです。
■「薬が効かない」十二指腸液の逆流
逆流性食道炎とは、食べた物が胃に入る入り口にある逆流防止弁が、破綻しゆるんでしまうことで、胃酸が逆流して食道の壁を荒らす病気——ですが、逆流する液は、胃酸に限りません。
というのも、通常は戻ってこないはずの十二指腸液という、胆汁と膵液が混じった、最も強力なアルカリ性の消化液が胃にまで戻ってきて、さらに胃酸も加わったものが一緒になって、食道まで戻ってくることがあるのです。
すさまじく組織障害性が高いこの消化液によって組織が障害されると、胸やけや吐き気がしたり、ひどい場合は胸痛があらわれます。
アルカリ性である十二指腸液が逆流してしまうのがなぜ厄介なのかと言うと、胃酸を抑える制酸剤は開発されているので対処法がありますが、アルカリを抑える薬はまだないからです。
しかも、胃酸の逆流もアルカリが混ざった消化液の逆流も、症状は変わらないため、どちらが逆流しているのかが見た目でわかるわけではありません。
どちらが逆流しているのかを知るには、内視鏡検査をする必要があり、黄色い液が戻ってきたら「あぁ、アルカリが戻っているな」とわかります。マノメトリー検査という鼻から管を入れて、十二指腸と胃と食道でpHを測る検査もありますが、それは大がかりな上に、一泊入院しなければならず、できる施設も非常に少なく、患者さんにとっては現実的ではないでしょう。
強烈な組織障害性があり、かつ、コントロールが利かないこの十二指腸液による逆流性食道炎は、私たち消化器の医師としては、非常に「イヤな」症状と言えます。
■「脂肪」より「糖質」が逆流を招く理由
逆流性食道炎が増えている原因としては、まずはストレスによって、交感神経が優位になり、胃・十二指腸の動きが止まってしまうことがあげられます。それにより、たまった消化液を逆流させてしまいます。
それだけでなく、糖質過多の食事、喫煙習慣、刺激物の過剰摂取、内臓脂肪型肥満の増加、ピロリ菌感染者の減少、加齢なども原因としてあげられます。
次のようなさまざまな要因で、逆流性食道炎は起こります。
まず、私が近年注目しているのが「糖質過多の食事」です。
従来は、逆流性食道炎の原因といえば、食習慣の欧米化にともなって脂っこい食べ物(高脂肪食)の摂取が増えたことがあげられていましたが、私は最近、脂っこい食事ではなく、「糖質過多」の食事が原因かもしれないと思うようになりました。
なぜなら、脂肪は、体内に摂取されても、急激に血糖値を上げる糖質と違い、ゆっくりと血糖値を上げます。糖質は、血糖値を上げ、急激に下がる血糖値スパイクを起こしてしまいますが、脂肪の摂取ではそれが起きず、脂肪には、高血糖のあとに低血糖となることを防ぐはたらきがあるからです。
一方、糖質過多の食事は、「血糖値スパイク」により、低血糖を招きます。低血糖は交感神経を優位にさせて、消化管の動き(消化管蠕動)を低下させてしまい、逆流に直結してしまうのです。
■「喫煙」が逆流防止弁をゆるませる
喫煙は、消化管の機能や環境にさまざまな影響を及ぼし、逆流性食道炎を引き起こす要因になります。
特に悪さをするのはタバコの煙に含まれるニコチンという化学物質です。
ニコチンは、食道と胃の間にあって、胃酸が食道に逆流するのを防いでいる「下部食道括約筋」をゆるめ、胃酸が食道に逆流しやすくします。
また、ニコチンは胃酸の分泌量を増加させるいっぽうで、唾液の分泌量を減少させてしまいます。さらには、食道粘膜の防御機能を低下させる、腹圧を増加させるといった作用もあり、いくつもの点で逆流性食道炎のリスクを高めてしまいます。
アルコール摂取、コーヒーなど刺激物の過剰摂取なども症状を悪化させる要因とされています。刺激物、特にカプサイシンは適量であれば逆流を低下させてくれますが、摂り過ぎた場合は胃酸を過剰に分泌させて、逆流を誘発する可能性があるからです。
写真=iStock.com/Rattankun Thongbun
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Rattankun Thongbun
■タバコとお腹の脂肪が胃を押し上げる
胃や腸の周辺につく内臓脂肪が増えると、お腹の圧が高まって、胃を外側から押す力が高まります。
内臓脂肪が増えている状態は、胃を風船とすると、周囲からの圧によって、食べた物が中に入っても膨らみにくい状態です。胃が外側から押されて、逆流しやすくなるのです。内臓脂肪は加齢と共に増加する傾向があります。
かつて日本人の大半はピロリ菌に感染していて、「萎縮性胃炎」を起こすことによって、胃酸の分泌量が普段から低下していました。そのため、逆流する胃酸自体が少なかったので、逆流性食道炎もほとんどなかったと言われています。
ところが昨今は、日本の環境が清潔になったことでピロリ菌への感染が減り、胃がんのリスクを下げるために積極的に除菌する人が増えたことで、ピロリ菌の感染率は激減して、胃酸の分泌量は正常レベル近くまで回復しました。以前は胃酸の分泌が少なかったのが、近年は回復したことにより、その他の理由とあいまって、逆流性食道炎となる方は増えているということになります。
■前かがみ姿勢が胃の出口を「渋滞」させる
いまは年齢に関係なく、若い人の逆流性食道炎も増えているとお伝えしましたが、もともとは高齢者に多い症状と言えます。
というのも、年齢を重ねるほど、消化管蠕動が低下し、消化が悪くなって胃もたれを起こしたり、便秘になったりしやすくなってしまうからです。
また、背中が曲がって姿勢が前かがみになると、胃の出口付近で渋滞した食べ物が、お腹を圧迫されることで逆流してしまうことになります。加齢による全身の筋力低下は、胃にもかかわってくると考えられます。
私は胃の外科医でありながら、栄養状態と筋力の改善が患者さんの回復と健康維持に不可欠と考えて、筋力アップの点でも理学療法士の人たちと連携しています。
さらにもう一つ、逆流性食道炎の原因として見逃されがちなのが「摂食障害」です。摂食障害には、「神経性無食欲症(拒食症)」と「神経性過食症(過食症)」がありますが、後者では、99%以上が逆流性食道炎を併発していると言われています。
過食症の人は、大量に食べた後、自分で口に手を入れて吐いてしまうのですが、これを続けていると、吐くことが癖になってしまい、食道と胃の間の逆流を防ぐ弁が緩くなり、逆流性食道炎を起こしやすくなってしまうのです。
摂食障害は心の病気ですから、摂食障害が原因で逆流性食道炎がある人は、消化器内科ではなく、精神科や神経内科の受診をお勧めします。
■「原因不明の咳」実は胃酸が喉まで到達
逆流性食道炎は、食べたものが胃酸や十二指腸液とともに逆流する病気ですが、逆流したものが食道を越えて喉まで戻ると、喘息のような咳が出ることがあります。
比企直樹『100年食べられる胃』(サンマーク出版)
そんなとき、おそらく多くの方は呼吸器内科や耳鼻咽喉科を受診しますが、その原因は逆流性食道炎なので、肺のCT検査をしても何ら異常がなく、「気のせい」にされてしまうこともあります。
胃酸もしくは十二指腸液が喉に噴き上げて、それを吸い込んだがために咳が出たり、肺炎になったりしている可能性が多々あります。
それは呼吸器内科や耳鼻咽喉科を受診しても原因にたどり着かないことが多く、周囲に、原因不明の咳で悩んでおられる人がいたら、逆流性食道炎の可能性がないかどうか、確認するよう教えてあげてください。
----------
比企 直樹(ひき・なおき)
北里大学医学部上部消化管外科学主任教授
北里大学医学部を卒業後、東京大学大学院医学系研究科修了。その間、ドイツ・ウルム大学や青梅市立総合病院外科などでも医師としての経験を積む。がん研究会有明病院に14年勤務、胃外科部長として日本トップクラスの手術症例数を執刀。「胃がん」における治療法の考案・手術方式の開発は数知れず、世界のスタンダードになっているものも多数。手術だけでなく、治療を支える「栄養」の重要性からがん研有明病院時代には「栄養管理部」を立ち上げ運営。2019年に北里大学医学部上部消化管外科学主任教授に就任後は上部消化管がんの手術に加え、医学部・栄養部合同の「栄養部」を開設、部長も兼任する。次世代ドクターと管理栄養士の指導に携わり、後進の育成に力を入れる。一般社団法人日本栄養治療学会の理事長や日本消化器外科学会の理事などを務める。
----------
(北里大学医学部上部消化管外科学主任教授 比企 直樹)